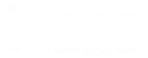【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
皆さんは華やかなピアノ曲といえばどんな曲をイメージしますか?
メロディと伴奏を同時に演奏でき、滑らかに旋律をつなげていくだけではなく、打楽器のように勇壮なリズムを生み出すこともできるピアノは、1台でオーケストラを再現できる楽器ともいわれています。
「美しさ」、「切なさ」、「はかなさ」など、さまざまな側面を持つピアノの音色ですが、今回は明るく力強い華やかな一面を、思う存分味わえる中級レベルの作品をピックアップしました!
穏やかな曲や切ない曲がお好きな方にも、この機会にピアノの新たな魅力を発見して弾いてみていただけたら幸いです。
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【中級者】オススメのピアノ連弾曲|かっこいい&華やかな作品を厳選
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【最新】ピアノソロ中級|おすすめ&人気楽譜をピックアップ
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】チャイコフスキーのおすすめピアノ曲【中級】
- 【ピアノ連弾曲】盛り上がること間違いなし!オススメ作品を一挙紹介
【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!(41〜50)
華やかなワルツGlenda Austin

華やかで優雅なワルツのリズムに乗せて、ジャズの要素が巧みに織り込まれた本作は聴く人の心を魅了します。
流麗な旋律の中にも現代的なアレンジが施され、その洗練された曲調は演奏者の表現力を引き出してくれます。
グレンダ・オースティンの作品はピアノ教室や音楽教育の現場で教材として採用されており、発表会やコンクールでの演奏曲として選ばれることも多い作品です。
本作は、ワルツ特有のリズム感を大切にしながらも、技術的な挑戦と音楽的な楽しさを兼ね備えた楽曲として、小学校高学年の学習者にぴったりの1曲といえるでしょう。
展覧会の絵より「プロムナード」Modest Mussorgsky

ロシア五人組の1人、モデスト・ムソルグスキーによって作曲されたピアノ組曲『展覧会の絵』。
その中でも特にオススメしたい作品が、こちらの『展覧会の絵より「プロムナード」』です。
日本のメディアでも頻繁に使用されているため、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
実はこの作品、ヴィクトル・ハルトマンというロシアの画家が亡くなったことにショックを受けて作られた作品なんです。
そうした背景を持ちながらも華やかな曲調にまとめられているのは、ムソルグスキー自身が画家の死を悼みながらも、展覧会を心から楽しんでいることのあらわれともいえるでしょう。
ハンガリー舞曲 第5番Johannes Brahms

連弾の練習曲として発表会などでも頻繁に耳にするヨハネス・ブラームスの作品『ハンガリー舞曲 第5番』。
誰しも一度は耳にする名曲ですね。
この作品はロマの音楽から強い影響を受けた作品で、のちのジプシージャズにも通ずる旋律がいたるところで登場します。
華やかというよりは激情を感じさせるメロディーですが、中盤には柔らかさも感じる華やかなメロディーにまとめられています。
連弾の華やかさはそのままに、独奏用にアレンジされた楽譜も出版されていますので、ぜひチャレンジしてみてください!
愛の挨拶Edward Elgar

ロマンティックな雰囲気に満ちたこの曲は、1888年にエドワード・エルガーが愛妻キャロライン・アリス・ロバーツへ婚約記念として贈られた作品です。
優美で甘美な旋律が特徴で、結婚式や記念日の音楽としても親しまれています。
ヴァイオリンとピアノのために作曲されましたが、ピアノ独奏や管弦楽版などさまざまな編成で楽しめます。
シンコペーションのリズムが印象的で、緩やかに始まり、中間部で転調し、再び主題が戻って高揚しながら終わります。
愛に溢れたこの名曲は、新しい出会いの季節として春の雰囲気にもぴったりです。
舟歌 Op.60 CT6 嬰ヘ長調Frederic Chopin

「舟歌」とは水の都ヴェネツィアのゴンドラをイメージしたピアノ曲であり、もともとは船頭が船に乗って口ずさんでいた歌が由来なのだとか。
数多くの著名な作曲家が「舟歌」を作曲していますが、なかでも特に有名なのがフレデリック・ショパンの作品!
通常「舟歌」はゆったりとした8分の6拍子で構成されていますが、ショパンの『舟歌』は8分の12拍子を用いて雄大な、そして優雅な雰囲気を演出している点が特徴的です。
陽光に照らされた水面にゴンドラが浮かぶ優雅な風景を想像しながら演奏してみてくださいね。
ピアノ曲集『お菓子の世界』 終曲「お菓子の行進曲」湯山昭

日本を代表する偉大な作曲家の1人、湯山昭さん。
旭日小綬章を受賞している偉人ですね。
そんな彼の作品のなかでも、特に華やかな雰囲気にまとめられている作品が、こちらの『ピアノ曲集「お菓子の世界」終曲「お菓子の行進曲」』。
子供から大人まで楽しめるようにというコンセプトのもと、1973年に作曲された作品ですが、非常におしゃれなメロディのため、子供が歌う童謡などとはまったく雰囲気が異なります。
ジャズやフゲッタを主体としたさまざまなジャンルの旋律が入り乱れる様子を、楽しみながら演奏できるとよいですね。
ピアノソナタ第11番 イ長調 K. 331 第3楽章「トルコ行進曲」Wolfgang Amadeus Mozart

誰もが一度は耳にしたことのある名曲『トルコ行進曲』。
小学生や中学生のころ、ピアノを習っている同級生が弾いていたなんて経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか?
そんな『トルコ行進曲』の魅力は、華やかさと力強さを兼ね備えているところにあります。
華やかな作品というのは、ワルツなどを主体とした柔らかい旋律が一般的ですが、この作品にはメフテル軍楽隊のリズムが取り入れられており、力強さも十分に感じられます。
かっちりとした雰囲気とワルツの軽やかさの両方を、うまく表現できるとよいでしょう。