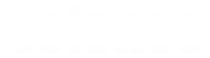【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ
夏休みの自由研究というと、テーマを決めるのが大変で悩んでいる高校生も多いかと思います。
特に自由研究は時間がかかり、大変ですよね。
しかし、ご安心ください!
こちらでは、高校生にオススメの面白い自由研究のアイデアをご紹介いたします。
火を使ったり、少しだけ複雑な研究も含まれており、きっと興味のあるものが見つかるはず。
身近な材料でできる実験や、工作系など、簡単なものから時間のかかるものまで、いろいろあります。
楽しく取り組んで充実した研究にしてみてくださいね。
楽しみながらいろいろなことを学んでくださいね!
- 高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集
- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 【大人向け】簡単だけどすごい工作。オシャレで見栄えのする作品集
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 中学生向にオススメ!短時間でできる自由研究のアイデア集
- 【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ
- 小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
- 簡単だけどすごい工作。小学生が作りたくなる工作アイデア
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 【小学校5年生】自由研究テーマ&工作|学びにつながるアイデア集
【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ(21〜30)
ストームグラス作り

ストームグラスを知っていますか?
日本語では「天気管」といい、ガラス管に入れたアルコールに複数の化学薬品を溶かすと、溶液や沈殿の状態によって天気が予測できるというもので、19世紀に実際に使われていたようです。
夏休みの長期間に渡って天気予報の正確性を検証することに加え、その歴史について詳しく調べてみるのもいいかもしれませんね。
音の秘密をさがしてみよう
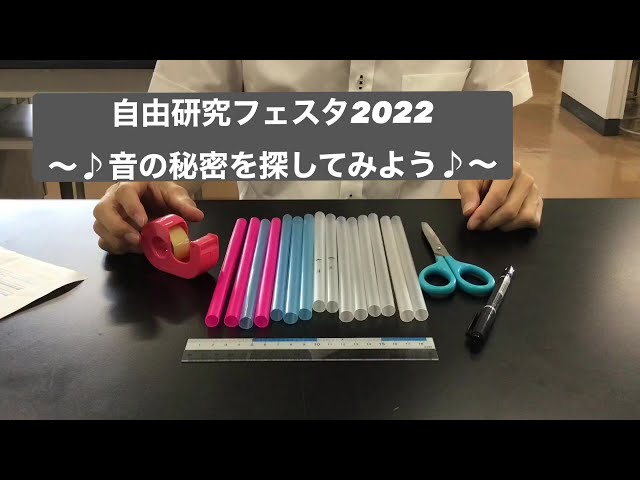
ストローをつなげるだけで作れる、笛のアイデアをご紹介します。
ストローは同じ太さ、長さのものをご用意ください。
拭き口に使うストローは8本ですが、あいだにストローを挟むので、プラスで7本、合計15本用意しましょう。
あいだに挟むストローは5センチにカット。
笛となるストローは音によって長さが変わるので、しっかりと定規で長さを測ってくださいね。
カットできたらストローの片側をテープで塞いで閉管します。
全てつないで接着したら完成です。
どの長さでどんな音がするか、いろいろと実験してみてください。
【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ(31〜40)
不可能立体作り

M.C.エッシャーという画家を知っていますか?
その名前を知らなくても、彼が描いた「だまし絵」による不可能立体は一度は見たことがあるのではないかと思います。
実際には再現できないから「不可能立体」と呼ばれるのですが、見る角度によってこの不可能立体を実際に再現できるんです。
「錯視」と呼ばれる現象は奥が深く、やりがいがありますよ。
作曲に挑戦
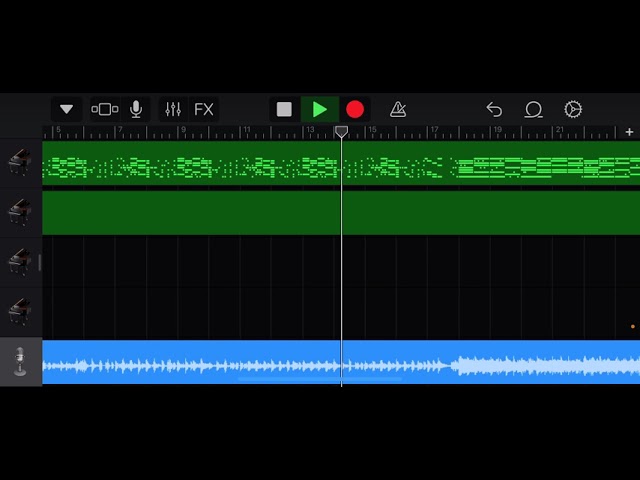
長い夏休みにじっくり曲作りに取り組んでみませんか!
作曲したことがある方もない方も、まずはいろんな曲を聴いてそれぞれがどんな構成で、どんな楽器を使って作られているのかリサーチしてみるところから始めてみましょう。
こんな曲が作ってみたいなというのが決まったら、コードやメロディーの進み方など既存の作品を参考にしながらオリジナルのものを作っていきます。
できたらスマホやDTMのソフトを使って録音し、ディスク化などすれば夏休みの課題が完成です!
オレンジジュースからDNAを取り出す!

植物や動物の身体がDNAで構成されているのは知っていますよね。
しかし、実際にDNAがどんなものなのかと聞かれると答えに困ってしまうのではないでしょうか。
そこでオススメしたいのがDNAに関する研究です。
中でもオレンジジュースからDNAを取り出す実験は手軽ですし、見た目にも楽しいです。
そのやり方はオレンジジュースが入ったコップに、無水エタノールをゆっくり注ぐだけ。
そのメカニズムを調べつつ、取り組んでみてください。
持ち運べる雲?!

持ち運べる雲を作りましょう。
まずペットボトルと線香を用意します。
2Lペットボトルに少し水を入れて、火をつけた線香の煙を中に閉じ込めます。
手で30秒ほどペットボトルに力を加えペットボトル中に気圧の変化を加えます。
すると中の空気が冷めて、水蒸気が生まれます。
その水蒸気が煙とまざることでペットボトルの中に持ち運べる雲ができあがります。
雲は大気中の水分とチリがまざることによりできますが、チリを煙で代用するという形での実験です。
放置するだけの自由研究
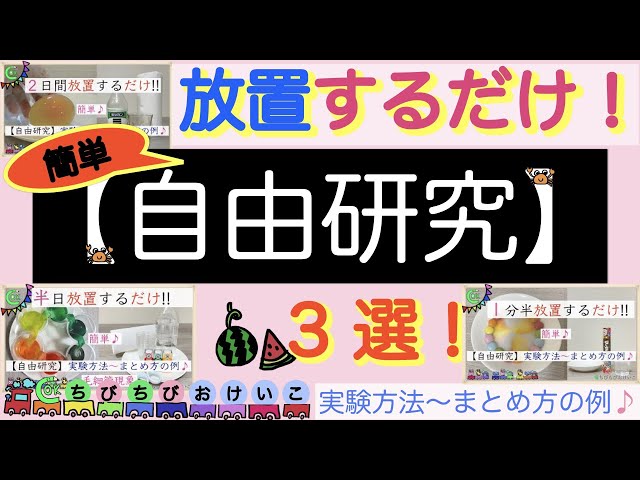
自由研究って何をすれば良いか迷いますし、あまり時間をかけたくありませんよね。
そこで、放置するだけでOKのアイデアに挑戦してみませんか?
こちらでは3つの自由研究を紹介しています。
1つ目は、カラフルにコーティングされたチョコのお菓子を皿のフチに並べ、水を注いでどうなるかを観察するアイデア。
2つ目は、お酢に卵を漬けてスケルトン卵を作るアイデア。
3つ目は、色水にキッチンペーパーをひたし染まる様子を観察するアイデアです。
どれもとても簡単ですので、ぜひ挑戦してみてください。