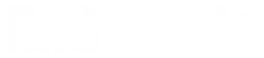日本の作曲家によるクラシック音楽。おすすめのクラシック音楽
クラシック音楽、と言われるとやはり誰でも知っている海外の作曲家による作品を思い浮かべますよね。
日常の場面でアレンジを変えて使われることも多いですし、ごく自然に多くの人が一度は耳にしていてすぐに名前を挙げられる作品は多く存在します。
それでは、日本人作曲家によるクラシック音楽の作品で知っているものを挙げてください、と言われてさっと答えられる方は少ないかもしれません。
ここでは日本人の作曲家が手掛けたクラシック音楽に注目、代表的な作品をピックアップしています。
日ごろからクラシック音楽を愛聴されている方々の中でも、あまり日本人の作品は聴いたことがないな、という方にもおすすめです。
日本の作曲家によるクラシック音楽。おすすめのクラシック音楽(31〜40)
交響曲第1番橋本國彦

1940年に作曲された『交響曲第1番』は『交響曲第1番 ニ長調』と表記されることもあり、皇紀2600年奉祝曲として橋本國彦さんが作曲しました。
プロパガンダの要素が強いとされ、戦後には長らく封印されていた歴史を持つ交響曲です。
親しみやすい管弦楽の雰囲気に、紀元節を意識した要素が取り入れられた作品と語られており、日本太鼓など古来の楽器を使用して演奏される場合もあります。
作曲された当時の情勢を考えるきっかけにもなりそうな交響曲ですね。
交響曲第5番「シンプレックス」池辺晋一郎

第1楽章冒頭でいきなり主要テーマが登場してオスティナート風に展開していきます。
第2楽章はがらりと雰囲気が変わってメロディックになりますが第3楽章でまた執拗なオスティナートが登場します。
「シンプレックス」と題しながらも複雑に展開されていく池辺ワールド全開の曲です。
ピアノ協奏曲三善晃
息つく暇もない疾走感と躍動感がジャズ的な雰囲気も感じさせる曲です。
多様な打楽器が使われていて音色が豊かな曲でもあります。
ピアノもかなり打楽器的に扱われています。
終盤の金管楽器による強烈なファンファーレも非常に印象的です。
チェロ協奏曲尾高尚忠

義弟の倉田高さんのために作曲されましたが戦時中の厳しい状況下にあったため全曲初演は叶いませんでした。
初演が叶ったのは尾高没後20年が経った年で、日本フィルハーモニー交響楽団が行いました。
その時のチェリストは若林洸です。
古典的な3楽章制の保守的な曲でクラシカルな美しさを持つ曲です。
交響曲第1番別宮貞雄

別宮貞雄さんはミヨーやメシアンさんに師事していました。
日本作曲家で交響曲といえば別宮さんと言っても過言ではないでしょう。
第1楽章から終楽章まで全曲を通して聴きどころ満載の名曲です。
特に第2楽章の色彩の豊かさ、第3楽章の凝集力には目を見張るものがあります。