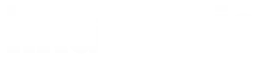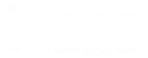【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介
ピアノを習い始めたお子さまがピアノへの興味を失うきっかけの一つ、それは「ピアノって難しい……」と感じてしまうこと。
譜読みが難しくなかなか練習が進まなかったり、指が思うように動かず一向に先生から合格をもらえなかったりすると、興味津々で始めたはずのピアノに対してマイナスな感情を抱いてしまいがちです。
そこで本記事では、子供でも弾きやすい簡単なクラシック作品をご紹介します。
難易度の体感や進み具合は必ず個人差がありますが、お子さまが「ピアノって楽しい!」と感じられるよう、その子に合った曲をピックアップしてみてくださいね。
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲
- 【子ども向け】1本指でピアノが弾ける!おすすめの曲まとめ
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【ピアノでディズニーの名曲を】発表会にもおすすめの簡単な楽曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- ピアノをはじめた初心者におすすめ!大人も楽しめる楽譜10選
- 【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
- 初心者でもピアノで簡単に弾ける!J-POPの人気曲&最新曲を厳選
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介(131〜140)
アヴェ・マリアCharles Gounod

『アヴェ・マリア』という言葉は多くの方が一度は聞いたことがあるはずですし、あの曲だよねと思われる人も多いでしょう。
とはいえ実際に皆さん思う『アヴェ・マリア』が、実は友だちと話してみたら違う曲だった……という経験はないでしょうか。
『アヴェ・マリア』自体はラテン語のカトリック典礼文における一節であり、そこからインスパイアされた楽曲を『アヴェ・マリア』と呼ぶため、世界中にさまざまな『アヴェ・マリア』が存在するのですね。
その中でも1859年にフランスの作曲家、シャルル・グノーが手掛けた『アヴェ・マリア』は知名度の高い声楽曲で、本稿ではそのピアノアレンジバージョンを紹介しています。
非常にシンプルなアレンジで音数も少なめですから、右手と左手の役目が切り替わる部分などに注意しつつゆっくりと練習してみてくださいね。
道化師Dimitri Kabalevsky

子ども向けの楽曲を多く世に送り出した近代のロシアの著名な作曲家、ドミトリー・カバレフスキーの『道化師』は、1944年に作曲されて翌年に出版された作品集『24の子供のためのやさしい小品』に収録されている楽曲。
半音階で進んでいくメロディと、スタッカートを活用した躍動的な左手の伴奏が特徴で、短いながらも聴いている人にインパクトを与えられる作品のため、発表会曲にもピッタリです。
単に音符を追うだけではなく、次々と変化していく楽曲の展開を楽しみながら弾いてみましょう。
ガボットFrançois-Josehp Gossec

テレビ番組やCMのBGMなどでもおなじみの『ガボット』は、もともとはフランスの作曲家フランソワ=ジョセフ・ゴセックによるオペラ作品の中で使われた楽曲。
バイオリンとオーケストラのための作品ですが、現在では簡単なピアノ譜にアレンジされ、子供向けピアノテキストにも掲載されています。
宮廷音楽のような上品さを作り出すスタッカートをやさしい音色で表現しながら、跳躍を含む左手の伴奏を軽やかに演奏するのが、この作品のポイント!
スラーの多いなめらかな中間部で場面をパッと切り替え、メリハリのある演奏を心がけましょう。
ポロネーズ 第13番 変イ長調(遺作)Frederic Chopin

ピアノ発表会でショパンの作品は頻繁に演奏されます。
その中でもとくに演奏されることの多い作品の一つが、こちらの『ポロネーズ 第13番 変イ長調(遺作)』。
華やかな踊りの曲で、演奏効果も高いことで知られています。
技術的には特に難しいというわけではありませんが、ピアノを学んでいくうえで重要となる基礎的な技術が詰まっています。
47小節目から始まるポロネーズの独特のリズムに慣れれば弾きやすくなるので、練習の際は反復練習をしてリズムを身につけてみてください!
ソナチネ ハ長調 Op.157-1 第2楽章「タランテラ」Fritz Spindler

ピアノ作品を得意とする作曲家のなかでも、とくに人気を集めるフリッツ・スピンドラー。
今回はそんなスピンドラーの名作のなかから、こちらの『ソナチネ ハ長調 Op.157-1 第2楽章「タランテラ」』を紹介します。
あっさりとした楽曲で、基礎的なピアノの技術を見せるにはピッタリの作品。
左右のパートのバランスはもちろんのこと、スタッカートやレガートなどの細かい表現が凝縮されているので、ぜひピアノ発表会の選曲としても参考にしてみてください。
クシコス・ポストHermann Necke

この曲を聴くと思わず走りたくなってしまう、そんな方も多いのではないでしょうか?
ドイツの作曲家ヘルマン・ネッケ作曲の『クシコス・ポスト』は、運動会の徒競走のBGMでおなじみの作品ですよね。
管楽器で演奏された華やかなアレンジを耳にすることが多いかもしれませんが、もともとはピアノ曲なんです!
今回ご紹介している楽譜は左手が4分音符ですが、さらに細かく8分音符にして演奏することで、より原曲の軽快な雰囲気に近づけられます。
練習を積み重ねて、どんどんテンポアップしてみてくださいね!
25の練習曲 Op.100 第20曲「タランテラ」Johann Burgmüller

ピアノを練習するうえで誰しも必ずは通る有名な作品、ブルグミュラーの『25の練習曲』。
練習曲のなかでは簡単な部類として知られていますが、初心者にとっては学ぶべき技術が凝縮されています。
今回はその中から難易度の高いこちらの『25の練習曲 Op.100 第20曲「タランテラ」』をご紹介します。
8分の6拍子または、8分の3拍子を主体とした激しい舞曲。
なかでも17小節から始まる2つの8分音符の間の8分休は、長すぎても短すぎてもダメな、絶妙なバランスが求められます。
繊細な演奏を学ぶうえで非常に有用な楽曲といえるでしょう。