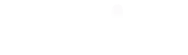動く!遊べる!楽しい折り紙。折り紙おもちゃの作り方
折り紙は子供たちの手先の器用さや集中力を育んだり、完成した喜びや達成感を味わうことができたりと、保育に欠かせない遊びの一つですよね。
今回はそんな折り紙を使った動くおもちゃの作り方を紹介します。
折り紙のみを使って作れるおもちゃを中心に紹介しているので、準備物が少ないのも嬉しいポイント。
子供心を刺激するユニークな動きの折り紙おもちゃがたくさん登場するので、子供たちもきっと夢中になって取り組めますよ!
気になったものを作って、たくさん遊んで楽しんでみてくださいね。
動く!遊べる!楽しい折り紙。折り紙おもちゃの作り方(1〜10)
簡単パクパク魚

パクパクと動く口がかわいい、パクパク魚の作り方をご紹介します。
折り目をつけて折っていく手順が多いので少し複雑かもしれませんが、折り紙1枚で作れるのでぜひ挑戦してみてくださいね!
完成した魚は口をパクパク動かして遊んでももちろん楽しいですが、いろいろな色で魚をたくさん作って、壁に貼って飾ってもかわいいですね!
口の中が小さな空洞になっているので、小さなあめやお菓子などをいれて友達にあげると、とっても喜んでくれそうです!
紙風船

折り紙で作る定番のおもちゃのひとつと言える、紙風船を折ってみましょう。
定番の折り紙の紙風船は、折る手順は多いですが一つひとつ順を追って進めていけば完成します。
紙風船ってどうやって作るんだろう?
と作り方がわからなかった方もゆっくり折れば完成するので、お子様もご高齢の方もぜひトライしてみてください。
完成した紙風船はそっと息を吹き込めば、ふわっと膨らみます。
飾ってもよし、ポンポンと投げて遊んでもよし、出来上がりもとっても可愛らしいので作ってみてくださいね。
パクパク

いろんな遊び方ができて折り紙だけで完成する、パクパクする動きが楽しいおもちゃを作ってみましょう。
折り方を覚えておけば、折り紙一枚あればいつでもどこでもお友達や家族と楽しく遊べるおもちゃなので、ぜひマスターしてみてくださいね。
折り方もシンプルなので小さなお子様でも、ご高齢の方でも作っていただけます。
出来上がったら片手でパクパクするのもいいし、両手を使ってパクパク動かすのもいいですね。
いくつかの質問と答えなどをそれぞれの面に書いておけば、ちょっとした心理ゲームのような遊びもできますよ。
動く!遊べる!楽しい折り紙。折り紙おもちゃの作り方(11〜20)
くるくる折り紙

風を受けながら、くるくると落ちていく様子が楽しい折り紙遊びです。
一つ目はメガネのような形の輪っかの折り紙、二つ目は魚のような形の折り紙、それから、不思議なブーメランのような形の折り紙です。
それぞれ、風の受け方や回転の仕方が違うので、観察すると楽しいですよ。
折り紙とのり、ハサミだけでできる手軽さが嬉しいですね。
ハサミで紙を切る作業、のりを付ける作業などもシンプルなので、小さなお子さまでも自分のオリジナルを作る達成感を味わえますよ。
スリンキー

伸びたり縮んだりバネのような不思議な動きがおもしろいスリンキーを、折り紙で作ってみませんか?
折り紙を4等分にした一枚で作るのですが、折った線が大切なので、折る時は折り線を意識しながらしっかりと折ってくださいね!
シンプルな折り方なのと、1つ折ると後は同じのを数枚作ってつなげていく作業になるので、楽しく作れると思います。
作ったパーツはらせん状にくるくるとつなげていくのですが、枚数に決まりはないので、好きな数をつなげてみましょう!
最後に表と裏に折り紙を貼り、好きな顔や絵をかいたらおもしろいスリンキーの完成です!
こま

同じ大きさの3枚の折り紙で作る、コマのおもちゃをご紹介します。
分かりやすい折り方なので、手順を丁寧に追っていけば小さなお子様からご高齢の方まで、楽しく折っていただけます。
3枚の折り紙はそれぞれ違う色を用意すると、出来上がりがとてもカラフルです。
コマがくるくる回るときれいなので、好きな色を選んでくださいね。
それぞれを折っていったら、3つのパーツを重ね合わせて組み立ててください。
少し重みがあることがコマとしてよく回るポイントです。
完成したらお友達や家族と回して遊んでみましょう。
ぴょんぴょんうさぎ

折り紙の楽しいところは折っているその時間はいうまでもなく、折ってからも鑑賞したり遊んだりできるところ。
帆かけ舟を作ったらビニールプールの上に浮かべたり、風車を作ったら風に向けて回したりと、楽しい時間がずっと続きますよね。
ここで紹介するのは「ぴょんぴょんうさぎ」、折ったあとはお尻部分を弾いて実際にぴょんぴょんと遊べます。
似たようなもので「ぴょんぴょんカエル」というのもあります。
30工程以上の折りがありますので難易度的にはやや上級者向けになるでしょうか。
大きめの紙を用意してレクチャーしながらみんなで折るのも楽しそうですね。