ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽
組曲『展覧会の絵』、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』で有名なモデスト・ムソルグスキーの名曲を紹介します。
「展覧会の絵」はラヴェルではないの?
「禿山の一夜」なら聞いたことがあるけどという方も多いかもしれませんが、原曲はもちろんムソルグスキーで、アレンジで演奏されて有名になりました。
実際のムソルグスキーは以外にも管弦楽単体の曲は少なく、歌曲やピアノ曲を多く残しています。
本来のムソルグスキーの音楽をぜひ知って頂きたいと思い、今回はそのムソルグスキーの名曲を紹介していきます。
- 【ムソルグスキーのピアノ曲】組曲「展覧会の絵」の作者による珠玉の名作
- ドヴォルザークの名曲。人気のクラシック音楽
- リムスキー・コルサコフの名曲|色彩豊かなロシア音楽の世界
- クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演
- 【名曲ラプソディ】クラシック音楽史を彩る華やかな狂詩曲を厳選
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介
- ストラヴィンスキーの名曲。人気のクラシック音楽
- ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲
- アレクサンドル・ボロディンの名曲。人気のクラシック音楽
- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽
- Mily Balakirevの人気曲ランキング【2026】
ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽(1〜10)
瞑想曲-アルバムの綴り ニ短調(Medetation-Feuillet d’album d-moll)Modest Petrovich Mussorgsky

この1曲は、繊細な感情表現と深い内面の探求が特徴的です。
ニ短調の穏やかなメロディが、静かな瞑想的な雰囲気を醸し出し、聴く人の心に深く響きます。
ゆっくりとしたテンポで進行する音楽は、作曲家の心の動きを映し出すかのよう。
シンプルながら感情が豊かな表現が魅力で、ピアノの音色だけで様々な感情を喚起させます。
内省的な時間を過ごしたい方や、深い音楽表現を味わいたい方におすすめの一曲です。
1880年に作曲されたこの楽曲は、今なお多くの人々の心を捉えて離しません。
紡ぎ女(1871)Modest Petrovich Mussorgsky

ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキーによる静謐な名曲です。
紡ぎ女の労働を描いた曲で、軽快なリズムと繊細なメロディが特徴的です。
8分の9拍子を基調としつつ、8分の12拍子を織り交ぜることで、糸を紡ぐ動作の繰り返しと、その中に潜む感情の揺れを表現しています。
1872年にサンクト・ペテルブルクで発表され、当時の音楽シーンに一定の影響を与えました。
紡ぎ女の日々の営みや、その背後にある感情を巧みに描き出した本作は、ロシアの民俗音楽に興味がある方や、繊細な音楽表現を楽しみたい方におすすめです。
組曲「展覧会の絵」より、プロムナード1Modest Petrovich Mussorgsky
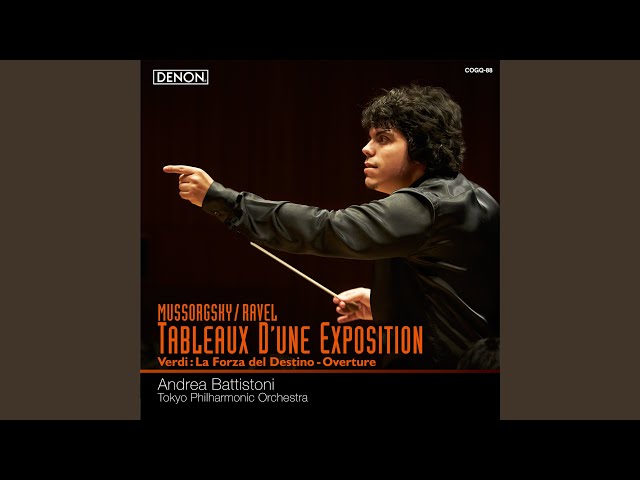
組曲「展覧会の絵」より、プロムナード(Promenade)。
「展覧会の絵」の中では「キエフの大門」とともに有名な曲です。
この曲はモデスト・ムソルグスキーが友人であったヴィクトル・ハルトマンの遺作展へ訪れた際の散歩の様子を作曲しました。
タイトルとなっているは10枚の絵ですが、プロムナードは第5まであり、合わせると16曲ほどになっています。
一番有名なのは組曲冒頭で演奏される第1プロムナードですが、比べて聞いていくと主題をさまざまな形で変奏されて雰囲気も変わっていく様子が味わい深く、また第4プロムナードでは短調になっており、親友であったハルトマンを悲しんでいる様子が音楽からも感じ取れます。
それぞれのプロムナードもぜひ聞いてほしいと思います。
ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽(11〜20)
組曲「展覧会の絵」より、鶏の足のうえの小屋 (バーバ・ヤガー)Modest Petrovich Mussorgsky
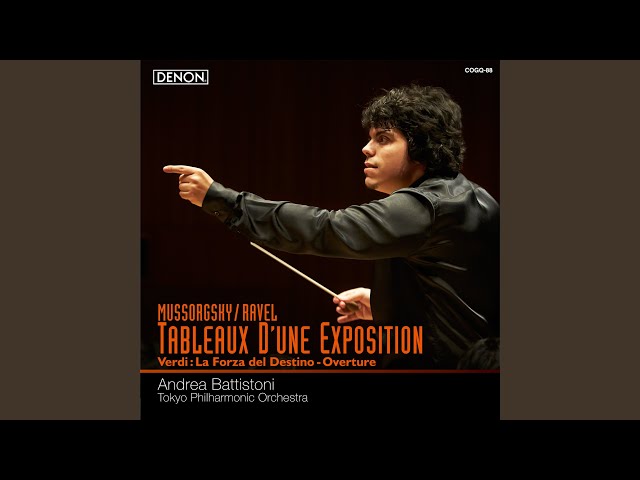
モデスト・ムソルグスキーによるロシア音楽の魂が響く名曲です。
恐ろしい魔女バーバ・ヤガーの小屋を鮮やかに描き出す、まさに音の絵画とも言えるでしょう。
激しいリズムと不安定な和音が、聴く者の心に不気味さと緊張感を巻き起こします。
1874年に友人の画家ヴィクトル・ハルトマンの遺作展をきっかけに生まれたこの曲は、ロシアの民間伝承を音楽で表現する革新的な試みでした。
音楽で物語を語る手法に触れられる素晴らしい1曲ですよ。
行進曲『カルスの奪還』Modest Petrovich Mussorgsky

モデスト・ムソルグスキーの代表作として知られる管弦楽曲です。
ロシア帝国の軍事的勝利を讃える華やかな行進曲で、力強いファンファーレから始まります。
中間部では東洋的な旋律が登場し、ロシアとトルコの対立を音楽で表現しています。
1878年10月に初演され、大成功を収めました。
ロシア民謡の要素を取り入れた荘厳な曲調は、聴く人の心に深い印象を残すでしょう。
クラシック音楽に興味のある方はもちろん、軍隊や歴史が好きな方にもおすすめの一曲です。
イエス・ナヴィヌス(ヨシュア)Modest Petrovich Mussorgsky

聖書の物語を題材にした合唱曲で、カナンの地を征服するヨシュアの勝利を描いています。
力強い合唱とピアノ伴奏が特徴的で、聖書の世界観を音楽で表現しています。
作曲は1874年から1877年にかけて行われ、モデスト・ムソルグスキーの宗教的な信念が反映されています。
神への信仰と戦いの勇気が込められた歌詞は、聴く人の心に響きます。
ロシアの伝統音楽の要素も取り入れられており、民族色豊かな曲調も魅力です。
宗教音楽や合唱曲に興味がある方、聖書の物語を音楽で体験したい方におすすめの一曲です。
古典様式による交響的間奏曲Modest Petrovich Mussorgsky

古典的な様式を取り入れながらも、独自の音楽表現を追求した一曲です。
オーケストラによる重厚な響きが特徴的で、古典的な形式の中にモデスト・ムソルグスキーらしい陰影のあるメロディが織り込まれています。
静かな導入から次第に高揚感を増していく展開は、聴く者の心を捉えて離しません。
1867年に完成されたこの作品は、ムソルグスキーの音楽的な探求心を示す重要な一曲といえるでしょう。
クラシック音楽に親しみたい方や、ロシア音楽に興味がある方におすすめです。
また、音楽の形式や構造に関心がある方にとっても、興味深い聴き所が多い作品となっています。


