ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽
組曲『展覧会の絵』、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』で有名なモデスト・ムソルグスキーの名曲を紹介します。
「展覧会の絵」はラヴェルではないの?
「禿山の一夜」なら聞いたことがあるけどという方も多いかもしれませんが、原曲はもちろんムソルグスキーで、アレンジで演奏されて有名になりました。
実際のムソルグスキーは以外にも管弦楽単体の曲は少なく、歌曲やピアノ曲を多く残しています。
本来のムソルグスキーの音楽をぜひ知って頂きたいと思い、今回はそのムソルグスキーの名曲を紹介していきます。
ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽(1〜10)
組曲「展覧会の絵」より、キエフの大門Modest Petrovich Mussorgsky

組曲『展覧会の絵』の中で、最も代表とする名曲です。
驚きの光景を通して日本の魅力を発見するテレビ朝日の番組『ナニコレ珍百景』で、驚きや衝撃の光景を紹介するBGMとして流れ、一部は聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。
キエフの大門とは黄金の門とも言われ、ウクライナの首都キーウの歴史的地区にある史跡、キエフ大公国時代のキエフの中央門のことです。
ピアノ版が原曲ですが、ラヴェル編曲によるオーケストラでの演奏版もよく知られており、大合奏によるロングトーンの迫力は圧巻です。
モデスト・ムソルグスキーは10枚の絵を見てインスピレーションを得て作曲したそうですが、実際の絵の場所を見に行くともしかしたら珍百景が見られるかもしれませんね。
組曲最後の曲なので、通して聞くと大感動するでしょう。
歌劇「ホヴァーンシチナ」より「シャクロヴィートゥイのアリア」Modest Petrovich Mussorgsky

歌劇『ホヴァーンシチナ』から、ロシアの運命を嘆くシャクロヴィートゥイのアリアをご紹介します。
この曲は、17世紀のロシアの動乱期を背景に、国の未来を憂う深い感情を表現しています。
低い声部と重いオーケストレーションが、絶望的な心情を見事に描き出しています。
ロシア音楽の魅力が詰まった本作は、歴史ドラマが好きな方や、オペラの壮大さを堪能したい方におすすめです。
1886年の初演以来、多くの聴衆の心を揺さぶり続けてきた珠玉の一曲です。
歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」より、ピーメンのアリアModest Petrovich Mussorgsky
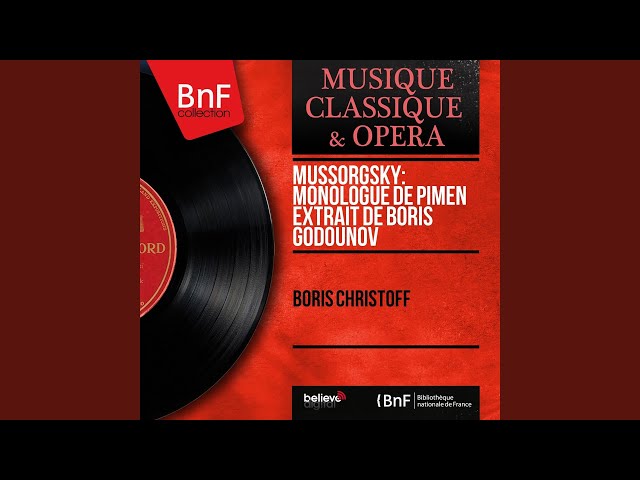
弦楽四重奏の中でも名曲として知られるこの楽曲は、オペラの一場面から生まれた名作です。
修道士ピーメンの深い洞察と宗教的な思索が、重厚な旋律とともに表現されています。
ゆったりとした進行の中に、ロシア正教の精神性が垣間見える素晴らしい曲調です。
1874年1月にサンクトペテルブルクで初演されたこの曲は、ロシアの民族音楽の影響を強く受けており、聴く者の心に深い印象を残します。
クラシック音楽に興味のある方はもちろん、人間の内面や歴史に関心のある方にもおすすめの一曲です。
スケルツォ 変ロ長調Modest Petrovich Mussorgsky

ロシアの誇るクラシック音楽の代表作です。
軽快で快活な雰囲気を持つこの短い楽曲は、初めのワルツのようなリズムが特徴的で、軽やかに進行します。
中盤には穏やかなトーンで進行するトリオのセクションがあり、前半のにぎやかなセクションとは対照的に、落ち着きと温かさを感じさせます。
全体として非常に軽快で、モデスト・ムソルグスキーの若き日の作品として注目に値します。
クラシック音楽に興味のある方や、ロシア音楽の魅力を知りたい方にぜひおすすめしたい1曲です。
1860年にサンクトペテルブルクで初演され、好評を博した本作は、ムソルグスキーの音楽的な成長を示す重要な作品として評価されています。
セレナヘリブの陥落(The Destruction of Sennacherib)(1866-67)Modest Petrovich Mussorgsky

アッシリアの軍勢が栄光の中で滅びる様を描いた名曲です。
戦争と神の力の対比を見事に表現し、軍事力への過信の無力さを訴えかけます。
力強い合唱とオーケストラの響きが、聴く者の心に深い感動を与えます。
1866年から1867年にかけて作曲されたこの楽曲は、ロシア音楽の革新性を示す珠玉の作品といえるでしょう。
クラシック音楽に興味のある方はもちろん、壮大な物語性を持つ音楽作品を楽しみたい方にもおすすめです。
本作を通じて、人間の力の限界と信仰の大切さを感じ取れます。
交響詩「禿山の一夜」Modest Petrovich Mussorgsky
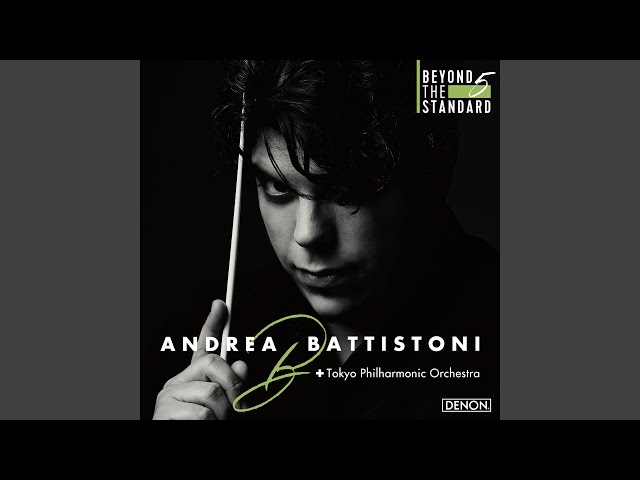
交響詩「禿山の一夜(A Night on the Bare Mountain)」。
聖ヨハネ祭前夜、禿山に魔物や精霊達が現れ大騒ぎするが、夜明けとともに消え去っていくという民話を元にしています。
原典版は『禿山の聖ヨハネ祭の夜』というタイトルで、紹介している動画のようによく知られる「禿山の一夜」という名称は、ロシア五人組として知られる作曲家リムスキー=コルサコフによる改訂版です。
近年では原典版も演奏されますが、作曲者本人であるモデスト・ムソルグスキー生前では演奏されることはなく、何度もお蔵入りされた曲でした。
リムスキー=コルサコフによっての本曲の復活とともにムソルグスキーの名声も上がるようになりました。
今ではオーケストラのコンサートや吹奏楽版のアレンジもあり、吹奏楽コンクールや定期演奏会でも演奏される名曲となっています。
涙 ト短調(Une larme g-moll)Modest Petrovich Mussorgsky

シンプルながらも情感が豊かなピアノソロ曲です。
わずか数分の長さながら、深い感情を表現し、聴く人の心に強く響きます。
ト短調の哀愁が漂う旋律と和音が特徴で、涙の一滴が持つ感情の重さと儚さを見事に描写しています。
曲中の和声の不安定さや短調の流れが、内面の葛藤を表現しているようです。
感情表現を重視する演奏者や、静かな中にも強い感動を求める方におすすめの一曲といえるでしょう。
1880年頃の作曲とされ、当時のロシア音楽の革新性を感じさせる珠玉の小品です。



