ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽
組曲『展覧会の絵』、『禿山の聖ヨハネ祭の夜』で有名なモデスト・ムソルグスキーの名曲を紹介します。
「展覧会の絵」はラヴェルではないの?
「禿山の一夜」なら聞いたことがあるけどという方も多いかもしれませんが、原曲はもちろんムソルグスキーで、アレンジで演奏されて有名になりました。
実際のムソルグスキーは以外にも管弦楽単体の曲は少なく、歌曲やピアノ曲を多く残しています。
本来のムソルグスキーの音楽をぜひ知って頂きたいと思い、今回はそのムソルグスキーの名曲を紹介していきます。
- 【ムソルグスキーのピアノ曲】組曲「展覧会の絵」の作者による珠玉の名作
- ドヴォルザークの名曲。人気のクラシック音楽
- リムスキー・コルサコフの名曲|色彩豊かなロシア音楽の世界
- クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演
- 【名曲ラプソディ】クラシック音楽史を彩る華やかな狂詩曲を厳選
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介
- ストラヴィンスキーの名曲。人気のクラシック音楽
- ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲
- アレクサンドル・ボロディンの名曲。人気のクラシック音楽
- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽
- Mily Balakirevの人気曲ランキング【2026】
ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽(11〜20)
村にて ニ長調(Au village D-Dur)Modest Petrovich Mussorgsky

ピアノソロの名曲が、明るく軽やかなメロディーと自然を描写するような音楽で魅了します。
作曲家の故郷への愛情が込められた作品で、聴く人に田舎のまったりとした雰囲気を感じさせます。
1880年頃に作られた本作は、民俗音楽の要素を取り入れたロシア音楽の特徴をよく表しています。
田園風景を音で表現した珠玉の一曲で、ロシアの自然や文化に興味がある方におすすめです。
クラシック音楽入門にも適していて、穏やかな気分になりたい時にぴったりの曲です。
歌劇「ソローチンツィの定期市」序曲Modest Petrovich Mussorgsky

ロシア民謡の影響を受けたモデスト・ムソルグスキーによる壮大な序曲です。
ウクライナの村祭りを舞台に、にぎやかな市場の様子や村人たちの生活を生き生きと描いています。
トランペットやティンパニが奏でる力強いリズムが印象的で、民俗音楽の要素を巧みに取り入れた独創的な音楽表現が特徴です。
1911年3月に初演された本作は、ロシア音楽の革新性を示す重要な作品として評価されています。
クラシック音楽に興味のある方や、ロシアの民族音楽を感じたい方におすすめの一曲です。
組曲「展覧会の絵」より、 カタコンブ (ローマ時代の墓)Modest Petrovich Mussorgsky

ロシアの民族性と墓地の暗い雰囲気を見事に描き出した名曲です。
響き渡るピアノの音色が、カタコンベの神秘的な空間を表現しています。
静寂と重苦しさの中にも、希望の兆しが垣間見える、深い哲学性を感じさせる曲想が魅力です。
1874年に作曲されたこの曲は、友人の画家ハルトマンの絵画からインスピレーションを得たとされています。
ピアノの技巧を駆使した表現力が豊かな演奏で、聴く人の想像力をかき立てます。
クラシック音楽の奥深さを味わいたい方や、音楽で描かれる情景に浸りたい方におすすめの一曲です。
組曲「展覧会の絵」より、ビドロModest Petrovich Mussorgsky

組曲「展覧会の絵」より、ビドロ(牛車)。
ビドロ(Bydlo)は、ポーランド語で「牛車」という意味がありますが、その他に「(牛のように)虐げられた人」の意味があります。
作曲された際にタイトルを決めた後にナイフで削った跡があり、モチーフとなっているハルトマンの遺作展を開いたロシアの芸術評論家ウラディーミル・スターソフがモデスト・ムソルグスキーへ尋ねた際、「われわれの間では『牛車』ということにしておこう。」と答えたそうです。
実際にハルトマンの絵には「ポーランドの反乱」と題された作品があり、この絵があることにより2つの意味があるものだと推測されました。
有名なラヴェル編曲版ではピアニッシモで始まりますが、原曲では力強く、かつ重い演奏で始まることが多くイメージの違いを感じ取れます。
ラヴェル版ではテューバのソロがあるのですが、テューバにしてはとても高い音域でソロを吹くので必聴です。
組曲「展覧会の絵」より、小人Modest Petrovich Mussorgsky

組曲「展覧会の絵」より、小人(グノーム)です。
組曲としての「展覧会の絵」では2曲目なのですが、絵のタイトルでは1曲目です。
曲名のグノーム(Gnomus)は、大地を司る精霊・妖精のことで、主に地中で生活し、老人のような容貌をした小人だそうです。
小人というとかわいらしいイメージがあると思いますが、この小人は地中にいるという設定なのか曲想は非常に重い曲になっています。
画像を検索すると実際に飾られた絵が見られますが、恐らく想像とは違う小人だと思うことでしょう。
一度実際の絵を検索してみてください。
音楽の曲想に納得がいきますよ。
組曲「展覧会の絵」より、死せる言葉による死者への話しかけModest Petrovich Mussorgsky

神秘的な雰囲気が漂う曲です。
静謐な旋律が、生者と死者の対話を想起させます。
モデスト・ムソルグスキーが友人の死をきっかけに作曲した本作は、深い感情が込められています。
1874年に発表されたピアノ組曲『展覧会の絵』の一部で、後にモーリス・ラヴェルによって管弦楽に編曲されました。
死者への呼びかけを表現した曲想は、聴く人の心に強く響きます。
静かな中にも力強さを感じさせる本作は、人生や死について深く考えたい方におすすめです。
クラシック音楽の奥深さを味わえる一曲となっています。
ムソルグスキーの名曲。人気のクラシック音楽(21〜30)
禿山の一夜Modest Mussorgsky
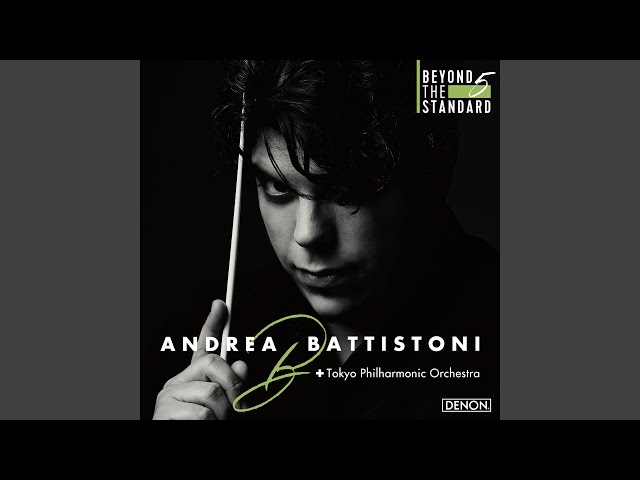
冒頭の何かに追われているようなスリリングな旋律から、魔物たちが狂乱するクライマックスへと突き進むドラマチックな楽曲展開は、楽しいだけではなくちょっと怖いハロウィンを演出したいときにぴったりですね!
ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキーによる本作は、魔女たちが集う真夜中の宴を描いた作品です。
ディズニーの名作映画『ファンタジア』でも使われており、その強烈なインパクトを記憶されている方も多いでしょう。
友人のリムスキー=コルサコフさんによる編曲版が1886年10月に初演されて以来、広く親しまれています。
最後は鐘の音とともに静かな朝を迎える構成も秀逸で、ハロウィンナイトの終わりを告げるBGMとしてもオススメです。


