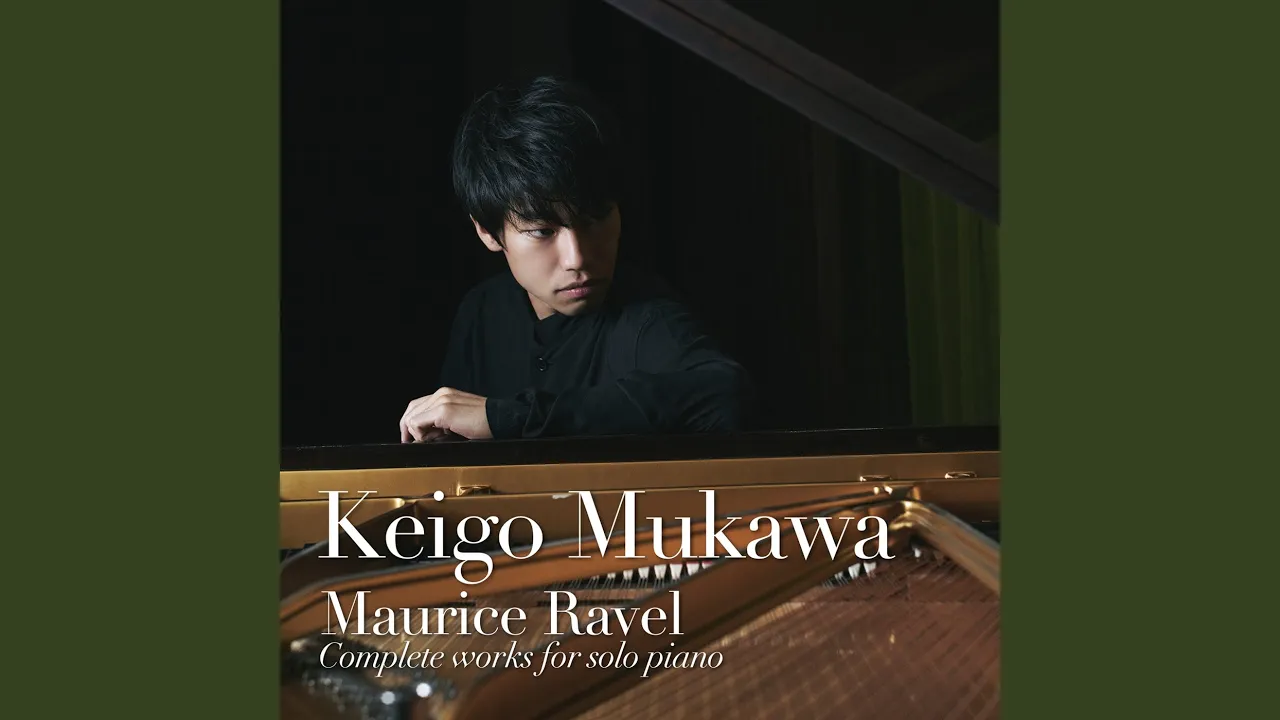【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介
印象派音楽の重要な人物の一人、モーリス・ラヴェル。
彼の作品は細部まで緻密に作られており、土台に古典的な形式をしっかり取り入れていますが、印象派らしい表現も混じり合っていることから、彼にしかない唯一無二の音楽を感じられます。
他の作曲家のオーケストラ編曲も行っており、その卓越されたオーケストレーションから「オーケストレーションの天才」「管弦楽の魔術師」とも呼ばれていました。
本記事では、そんなラヴェルの名曲、代表曲をご紹介します。
クラシックに馴染みのない方でも、どこかで一度は聞いたことがあるであろう曲も存在するので、ラヴェルの素晴らしい名曲の数々をお楽しみください!
【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介(1〜10)
ソナチネ, M. 40: II. Mouvement de MenuetNEW!Maurice Ravel

「オーケストレーションの天才」と称されるフランスの作曲家、モーリス・ラヴェルさん。
彼が手がけた名作『ソナチネ』の第2楽章は、作業中の集中力を高めてくれる1曲としてオススメです。
1903年の雑誌企画をきっかけに作曲が始まり、全曲が初演されたのは1906年3月のこと。
古典的なメヌエットの形式をとりながらも、彼特有の洗練されたハーモニーが光ります。
派手な展開よりも静かな美しさが際立つ本作は、勉強や読書のBGMとしても最適ですね。
控えめながらも芯のあるピアノの音色に、ぜひ耳を傾けてみてください。
ソナチネMaurice Ravel

1903年から1905年にかけて作曲されたピアノ独奏曲。
全3楽章から成る本作は、作曲コンクールのために書かれた小品ながら、魅力的な旋律と繊細な響きが凝縮されています。
第1楽章は叙情的なメロディが印象的。
第2楽章は優美で可憐な旋律が特徴的で、ラヴェル自身が「踊りのあとのお辞儀」と表現した部分もあります。
第3楽章は快活なパッセージが活躍。
古典的形式にのっとりながらも、ラヴェル特有の繊細な表現が光る名曲です。
ピアノ協奏曲ト長調Maurice Ravel

1931年に完成されたこちらの作品は、彼の晩年の傑作として知られています。
アメリカ演奏旅行でジャズに触れた経験や、母の出身地であるバスク地方の民謡の影響が色濃く反映された本作。
3楽章構成で、第1楽章は明るく楽しげな雰囲気、第2楽章は叙情的なサラバンド風、第3楽章はサーカスやパレードを思わせる活力に満ちた展開と、変化に富んだ魅力的な曲調が特徴です。
ラヴェルの音楽的ルーツへの回帰を感じさせつつ、彼独自の世界観が広がっています。
ラヴェルが手掛けたピアノ協奏曲は二つだけ。
そのなかの一つであるこの作品を、ぜひ聴いてみてください。
ラ・ヴァルスMaurice Ravel

1919〜1920年に作曲されたバレエ曲。
曲名はフランス語で「ワルツ」のこと。
ウィンナ・ワルツを思い起こさせるフレーズが登場します。
ラヴェルがパリで成功を博していたディアギレフに作品を聴いてもらったところ、ディアギレフは「傑作ではあるがバレエには不向き。
バレエの絵に過ぎない」として、作品を受け取らなかったそう。
どこか不吉な雰囲気があり、最後は爆発的に幕を閉じます。
亡き王女のためのパヴァーヌMaurice Ravel

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルによる優美な名曲。
1899年にピアノ曲として誕生し、後に管弦楽版も作られた本作は、静かな美しさで聴く人の心を捉えます。
テレビCMや映画の挿入歌としても使用され、現在でも幅広い層に愛されていますね。
約7分の演奏時間に込められた繊細な旋律は、古い宮廷舞踏を思わせる優雅さを醸し出しています。
ラヴェルならではの洗練された音色と抑制の効いた表現が魅力的で、初めて聴く人でも心地よく世界観に浸れる1曲。
クラシック音楽に親しみたい方や、優美な音楽を求める方にオススメです。
水の戯れMaurice Ravel

水の動きを音楽で表現した、フランスの作曲家モーリス・ラヴェルのピアノ曲。
1901年、パリ音楽院在学中に作曲されたこの作品は、水滴が水面に落ちる様子や、水が流れる姿をピアノの音色で見事に描き出しています。
軽やかなアルペジオの連続で、水の様々な表情が浮かび上がる幻想的な世界観が魅力です。
当初は不協和音の多さを批判されましたが、現在では多くのピアノファンを魅了する名曲として親しまれています。
マ・メール・ロワMaurice Ravel

ラヴェルが1908年に作曲した組曲。
童話をモチーフにした5つの楽章から成り、子どもたちのための音楽として生み出されました。
優美で幻想的な響きが特徴的で、ラヴェルの繊細な音楽性が存分に発揮されています。
ピアノ四手連弾で発表された後、1911年に管弦楽版に編曲され、より色彩豊かな表現が加わりました。
各楽章では、眠れる森の美女やパゴダの女王など、さまざまな物語の情景が音楽で巧みに描かれています。
おとぎ話の世界に誘われるような魅力的な作品を親しみたい方にオススメです。