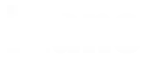【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
「この曲を聴くと癒やされる」「いつかこの曲を弾いてみたい」そんな印象的なピアノ曲はありますか?
お気に入りの曲は、ストレスや不安でモヤモヤした心を落ち着かせてくれます。
本記事では、そんな癒やしの1曲の候補となり得るクラシックの名曲の中から、世界的に有名なピアノ作品を厳選してご紹介します。
クラシックにあまりなじみがないという方でも、必ずどこかで耳にしたことがあるであろう有名な作品ばかりをセレクトしていますので、ぜひ最後までお楽しみください!
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【クラシック】有名ピアノ作品|一生に一度は弾きたい珠玉の名曲たち
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- ピアノ初心者必見!一度は弾いておきたい定番クラシック作品を厳選
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち(21〜30)
夜のガスパール, M. 55: II. 絞首台Maurice Ravel

モーリス・ラヴェルが1908年に作曲したピアノ組曲『Gaspard de la nuit』の一曲で、ルイ・ベルトランの詩が描く荒涼とした情景を音で表現しています。
この楽曲の大きな特徴は、遠くで鳴り響く鐘の音を表す同じ音が、冒頭から最後まで150回以上も執拗に反復される点です。
この単調な響きに不気味な和音が重なり、聴く人を死の静寂が支配する瞑想的な世界へと誘います。
演奏する側は、この厳格なテンポと響きのバランスを保たないと、作品の持つ壮絶な陰鬱さを損ないかねない難曲です。
本作はコンクールでも頻繁に取り上げられます。
悲しみの底にある静かな美しさに触れたい時に聴いてみてはいかがでしょうか。
「四季」-12の性格的描写 Op.37bis 6月「舟歌」Pyotr Tchaikovsky

ロシアの作曲家によるピアノ独奏曲集『The Seasons』の中でも、叙情美をたたえて人気の高い一曲です。
本作は1876年6月に雑誌で公開されたもので、寄せては返す波のような物悲しい旋律で始まります。
水辺の情景を描いた詩が添えられているとされ、その切ない調べは聴く人の心に深く染み渡ります。
中間部で一転して長調になると、星のきらめきを思わせる華やかなアルペジオが展開されます。
あまりにも人気が高いため、1981年に振付されたバレエ『Piano Pieces』にも用いられました。
悲しみに沈む心に優しく寄り添う、言葉にならない感情が込み上げてくる名曲です。
【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち(31〜40)
森にてAlbert Ketèlbey

暑い夏の午後に、まるで木陰で涼んでいるかのような心地よさを運んでくれる、アルバート・ケテルビーのピアノ独奏曲はいかがでしょうか。
この楽曲を聴いていると、森の奥深く、木々の間から射し込む柔らかな光や、そよ風に葉が揺れる音までもが聞こえてくるような、そんな情景が目に浮かびます。
優しく親しみやすい旋律は、とても穏やかな時間の流れを感じさせてくれることでしょう。
本作は、1920年代に形になったと考えられているピアノ曲です。
アルバム『A Dream Picture』には1993年に録音されたローズマリー・タックの演奏が収められています。
日常の喧騒から離れてほっと一息つきたい時や、優しいピアノの音色に包まれて心静かに過ごしたい方に、ぜひ聴いていただきたい一曲です。
夢Claude Debussy

1890年にフランスの作曲家クロード・ドビュッシーが作曲したこの楽曲の魅力は、穏やかで幻想的な響きにあります。
A-B-A三部形式で構成され、分散和音による美しい伴奏の上に歌うような旋律が流れていきます。
中間部ではコラール風の和声が現れ、ドラマチックな表情を見せた後、再び静寂へと戻る構成です。
本作は調性が曖昧で、フェードアウトするような柔らかな終結が夢見心地の余韻を残します。
暑い夏の日に心の安らぎを求める方や、印象派音楽の色彩が豊かな響きを楽しみたい方におすすめです。
約4分という演奏時間で気軽に聴けるため、リラックスしたいひと時にぴったりの作品といえるでしょう。
小組曲:第1曲「小舟にて」Claude Debussy

暑い夏、心に一服の清涼剤となるような、クロード・ドビュッシーのピアノ連弾作品をご紹介しますね。
1889年2月にドビュッシーと出版社代表によって初めて二人で演奏されたこの作品は、4つの小品から成る組曲の冒頭を飾ります。
まるで水面をゆるやかに進む小舟を思わせる、穏やかで美しい旋律がとっても魅力的です。
歌詞こそありませんが、ベルレーヌの詩にインスピレーションを得ているそうで、月光の下で揺蕩う舟の情景や、遠い時代の優雅な雰囲気が心に広がるようです。
揺らめくピアノの音色が、聴く人を心地よい涼しさで包み込んでくれますね!
本作は管弦楽編曲版も広く知られ、一層豊かな色彩を感じられますし、館内BGMなどで耳にすることもあるかもしれません。
暑さで少しお疲れの時や、静かに心を落ち着けたい時にぜひ聴いてみてください。
ドビュッシーが「重すぎず短すぎない」サロン向けに考えたと言うように、気軽に優雅な気分に浸れることでしょう!
4分33秒John Cage

「4分33秒」は、アメリカの作曲家ジョン・ケージが作曲し、1952年に初演された「3楽章」から成る楽曲です。
この曲は、「4分33秒」の全楽章すべてが「休止」となっています。
この曲は、単に悪ふざけで作った曲ではなく、作曲者の創造が吹きこまれた楽曲であり、世界的にも高い評価を受けています。
「フレースエーの花々」第3巻 Op.16:第2曲 夏の隠れ家に入居してWilhelm Peterson-Berger

ここで、暑い夏にぴったりの、涼やかなピアノ曲をご紹介しますね。
スウェーデンの作曲家ウィルヘルム・ペテルソン=ベルゲルによる、ピアノ小品集『Frösöblomster』の第3巻に収められた、とっておきの一曲なんですよ。
1914年に完成したこの楽曲は、まるで夏の静かな隠れ家へそっと足を踏み入れたような、穏やかで美しい旋律が心に響きます。
聴いていると、きらめく木漏れ日の中で、心地よいそよ風に吹かれているような気分になれるんです。
作曲者が愛したフレソー島の夏の情景が目に浮かぶようで、日常を忘れさせてくれますね。
派手さはないけれど、じんわりと心に染み入るような、そんな魅力にあふれています。
日々の喧騒から離れて、静かに音楽の世界に浸りたい方には、本当におすすめです。
心を落ち着かせたい時や、ゆったりとした午後のひとときに本作を聴けば、きっと優しい気持ちになれることでしょう。
読書のお供にも、もってこいかもしれませんね!