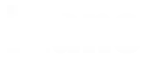【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
「この曲を聴くと癒やされる」「いつかこの曲を弾いてみたい」そんな印象的なピアノ曲はありますか?
お気に入りの曲は、ストレスや不安でモヤモヤした心を落ち着かせてくれます。
本記事では、そんな癒やしの1曲の候補となり得るクラシックの名曲の中から、世界的に有名なピアノ作品を厳選してご紹介します。
クラシックにあまりなじみがないという方でも、必ずどこかで耳にしたことがあるであろう有名な作品ばかりをセレクトしていますので、ぜひ最後までお楽しみください!
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【クラシック】有名ピアノ作品|一生に一度は弾きたい珠玉の名曲たち
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- ピアノ初心者必見!一度は弾いておきたい定番クラシック作品を厳選
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち(41〜50)
サマータイムGeorge Gershwin

夏の気だるい午後にぴったりの、心が安らぐ子守歌はいかがでしょうか。
ジョージ・ガーシュウィンが手掛けたオペラ『ポーギーとベス』からの一曲で、1935年に初めて世に出た作品です。
この楽曲は、ジャズの自由な雰囲気とクラシック音楽の持つ美しさが溶け合い、聴く人の心を優しく包み込みます。
シンプルな旋律ながら、その奥には深い情感が揺蕩うのを感じられるでしょう。
歌詞には、我が子をあやす母の愛情と未来への静かな希望が描かれ、アフリカ系アメリカ人のスピリチュアルな世界観が息づいています。
1959年の映画版『ポーギーとベス』でも効果的に使用されたことでも知られています。
暑さで疲れた心にそっと寄り添い、穏やかな時間を与えてくれる本作は、ゆったりと音楽を楽しみたい方におすすめですよ。
夏の朝Heino Kasuki

夏の早朝、きらめく光の中で深呼吸したくなるような、そんな清涼感があふれる調べが魅力のピアノ曲はいかがでしょうか。
ヘイノ・カスキが作曲し、作品番号Op.35-1「夏の朝」として知られるこの楽曲は、1920年代初頭に書かれたとされています。
北欧の澄み切った空気を感じさせる透明感と、穏やかながらも心に深く染み渡る叙情性が持ち味ですね。
繊細なトリルが木漏れ日のようにきらめき、聴く人を心地よい気分へと誘います。
ヘイノ・カスキが紡いだ、心惹かれる一曲ではないでしょうか。
暑い季節に涼やかなひとときを過ごしたい方や、心静かに美しい旋律に浸りたい方にとてもおすすめです。
本作を聴けば、日常の忙しさを忘れさせてくれることでしょう。
ピアニスト舘野泉さんのアルバム『Piano Works』でもその魅力に触れることができますよ。
夜の海辺にてHeino Kasuki

ひんやりとしたピアノの音色で、夏の暑さを忘れてみませんか。
フィンランドの作曲家ヘイノ・カスキが手掛けた美しい小品です。
ピアノの一音一音がまるで夜の海辺にきらめく光の粒のように感じられ、北欧の静謐な自然へと心を誘うことでしょう。
穏やかで幻想的な旋律は、聴く人を優しく包み込むようで、内省的な気分にさせてくれます。
ピアニストの舘野泉が演奏し、1999年4月に録音されたアルバム『Kaski: Night By the Sea』に収録されたことで、この楽曲の魅力は広く知られるようになりました。
暑さでお疲れ気味の心にそっと寄り添い、涼やかな気分に浸りたい方に、ぜひおすすめしたい作品です。
組曲「鏡」より「洋上の小舟」Maurice Ravel

暑い日に聴きたくなる、モーリス・ラヴェルの涼やかな一曲はいかがでしょうか。
1906年にパリで出版されたピアノ組曲『Miroirs』の第3曲で、画家ポール・ソルドへ献呈された作品です。
広い海原を小舟がゆったり漂う情景が目に浮かび、聴くだけで心が洗われる気分になりますね。
本作の魅力は、きらめくアルペジオによる水の表現。
光を受けて揺れる水面や深い海の静けさを感じさせ、ピアノ一台とは思えないほど表情が豊かです。
140小節で36回も拍子が変わるのも、絶え間ない波の動きを巧みに捉えているからでしょう。
美しい音色で涼みたい方、印象派音楽がお好きな方に、きっと気に入っていただけるはず。
組曲『Miroirs』の他の曲とあわせて楽しむのも良いかもしれませんね。
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773J.S.Bach

『インヴェンション』の第2番として知られるこのハ短調の作品は、バロック時代の対位法技術が凝縮された魅力的な1曲です。
1723年にまとめられた教育的作品集の一部で、右手と左手が2小節ずれてカノン形式で対話する構造となっています。
短い作品ながら声部の入れ替わりや転調も含まれ、演奏者には各声部の独立性とバランスが求められます。
ハ短調という調性が生み出す内省的で厳格な雰囲気も印象的で、単なる練習曲を超えた芸術性を持っています。
対位法の美しさを学びたい方や、バロック音楽の奥深さに触れたい方におすすめです。
技術的な挑戦と音楽的表現力を同時に養える、学習者にとって貴重なレパートリーとなるでしょう。
フランス組曲 第1番 BWV 812 サラバンドJ.S.Bach

バロック音楽に憧れはあるものの、複雑な対位法が苦手という方にはこの楽曲がおすすめです。
1722年頃に作曲されたこの作品は、アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳に収められていることからも、家庭での演奏を意図した親しみやすい楽曲となっています。
3拍子のゆっくりとした舞曲で、シンプルな和声進行と美しい装飾音が特徴的です。
曲調もゆっくりですし、難しいフレーズも技巧的なところもないため、バロック音楽を弾き始めた方でも練習すればすぐに演奏できます。
音色や表現、強弱などが重視されるので、良い音色の探求をしながら弾きましょう。
フランス組曲 第1番 BWV 812 メヌエットⅠJ.S.Bach

バロック時代の舞曲形式の中でも、この優雅な3拍子の楽曲は1722年から1725年頃に作曲され、「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳」にも収録されています。
シンプルで親しみやすい旋律でありながら、対位法的な要素も含まれており、教会で響く上品な音色をイメージしながら演奏すると雰囲気が出てきます。
本作は技術的な難易度が比較的低いため、ピアノを始めて間もない方やバロック音楽に憧れを持つ方におすすめです。
音色や表現、強弱などが重視されるクラシックの場合は、ロングトーンの練習や良い音色の探求をしながら弾いてみましょう。