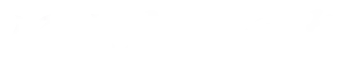実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌
童謡といえば、保育園や幼稚園で子供たちが歌うかわいらしい歌というイメージが強いですよね。
しかし、なかには歌詞をすべて聴くと背筋が凍りついてしまうような恐ろしい曲があるのをご存じでしたか?
この記事では、実は歌詞を深掘りすると怖い童謡を集めてみました。
ただ怖いだけではなく、興味深い曲の背景も知れるので「そういえば歌詞の意味がわからない」「子供の頃から気になっていた」そんな童謡がある方はぜひ一度チェックしてみてくださいね!
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
- ゾゾっと背筋が凍る怖い曲。狂気やホラー性を感じる邦楽
- お月さまを歌った童謡・わらべうた
- 恐ろしい音楽のススメ~実は怖いあの曲
- 【ダークサイド】怖い歌詞の曲。ゾクッとするフレーズに震える曲
- 【びっくり!】海外発祥の童謡。なじみ深いあの童謡も実は
- 【ひな祭りの歌】桃の節句の定番曲。実は知らない!雛祭りソング
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 【ヘビの歌】童謡・わらべうた・手遊びうた
- 世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌
- 雨の日に歌いたい・雨をテーマにした童謡
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- アンパンマンの歌。主題歌・挿入歌・キャラクターの曲一覧
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(1〜10)
ねこふんじゃった作曲者不詳

世界中で親しまれている軽快なピアノ曲に、作詞家の阪田寛夫さんが歌詞を手掛けた本作。
猫を踏んでしまった主人公が猫をしかりつけ、最後には空の彼方へ飛んでいってしまうという、少し不思議な物語が展開します。
ブラックユーモアを感じさせる結末ですが、物語として楽しくおぼえられるのもこの曲の良いところ。
ただ、もしも動物虐待が大きな問題となっている現代に生まれていたとしたら……いくら可愛らしいメロディでも、社会が受け入れなかったかもしれませんね。
うさぎとかめ作詞:石原和三郎/作曲:納所弁次郎

はじめから終わりまでしっかりとしたストーリーになっている『うさぎとかめ』。
作詞を石原和三郎さん、作曲を納所弁次郎さんが手がけたこの歌は、誰もが知る教訓物語ですね。
でも歌詞をよく聴くと、うさぎが急にかめを見下したり、勝ったカメが最後にチクリと皮肉を言ったりと、登場人物たちのちょっぴり黒い一面にも気づきます。
単純な教訓だけでなく、言葉の裏にある本当の意味を想像できるのもこの曲おもしろいところ。
「どうしてこんなことを言ったのかな?」と物語の背景を話し合いながらイメージをふくらませていくと、また違った楽しみ方ができるかもしれませんね。
おちゃらかほいわらべ歌

シンプルな歌詞と軽快なリズムが特徴の、日本の伝統的な手遊び歌。
向かい合って手をつなぎ、歌いながらじゃんけんを楽しんだことのある方も多いのではないでしょうか?
実はこの『おちゃらかほい』、一説では、家が貧しく、お金を稼ぐために身売りせざるを得なかった遊女たちの姿を描いているともいわれています。
無邪気な子供の歌かと思いきや、そこには悲しい物語が……。
しかし、リズム感や協調性を育むのにピッタリなので、子供たちと手遊びする際は、深い意味については触れずに楽しみましょう。
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(11〜20)
おつきさんいくつわらべうた

月とののどかな問いかけで幕を開ける、一見かわいらしいわらべうた。
でも物語を最後まで聴くと、その残酷な結末に思わずゾッとしてしまいます。
お使いに出た女性の失敗談かと思いきや、最終的に油を舐めた犬が太鼓の皮にされてしまうという、なんとも恐ろしい展開。
この歌の無邪気な調子と歌詞のギャップが、不気味さをかもしだしているのかもしれません。
背景を知った今、改めて聞いてみてください。
「なぜ?」「どうしてそんな……」といろいろな想像が浮かぶはずです。
線路は続くよどこまでもアメリカ民謡

19世紀後半にアメリカで生まれた民謡『線路は続くよどこまでも』。
日本では、NHK『みんなのうた』で流れていたのを記憶している方もいらっしゃるはず。
野山を越えてどこまでも旅をする、希望に満ちた歌という印象が強いですよね。
しかし、原曲は過酷な鉄道工事にたずさわる人々の労働歌だったのだそうです。
働き詰めで力尽きる様子や、恋人の不貞を暗示するような衝撃的な歌詞も存在したといいます。
この事実を知ってしまうと、陽気なメロディが、かえって不気味な響きを帯びて聴こえてくるから不思議です。
桃太郎作詞:不詳/作曲:岡野貞一

日本中で歌い継がれてきたといっても過言ではない、おなじみの童謡『桃太郎』。
誰もが桃太郎の活躍に胸をおどらせた記憶があるのではないでしょうか?
ところが、歌詞を全編通して聴いてみると、その印象がガラリと変わってしまうから驚きです。
「残らず鬼を攻めふせて」「ぶんどりものをエンヤラヤ」と歌う内容は、正義のヒーローの活躍にもとれますが、少し過激な侵略者のようにも聞こえてしまいます。
このドキッとするような展開の裏には、実は深い歴史的背景があるのだそう。
物語の別の側面を探るきっかけとして、親子で話し合ってみるのもよいかもしれませんね。
山寺の和尚さん作詞:久保田宵二/作曲:服部良一

まりのかわりに猫を袋に入れてしまう、思わず耳を疑うような歌詞にドキッとした方も多いでしょう。
軽快でコミカルなメロディと、その裏にひそむ少し怖い内容のギャップが、本作の不思議な魅力を形作っています。
この楽曲は作詞家の久保田宵二さんと作曲家の服部良一さんによって、昭和12年に大人向けのコミックソングとして作られたもの。
もとは江戸の俗謡で、当時の世相を映す風刺やユーモアが込められていたそうです。
ただ怖いだけでなく、歌が生まれた背景を知ることで、昔の人々の遊び心を感じられるかもしれません。
どうしてこんな歌詞なのか、友達と想像しながら聴いてみるのもおもしろいいですよ。