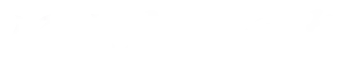実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌
童謡といえば、保育園や幼稚園で子供たちが歌うかわいらしい歌というイメージが強いですよね。
しかし、なかには歌詞をすべて聴くと背筋が凍りついてしまうような恐ろしい曲があるのをご存じでしたか?
この記事では、実は歌詞を深掘りすると怖い童謡を集めてみました。
ただ怖いだけではなく、興味深い曲の背景も知れるので「そういえば歌詞の意味がわからない」「子供の頃から気になっていた」そんな童謡がある方はぜひ一度チェックしてみてくださいね!
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
- ゾゾっと背筋が凍る怖い曲。狂気やホラー性を感じる邦楽
- お月さまを歌った童謡・わらべうた
- 恐ろしい音楽のススメ~実は怖いあの曲
- 【ダークサイド】怖い歌詞の曲。ゾクッとするフレーズに震える曲
- 【びっくり!】海外発祥の童謡。なじみ深いあの童謡も実は
- 【ひな祭りの歌】桃の節句の定番曲。実は知らない!雛祭りソング
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 【ヘビの歌】童謡・わらべうた・手遊びうた
- 世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌
- 雨の日に歌いたい・雨をテーマにした童謡
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- アンパンマンの歌。主題歌・挿入歌・キャラクターの曲一覧
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(11〜20)
雨降りお月作詞:野口雨情/作曲:中山晋平

雨の夜、花嫁がひとり嫁いでいく様子を描いた『雨降りお月』は、どこかもの悲しい雰囲気が印象的な童謡です。
歌詞をよく読むと、なぜか一人で嫁いでいく花嫁の姿に、少し不思議な気持ちになりますね。
その背景には、亡き娘を思う鎮魂歌という切ない説があるといわれています。
ですが、作者が雨の中を嫁いできた妻をモデルにしたという、心温まるエピソードも残されているのだとか。
いろいろな可能性を想像しつつ、歌詞の世界観に思いをはせながら聴いてみてくださいね。
りんごのひとりごと作詞:武内俊子/作曲:河村光陽

愛らしいリンゴの独白が描かれた『りんごのひとりごと』。
軽快なメロディで親しまれていますが、歌詞にはどこかもの悲しさがただよいます。
北国から汽車で運ばれ、故郷のおじいさんを思う姿が、実は都会へ出稼ぎに来た娘の境遇と重なるという解釈もあるようです。
この歌が作詞家の武内俊子さんの闘病中に生まれたと知ると、歌詞に込められた郷愁が一層胸にせまるかもしれません。
背景を知ってから聴き直すと、いつもの童謡がまったく違う物語に見えてくるはず!
ぜひそのギャップを味わってみてくださいね。
きゃーろのめだまわらべうた

一度聴いたら忘れられない、少し不思議な歌詞が印象的なわらべうた『きゃーろのめだま』。
子供のいたずら心や好奇心が歌われており、わらべうたとして各地で歌われていますが、内容は「かえるの目玉にお灸をすえる」というなんとも残酷なもの。
もはやいたずらのレベルではなく、よくよく意味を考えると非常に恐ろしい歌であることがわかります。
しかし、手遊びにもピッタリの陽気なリズムで、子供たちにとっても親しみやすい作品であるのは確か。
「昔の子供たちの無邪気な一面」として受け止めつつ、目の前の子供たちには命の大切さを伝えていきたいですね。
あぶくたったわらべうた

お鍋を囲んで輪になって歌う、わらべうた『あぶくたった』。
グツグツ煮えたお鍋の中身を「むしゃむしゃ」と食べるまねをするのが、この歌の楽しいところですね!
でも、戸棚に鍵をかけて寝静まると聴こえてくる「トントン」という不気味な音……。
その正体は「お化けの音!」という掛け声で、ここから一気に鬼ごっこがスタートします。
人食いの儀式というゾッとする説もありますが、このスリルこそが遊びの醍醐味。
物語の登場人物になった気分で、ドキドキの追いかけっこを思いきり楽しみましょう。
こぎつねドイツ民謡

ドイツ民謡を原曲とし、日本では秋の唱歌として親しまれている『こぎつね』。
誰もが一度は歌ったことがあるといっても過言ではない、おなじみの1曲ですね。
この曲のおもしろいところは、日本語詞と原曲のドイツ語詞で描かれる世界が全く違う点にあります。
愛らしいこぎつねがお化粧をする日本語詞に対し、原曲は盗みをいましめる教訓的な物語。
その背景を知ってから聴き直すと、どこか哀愁を帯びたメロディがより深く心に響くのではないでしょうか?
国や文化による歌詞の違いを親子で話し合ってみるのも、この曲の奥深い楽しみ方としてオススメですよ!
靴が鳴る作詞:清水かつら/作曲:弘田龍太郎

子供たちが元気に歩く微笑ましい光景が目に浮かぶ『靴が鳴る』。
作詞家の清水かつらさんと作曲家の弘田龍太郎さんが手掛けたこの曲は、誰もが知る名曲ですよね。
しかし、この軽快な靴音に「戦地へ向かう兵隊の行進」を重ねたり、無邪気な子供たちがどこかへ連れ去られてしまうのでは、という少しぞっとする解釈もあるのだそう。
明るく楽しげなメロディだからこそ、その裏に隠された意味を想像すると、いつもの歌が少し違って聴こえてくるから不思議です。
普段とは違う視点で聴いてみるのも、この曲の新たな楽しみ方かもしれませんよ!
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(21〜30)
あめふり作詞:北原白秋/作曲:中山晋平

詩人・北原白秋さんによる作詞と、数多くの流行歌を制作した作曲家・中山晋平さんの作曲により生まれた童謡。
日本の歌百選にも選ばれた楽曲で、歌詞どおりの無邪気さがイメージできる軽快なメロディーを覚えているという方も多いのではないでしょうか。
実は病気の母を待つ子供の姿を描いているという都市伝説が存在し、5番まである歌詞の3番意向を口にすると呪われると言われています。
学校でもすべての歌詞を歌うことが禁止されているという逸話まである、明るいイメージからは想像もできないうわさを持つ童謡です。