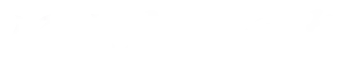実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌
童謡といえば、保育園や幼稚園で子供たちが歌うかわいらしい歌というイメージが強いですよね。
しかし、なかには歌詞をすべて聴くと背筋が凍りついてしまうような恐ろしい曲があるのをご存じでしたか?
この記事では、実は歌詞を深掘りすると怖い童謡を集めてみました。
ただ怖いだけではなく、興味深い曲の背景も知れるので「そういえば歌詞の意味がわからない」「子供の頃から気になっていた」そんな童謡がある方はぜひ一度チェックしてみてくださいね!
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
- ゾゾっと背筋が凍る怖い曲。狂気やホラー性を感じる邦楽
- お月さまを歌った童謡・わらべうた
- 恐ろしい音楽のススメ~実は怖いあの曲
- 【ダークサイド】怖い歌詞の曲。ゾクッとするフレーズに震える曲
- 【びっくり!】海外発祥の童謡。なじみ深いあの童謡も実は
- 【ひな祭りの歌】桃の節句の定番曲。実は知らない!雛祭りソング
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 【ヘビの歌】童謡・わらべうた・手遊びうた
- 世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌
- 雨の日に歌いたい・雨をテーマにした童謡
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- アンパンマンの歌。主題歌・挿入歌・キャラクターの曲一覧
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(21〜30)
指切りげんまん

誰かと約束するときに、その約束を必ず守るという誓いを込めて指を絡め合わせること。
幼少期から多くの方が当たり前のように歌ってきた曲ですが、実は歌詞をそのまま読んでも怖いフレーズが多いと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、指切りげんまんは「指切り拳万」と書き、拳万とは数千数万の拳で殴ることという意味があることから約束を破ったら指を切られた上に何千発も殴られ、さらに針を千本飲ませる、という意味がありました。
約束や規律を破ることが当時いかに大切なことだったかがうかがえる、現代では考えられないほどの恐怖を感じさせる童謡です。
金魚作詞:北原白秋/作曲:成田為三

子供の愛情と残虐性が混在した歌詞が背筋を凍らせる、詩人・北原白秋さんの作詞による童謡。
歌詞の意味そのままに、大好きな母親が帰ってこないことへの寂しさと、それを紛らわすように金魚を殺していく描写がホラーテイストとなっていますよね。
大人であれば寂しさを紛らわす手段もあれば自分で探しにいくこともできますが、待つことしかできない子供の小さい世界の中で起こっている心情の不安定さは、その文章だけで「残酷だ」と断罪してしまうのは浅はかではないかと考えさせられるのではないでしょうか。
良くも悪くも子供らしさが表現されている、怖いというだけでは片付けられない奥深い童謡です。
とおりゃんせわらべ歌

埼玉県や神奈川県の神社が発祥と言われ、江戸時代に歌詞が成立したとみられている遊び歌。
幼少期の遊戯で使われるほか、地域によっては音響信号機のメロディーとして使われているため聴きなじみのある方も多いのではないでしょうか。
その影を感じさせる歌詞やマイナー調の旋律から、神隠しや人柱をイメージさせる都市伝説も根強いですよね。
さらに、被差別部落への一本道を指すとする説まで存在するなど、わらべうたでありながら際立った不気味さを感じさせる童謡です。
シャボン玉作詞:野口雨情/作曲:中山晋平

大正時代に仏教児童雑誌『金の塔』にて歌詞が発表された、詩人・野口雨情さん作詞による唱歌。
賛美歌のテイストを感じさせるどこか幻想的なメロディーは、幼少期に多くの方が口ずさんだことがあるのではないでしょうか。
よう逝してしまった我が子への鎮魂歌として制作されたと言われている歌詞は、その意味をふまえて読むことで違った情景が目に浮かびますよね。
受け止めきれない感情を歌に乗せるという本来の歌の役割を感じさせる、未来まで残したい童謡です。
雀の学校作詞:清水かつら/作曲:弘田龍太郎

『雀の学校』というタイトルや、歌詞に含まれる鳴き声からは、小さなすずめたちが集まるかわいらしい様子が連想されます。
しかし、よく読んでみると、すずめの先生ムチを振るい、生徒たちが一緒に鳴くという、なんとも恐ろしい内容が浮き彫りに。
集団行動や規律を強調しているとされていますが、冷静に考えると非常に過激なシーンといえるかもしれません。
1922年2月の『少女号』で初めて発表され、以来広く親しまれてきた本曲。
童謡としてみんなで楽しく歌うときには、あまり意味を深く追求しない方がよいかも……。
証城寺の狸囃子作詞:野口雨情/作曲:中山晋平

1924年に発表されたこの曲は、たぬきがおなかをポンポコと叩いている姿が思い浮かぶ楽しい曲に思えますよね。
しかし、実は作詞をした野口雨情さんは、狸囃子という怪談をもとに歌詞を書いたんだとか。
どこからともなくお囃子の音が聞こえてくるんだそうで、音のする方へ歩いていってもその音の正体はわかりません。
そして音の正体を探しているうちに、気づけば知らないところまできてしまっているというのが狸囃子のお話です。
そんな怖い怪談がもとになっているとは思いもよらない、軽快なリズムが楽しげな曲調ですね。
いとまきのうた作詞:香山美子/作曲:小森昭宏

手遊びしながら歌う『いとまきのうた』。
香山美子さんが作詞、小森昭宏さんが作曲したこの曲は、デンマークの民謡『靴屋のポルカ』をもとに生まれました。
本作は、こびとさんの家に向かう様子を描写し、子供たちの想像力をかき立てる内容となっています。
歌詞に関しては複数の解釈がありますが、「後半部分は、落とし穴でこびとさんを捕まえてスープの具材にしてしまった」と捉えられる場合もあるようです。
あなたはどう思いますか?
ぜひ、耳にする機会の少ない後半の歌詞にも注目してみてください!