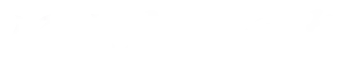実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌
童謡といえば、保育園や幼稚園で子供たちが歌うかわいらしい歌というイメージが強いですよね。
しかし、なかには歌詞をすべて聴くと背筋が凍りついてしまうような恐ろしい曲があるのをご存じでしたか?
この記事では、実は歌詞を深掘りすると怖い童謡を集めてみました。
ただ怖いだけではなく、興味深い曲の背景も知れるので「そういえば歌詞の意味がわからない」「子供の頃から気になっていた」そんな童謡がある方はぜひ一度チェックしてみてくださいね!
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
- ゾゾっと背筋が凍る怖い曲。狂気やホラー性を感じる邦楽
- お月さまを歌った童謡・わらべうた
- 恐ろしい音楽のススメ~実は怖いあの曲
- 【ダークサイド】怖い歌詞の曲。ゾクッとするフレーズに震える曲
- 【びっくり!】海外発祥の童謡。なじみ深いあの童謡も実は
- 【ひな祭りの歌】桃の節句の定番曲。実は知らない!雛祭りソング
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 【ヘビの歌】童謡・わらべうた・手遊びうた
- 世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌
- 雨の日に歌いたい・雨をテーマにした童謡
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- アンパンマンの歌。主題歌・挿入歌・キャラクターの曲一覧
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(21〜30)
ぞうさん作詞:まどみちお/作曲:團伊玖磨

政治、行政、教育、経済、戦争といった社会に対する不満を原動力に、ユーモアにあふれる作品を作り続けたまど・みちおさん作詞の童謡。
幼少期から多くの方が歌ってきたであろう、数ある童謡の中でもメジャーな楽曲ですよね。
他とは違う特徴に対する悪口を、尊敬するお母さんと同じだと胸を張る子供の姿は、差異を気にせず個性を大切にしていこうとする昨今の風潮にもリンクするのではないでしょうか。
キュートな歌詞やメロディーの中に普遍的なテーマが含まれた、誰もが知る童謡です。
はないちもんめ作詞:椎名慶治/作曲:椎名慶治、山口寛雄

二つのグループに分かれて歌を歌い、メンバーを取り合う子供遊び。
漢字では「花一匁」と書き、匁は江戸時代の銀貨の単位を示すことから、表向きには江戸時代の花の売買を表現して童謡と言われています。
しかし、花は若い女性を表す隠語であることから、「かって嬉しい」は安く買えたことを喜んでいる表現で、「まけて悔しい」は値段をまけて買いたたかれたことを示すという都市伝説があることをご存じでしたでしょうか。
口減らしが多かったとされる時代背景を感じさせる、無邪気な子供の声で歌うほど怖さを感じる童謡です。
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(31〜40)
一年生になったら作詞:まどみちお/作曲:山本直純

卒園式、入学式、歓迎会など、現在も子供の新たな門出を祝う席で歌われることが多い童謡。
「友達が100人できたなら自分を入れて101人のはずで、常に100人で何かをしている描写がおかしい」という理由や、制作されたのが1966年という戦時中に制作されたという観点から、一人は間引きされてしまった、仲間に食べられてしまったという都市伝説が多い楽曲としても知られています。
しかしシンプルに考えれば、数えどおり99人や101人ではメロディーとして語呂が悪いということもあり、分かっていてあえて100人にしたと考えるのが普通かもしれませんね。
あまり深掘りせず、子供たちの明るい未来のために使用してほしい童謡です。
赤い靴作詞:野口雨情/作曲:本居長世

横浜のシンボルとして現代でも幅広く知られている童謡。
その歌詞の内容や寂しげなメロディー、そして時代背景などから人身売買をイメージされることも多い楽曲として知られていますよね。
しかし実は生活苦からアメリカ人宣教師の夫妻の養女として幸せになってほしいという母の願いと、渡米前に結核によって児童養護施設で亡くなってしまった女の子を歌った実話というものが定説として言い伝えられています。
歌詞の解釈には数々の議論が存在しますが、その美しく哀愁をまとったメロディーが時代を越えて愛されている童謡です。
メトロポリタン美術館作詞・作曲:大貫妙子

音楽番組『みんなのうた』において1984年の放送以来何度も再放送されている、シンガーソングライター・大貫妙子さんの楽曲。
アメリカの児童小説『クローディアの秘密』から着想を得て制作された楽曲で、かわいらしいメロディーとあやしげなアレンジがキャッチーですよね。
不気味さを感じさせる映像と最終的に絵に閉じ込められるという結末から多くの方が怖いイメージを持っていますが、終始ポップな空気感と「好きな場所にずっといたい」という主人公の気持ちを踏まえて聴くと、また違った印象を受けるのではないでしょうか。
子供にとってはトラウマソングかもしれませんが、大人になってから改めて聴いてみてほしいキュートなナンバーです。
赤とんぼ作詞:三木露風/作曲:山田耕筰

映画『ここに泉あり』や『夕やけ小やけの赤とんぼ』の挿入歌としても使用されている、ヨナ抜き音階を使った郷愁感にあふれる童謡。
作詞を務めた随筆家・三木露風さんの幼少期の記憶をベースに生まれた楽曲で、両親の離婚後に自分を育ててくれたお手伝いさんがお嫁に行ってしまった情景が描かれています。
都市伝説ではお手伝いさんは結婚したのではなく人身売買で売られてしまったとか、赤とんぼとは戦闘機「零戦」のことだとか、当時の時代背景をイメージさせるものが多いですが、実話だけでもじゅうぶんに切ないですよね。
日本の歌百選にも選定された、日本人であれば誰もが知る叙情的な童謡です。
いろは歌

10世紀から11世紀にかけて成立したと言われている、すべての仮名を重複させず作られた作者不明の経文。
諸行無常を悟った人の歌と言われ、現代では栃木県日光市にある「いろは坂」にある48のカーブで数えられることも有名ですよね。
一聴してあまり意味がわからない方も多いであろう歌ですが、原文を7文字ごとに区切り、それぞれの文章の最後をつなげて読むと「とがなくて死す」と読めることから、無罪の罪で死刑となった人の無念を表す歌という都市伝説が存在しています。
現代のSNSでも使われるタテ読みのような表現の逸話に、怖いながらも感心してしまう都市伝説を持った歌です。