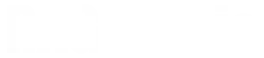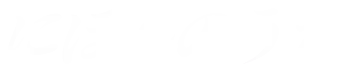実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌
童謡といえば、保育園や幼稚園で子供たちが歌うかわいらしい歌というイメージが強いですよね。
しかし、なかには歌詞をすべて聴くと背筋が凍りついてしまうような恐ろしい曲があるのをご存じでしたか?
この記事では、実は歌詞を深掘りすると怖い童謡を集めてみました。
ただ怖いだけではなく、興味深い曲の背景も知れるので「そういえば歌詞の意味がわからない」「子供の頃から気になっていた」そんな童謡がある方はぜひ一度チェックしてみてくださいね!
実は怖い童謡。聴くとゾッとする子どもの歌(21〜40)
むすんでひらいて文部省唱歌

フランスの哲学者として知られているジャン=ジャック・ルソーさん作曲という外国曲でありながら日本の歌百選に選ばれている童謡。
もともとの作詞者は不明で、日本では賛美歌、唱歌、軍歌といった、それぞれの時代によって歌詞が変化してきた楽曲であることをご存じでしょうか。
2番や3番もなく同じ内容をひたすら繰り返すシンプルな歌詞は、さまざまな考察がなされるほど聴き手にその解釈が委ねられています。
日本においては第二次世界大戦後に童謡として定着し、海外では現在も讃美歌として歌われている楽曲です。
ずいずいずっころばしわらべ歌

手で輪を作って、その輪の中に順番に指を入れていく手遊びで知られている『ずいずいずっころばし』ですが、この歌にも怖い意味があるのをご存じでしたか?
江戸時代に京都、宇治のお茶をつぼに入れ、江戸幕府まで運んだのですが、それは『お茶壷道中』とよばれ、だれもその行列を横切ってはいけないことになっていました。
通るのはただのお茶でしたが、横切ると徳川家の威信を傷つけた、という風にとられたのです。
その行列が通り過ぎるのを息をひそめてみていた街道の庶民の様子がうかがえますね。
赤とんぼ作詞:三木露風/作曲:山田耕筰

映画『ここに泉あり』や『夕やけ小やけの赤とんぼ』の挿入歌としても使用されている、ヨナ抜き音階を使った郷愁感にあふれる童謡。
作詞を務めた随筆家・三木露風さんの幼少期の記憶をベースに生まれた楽曲で、両親の離婚後に自分を育ててくれたお手伝いさんがお嫁に行ってしまった情景が描かれています。
都市伝説ではお手伝いさんは結婚したのではなく人身売買で売られてしまったとか、赤とんぼとは戦闘機「零戦」のことだとか、当時の時代背景をイメージさせるものが多いですが、実話だけでもじゅうぶんに切ないですよね。
日本の歌百選にも選定された、日本人であれば誰もが知る叙情的な童謡です。
森のくまさんアメリカ民謡

作詞作曲が不明のアメリカ民謡をベースとし、アメリカではスカウトソングとして歌われてきた童謡。
幼少期に聴いて「逃げろと言うならなぜ追いかけてくるのか」など、さまざまな疑問を感じられた方も多いのではないでしょうか。
オリジナルの歌詞には日本語詞に登場する耳飾りを届けるという描写はありませんが、逃げろと言いながら追いかけてくるというベースは変わらないため、サディスティックな熊に出くわしたという意味で受け取られることも多いようです。
誰もが幼少期に一度は歌ったであろう童謡でありながら、謎も多い楽曲です。
いろは歌

10世紀から11世紀にかけて成立したと言われている、すべての仮名を重複させず作られた作者不明の経文。
諸行無常を悟った人の歌と言われ、現代では栃木県日光市にある「いろは坂」にある48のカーブで数えられることも有名ですよね。
一聴してあまり意味がわからない方も多いであろう歌ですが、原文を7文字ごとに区切り、それぞれの文章の最後をつなげて読むと「とがなくて死す」と読めることから、無罪の罪で死刑となった人の無念を表す歌という都市伝説が存在しています。
現代のSNSでも使われるタテ読みのような表現の逸話に、怖いながらも感心してしまう都市伝説を持った歌です。