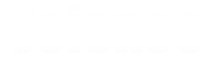【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集
夏休みの自由研究、小学校6年生ならではの面白いテーマを探している方にオススメのアイデアを集めました!
「SDGsについて調べよう」「オリジナル縄文土器を作ろう」など、高学年らしい発想力と工夫が光る研究テーマが勢ぞろい。
友達と差がつく個性的なアイデアばかりですよ。
身近な材料で始められるものから、ちょっと本格的な実験まで、きっとピッタリの研究テーマが見つかるはず。
6年生の夏休みにふさわしい、楽しく取り組める自由研究をスタートしてくださいね!
- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
- 中学生向にオススメ!短時間でできる自由研究のアイデア集
- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
- 小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学生にオススメ!6年生向けの作って楽しい工作アイデア集
- 【男の子向け】ペットボトルキャップを使った工作アイデア
- 先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア
- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集
- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集
【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集(1〜10)
動画製作にチャレンジ

ユーチューブなどで動画を見ることが当たり前になっている現代の子供達にぴったりな動画製作を自由研究に取り入れてみるのもオススメです。
いつもみている動画を今度は自分で撮影して製作してみることはより動画の製作などに深く触れ知れますよね。
誰にどんな動画を見せたいのか、どのくらいの長さで動画を製作するのかテーマを決めて自由研究にしてみるのも面白いのではないでしょうか。
楽しみながら自由研究ができるように興味のあることをテーマに設定するのがオススメです。
ダンゴムシ迷路

どうなるのか興味をそそられる、ダンゴムシ迷路のアイデアです。
その内容は段ボールで作った迷路にダンゴムシを入れて歩かせるというもの。
するとダンゴムシは、右、左、右、左と規則性を持って迷路を進んでいくはずです。
実はこれ、交替性転向反応という習性によるものです。
どうしてそんな習性が備わっているのか、考えたり調べたりしてみてくださいね。
ちなみに、同じ実験に使える虫にはミミズがいます。
セットで試してみるのもよいでしょう。
てこを利用した道具を見つけよう

弱い力で重たいものを動かせるてこの原理、理科の授業で聞いたことのある名前ですよね。
そんなてこの原理がどのようなものかを理解し、それが使われている道具について調べていきましょう。
仕組みを深く考えずに何気なく使っていた道具など、知らてみると意外な発見があるかもしれませんよ。
支点と力点、作用点がてこの原理を考えるうえでは重要なポイントなので、どの部分がそれにあたるのかもあわせて考えていくのがオススメですよ。
【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集(11〜20)
手作り花火

夏といえば花火は欠かせないイベントですよね。
市販されているものを購入するイメージが強いそんな花火を自作してみるのはいかがでしょうか。
作っていくのは線香花火で、火薬の素である酸化剤や燃焼剤、閃光剤を混ぜ合わせて、紙に巻いていくという内容ですね。
パチパチとはじけるように燃えるので、安全面には注意しつつ、より長持ちする量や巻き方などを試していきましょう。
火薬の乗せ方によっては燃え方にもムラが出るので、集中して作業に挑むことも重要なポイントですよ。
基本ロボットの作り方

自分の力でロボットを作る!
基本ロボットの作り方のアイデアをご紹介します。
近年では、さまざまな用途で活躍するロボットを見かけますよね。
ファストフード店では、料理や飲み物を運ぶロボットがいたり、ロボットのペットを飼っているというご家庭もありますね。
今回は、基本的なロボットを作ってみましょう。
準備するものは定規、ハサミ、ペン、厚紙、電池、電池ボックス、スイッチ、モーター、コードなどです。
先生や保護者の方と一緒に取り組んでみてくださいね。
顕微鏡でいろいろなものを観察

顕微鏡でいろいろなものを観察してみるのも楽しいですよ。
まずは思い付くままに顕微鏡で観察してみましょう。
自分の髪の毛や、普段食べているお菓子など身近なものだと興味がわきやすいかもしれません。
ただ観察してみるだけでもOKなのですが、さらに踏み込んで研究してみると、よりおもしろいですよ。
保護者の方の毛や、他のお菓子などと比べてみましょう。
そしてどうして違うのかなと考えてみてください。
ちなみに子供向けの顕微鏡は2千円程度で購入できます。
夏の星空観察

せっかくなら夏にしかできないことにチャレンジしてみませんか!
夏の星座観察は、王道かつ超オススメなアイデアです!
なんたって宇宙が題材ですので、調べれば調べるだけ新しい知識が得られます。
その星座がどういう星々で構成されているのか、誰がどこで発見したのか、名前の由来やその星座にちなんだ神話など、もしかしたら一夏ではまとめきれないぐらいになるかも。
小学校最後の自由研究、ぜひ大作を仕上げてくださいね。
ちなみに夏の星座には、いて座、さそり座、はくちょう座などがあります!