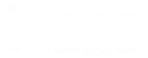ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
ピアノ曲といえば、クラシック作品をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
しかし現代ではクラシックだけでなくJ-POPやアニソンなどいろいろな楽曲がピアノで演奏され、SNSや動画サイトで「弾いてみた」動画が注目を浴びています。
「こんな曲もピアノと相性が良いんだ!」と驚きながら、毎日動画視聴を楽しんでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そこで今回は、ピアノで弾けたらかっこいいなと思える楽曲をピックアップ!
クラシックの名曲はもちろん、ピアノでかっこよく弾ける最新ヒット曲などもご紹介しますので、ピアノ演奏を披露してみんなをあっと言わせたい!と思っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 初心者でもピアノで簡単に弾ける!J-POPの人気曲&最新曲を厳選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【ピアノ×J-POP】弾けたらかっこいい最新曲・アニソンを厳選
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- かっこいいジャズピアノ。定番の人気曲から隠れた名曲まで
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【ピアノ弾き語り】ピアノ弾き語りにおすすめ!平成~令和のヒット曲
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ(91〜100)
ヴォカリーズ 作品34-14Sergei Rachmaninov

『ヴォカリーズ』は、ロシアの偉大な作曲家、セルゲイ・ラフマニノフの作品の中でも著名なピアノ伴奏つきの歌曲で、ピアノ独奏のみならず多くの楽器による編曲が行われている人気の高い名作です。
あまりにも美しくメランコリックな主旋律を聴いていると、まるで誰かの人生の1ページが垣間見えるかのよう。
歌詞が存在しないからこそできる自由な解釈と表現で、自分オリジナルの『ヴォカリーズ』に仕上げてみてはいかがでしょうか?
風の即興曲中田喜直

アルバム『こどものゆめ』に収録された一曲は、まるで風が吹き抜けていくような爽やかな旋律が印象的です。
軽やかで流れるような自由なメロディが心地よく、グリッサンドの技法を取り入れた仕上がりは発表会でも魅力的な要素となっています。
本作は、流麗なフレーズと繊細なタッチが溶け合い、ピアノならではの表現力を存分に引き出した1分20秒の小品。
2011年のピティナ・ピアノコンペティションでC級の課題曲に選ばれた本作は、音楽の楽しさを感じながら技術を磨きたい方におすすめの一曲です。
手の大きさを考慮した自然な運指で、誰もが楽しく演奏できる工夫が施されています。
ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ(101〜110)
鉄道Charles Valentin Alkan

産業革命の象徴である鉄道をモチーフにしたピアノ独奏曲で、シャルル=ヴァランタン・アルカンが1844年に作曲しました。
左手で刻む規則的なリズムと右手の華麗なメロディーラインが鮮やかに絡み合い、蒸気機関車の力強い走行音や規則的な車輪の音を見事に表現しています。
本作は軽快でリズミカルな曲調でありながら、ロマン派音楽特有の情感が豊かな表現も織り込まれており、聴き手を魅了する独創的な作品に仕上がっています。
発表会でインパクトのある演奏を披露したい方や、技巧的な曲に挑戦したい方におすすめの一曲です。
ラジオ番組や鉄道関連のドキュメンタリーでも使用される、多くの人々に愛されている名作です。
アルマンド イ長調 WoO 81Ludwig van Beethoven

4分の4拍子で優雅に流れる舞曲は、16世紀から17世紀にかけて人気を博したドイツの伝統的なスタイルを踏襲しながら、1793年ウィーンで作曲された作品です。
右手で奏でられる華やかな旋律と、左手の落ち着いた伴奏が見事に調和し、短い演奏時間ながらも豊かな音楽表現が詰まっています。
本作は穏やかな流れの中にベートーヴェンらしい個性的な表現が織り込まれ、落ち着いた気分で演奏を楽しめます。
シンプルながらも魅力的な旋律は、ピアノを楽しく練習したい方や、クラシック音楽の世界に触れてみたい方にぴったりの一曲です。
ジャンルカ・カッショーリやロナルド・ブラウティガムなど、著名なピアニストたちの演奏でも親しまれています。
決戦-ファイナルファンタジーX Piano collectionsより植松伸夫

「ファイナルファンタジーX」のバトルシーンを飾る人気楽曲のピアノアレンジ版です。
原曲の持つ迫力とエネルギッシュな展開を、ピアノ一台で見事に表現した意欲作。
速いテンポと複雑なリズム、ダイナミックな強弱の変化が織りなす緊張感があふれる世界観に、聴く人を圧倒します。
2002年にリリースされたアルバム『Piano Collections FINAL FANTASY X』に収録された本作は、変拍子や転調を巧みに取り入れた独創的な楽曲構成で、演奏者の技術と表現力が存分に試される1曲です。
発表会での演奏を通じて、聴衆に強い印象を残したい方にぴったり。
華やかで情熱的な演奏を披露できる、魅力的なレパートリーとなるはずです。
ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」 第3楽章Ludwig van Beethoven

力強く情熱的な性格を持ち、堂々とした雰囲気が魅力の楽曲です。
印象的な冒頭から心をつかむメロディが、繰り返し現れながら緊張感と解放感を交互に提供することで、聴く人を自然と音楽の世界へと引き込んでいきます。
1799年に出版された当時から高い評価を受け、現代まで世界中で演奏され続けている本作は、ダイナミックな表現と豊かな音色の変化が見どころです。
テレビ番組や映画でも度々取り上げられ、ビリー・ジョエルの『This Night』でも旋律が引用されているほど影響力のある作品です。
ピアノの魅力を存分に引き出す構成で、急速なパッセージと表現力を磨きたい意欲的な演奏者にぴったりの1曲といえるでしょう。
8つの演奏会用練習曲より 第5曲「冗談」Nikolai Kapustin

クラシックとジャズが融合した躍動感があふれる楽曲です。
1984年に発表されたアルバム『8つの演奏会用練習曲 Op.40』に収録された本作は、軽快でユーモアもたっぷりな性格を持ち、聴く人の心をくすぐります。
スウィングやブギウギなどジャズの要素を巧みに取り入れながら、クラシックの形式美も大切にした魅力的な一曲。
リズミカルで躍動感のあるフレーズが次々と展開され、会場全体を楽しい雰囲気で包み込みます。
ニコライ・ペトロフやマルク=アンドレ・アムランなど、世界的なピアニストたちも演奏するこの作品は、技術と表現力を存分に披露したい方にぴったり。
観客を魅了する素晴らしいステージを作り上げられることでしょう。