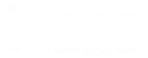ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
ピアノ曲といえば、クラシック作品をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
しかし現代ではクラシックだけでなくJ-POPやアニソンなどいろいろな楽曲がピアノで演奏され、SNSや動画サイトで「弾いてみた」動画が注目を浴びています。
「こんな曲もピアノと相性が良いんだ!」と驚きながら、毎日動画視聴を楽しんでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そこで今回は、ピアノで弾けたらかっこいいなと思える楽曲をピックアップ!
クラシックの名曲はもちろん、ピアノでかっこよく弾ける最新ヒット曲などもご紹介しますので、ピアノ演奏を披露してみんなをあっと言わせたい!と思っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 初心者でもピアノで簡単に弾ける!J-POPの人気曲&最新曲を厳選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【ピアノ×J-POP】弾けたらかっこいい最新曲・アニソンを厳選
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- かっこいいジャズピアノ。定番の人気曲から隠れた名曲まで
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【ピアノ弾き語り】ピアノ弾き語りにおすすめ!平成~令和のヒット曲
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ(51〜60)
真夜中の火祭り平吉毅州

炎が燃え盛る情景を思わせる熱烈な日本人作曲家、平吉毅州さんによるピアノ独奏曲です。
ダイナミックで激しい響きと、緻密なアーティキュレーションが見事に調和し、夜空に舞い上がる火の粒を表現しています。
独特の変拍子が生み出す躍動感と、スペイン舞踊を思わせるリズムパターンが、聴く人の心を高揚させます。
2024年度PTNAピアノコンペティションの課題曲に選定されており、ピアノ学習者の技術向上に役立つ作品としても評価が高まっています。
短調の響きながらも暗さを感じさせない力強さがあり、暑い夏の夜に聴くことで心が躍るような清涼感が得られる一曲です。
幻想曲さくらさくら平井康三郎

日本の伝統音楽を現代に蘇らせたピアノ独奏曲をご紹介します。
本作は、古くから親しまれている旋律を基に、日本の作曲家平井康三郎さんがピアノソロでも楽しめる幻想曲として生まれ変わりました。
冒頭の穏やかな序奏から始まり、中盤では太鼓のようなリズムが加わり、祭りの賑わいを感じさせます。
そして最後は、静かに幕を閉じます。
日本の春の情景が音楽で描かれているかのようですね。
日本の伝統音楽に興味がある方や、日本発のクラシック音楽を楽しみたい方におすすめです。
ぜひ一度耳を傾けてみてください。
ドラゴンクエスト「序曲」すぎやまこういち

日本を代表するゲーム音楽として知られる本作は、壮大なオーケストラサウンドが特徴的です。
冒頭のファンファーレから始まり、高揚感のある旋律が展開されていきます。
冒険の始まりを告げるようなメロディーは、聴く人の心を奮い立たせる力を持っています。
ゲーム音楽の枠を超えて、さまざまな場面で演奏されることも多く、2021年の東京オリンピック開会式でも使用されました。
ゲームファンはもちろん、ピアノでチャレンジしたい1曲です。
短いながらもストーリー性のある構成で、弾く度に新たな冒険への期待が膨らむことでしょう。
無言歌集 第5巻 Op.62 第6曲 春の歌Felix Mendelssohn

フェリックス・メンデルスゾーンの名作『無言歌集 第5巻 Op.62 第6曲 春の歌』。
この作品の魅力は、非常に洗練された美しいメロディーと、春の暖かな風を連想させる左手のアルペジオ。
難易度としてはそれほど高くありませんが、跳躍する左手の音を正確にとらえながらメロディをなめらかに演奏するのは決して簡単ではありません。
音を並べるだけではなく、メンデルスゾーンの作品らしい繊細な美しさを追求しながら、練習に取り組んでみてくださいね!
ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ(61〜70)
ノクターン 第19番Op.72-1 ホ短調「遺作」Frederic Chopin
1827年頃、わずか17歳で作曲されたとは思えないほど深い哀愁を湛えた夜想曲です。
左手の絶え間なく続く三連符のアルペジオが心の揺らぎを表現し、その上に乗る右手の素朴で物悲しい旋律が、胸の内に秘めた想いを静かに語りかけます。
本作はホ短調で始まりながら、最後は温かい長調で静かに終わる構成が特徴的で、涙のあとの穏やかな安らぎを感じさせます。
ドラマ『Fringe』でも使用されました。
感傷的な夜に一人でじっくり向き合いたい、そんな気分に寄り添ってくれる一曲です。
ファイナルファンタジーⅩ「ザナルカンドにて」(Piano collections ver.)植松伸夫

美しい旋律が印象的な切ないメロディーは、耳に心地よく響きながらも深い余韻を残します。
物語の舞台となる架空の都市を象徴する本作は、主人公の故郷への思いや、運命に翻弄されるキャラクターたちの葛藤が繊細に表現されています。
2004年7月にリリースされたアルバム『Piano Collections FINAL FANTASY X』に収録され、ピアノならではの表現力で物語性が一層引き立てられました。
本作はゲーム音楽の枠を超えて多くの場面で演奏される人気曲となり、その普遍的な魅力で聴く人の心を魅了し続けています。
ピアノを始めたばかりの方でも、美しいメロディーラインを丁寧に練習することで、深い感動を表現できる1曲です。
奏スキマスイッチ

2004年に発売されたスキマスイッチの楽曲、多くのアーティストにもカバーされた彼らの代表曲ともいえる曲です。
別れの季節に苦しみを感じつつ、先へと進んでいこうとするさみしさや切なさといった感情を強くイメージさせるようなバラードです。
スキマスイッチのサウンドといえばギターとピアノの音色が中心で構成されますが、この楽曲ではピアノの音色が強く出ているような印象。
ピアノだけで演奏しても、曲の持つ穏やかな雰囲気は再現できるのではないでしょうか。