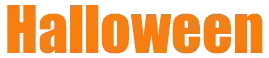ハロウィンに観たいホラー映画!ガチ怖から笑えるコメディ作品まで
怖いけど笑える、ゾッとするけどクスッとしちゃう…。
最初から最後まで怖い!
そんな不思議な魅力を持つホラー映画を紹介します。
ハロウィンシーズンだからこそ楽しみたい、ホラーとコメディが絶妙なバランスで融合した作品たちを集めました。
怖がりな方も笑いで恐怖を和らげながら楽しめる、ユニークな世界観の映画もありますよ。
仲間と一緒にみれば、さらに面白さは倍増!
笑ったり震えるホラー映画で特別なハロウィンを過ごしてくださいね!
ハロウィンに観たいホラー映画!ガチ怖から笑えるコメディ作品まで(1〜10)
ハロウィーンタウンデュウェイン・ダナム

『ハロウィーンタウン』というタイトルだけなら、あの『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』を思い出す方も多いかもしれませんが、こちらは1998年にディズニー・チャンネルのテレビムービーとして制作された作品です。
かの名作ミュージカル映画『雨に唄えば』などで知られている女優、デビー・レイノルズさんがチャーミングなおばあちゃん役として出演しておりましたね。
4作品のシリーズが作られるなど、ハロウィン映画の定番として人気を博しました。
子どもの頃に観て、ハロウィンといえばこの映画が最初に頭に浮かんでくるという方もいらっしゃるはず。
残念ながら2020年の現時点ではソフト化されておらず、気軽に見られる作品ではないのですが、機会に恵まれたらぜひチェックしてみてくださいね。
ナイトメアー・ビフォア・クリスマスヘンリー・セリック

定番中の定番、ここ日本においても最も有名なハロウィン映画の筆頭に挙げられるのが、この『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』でしょう。
原案・原作は『シザーハンズ』や『チャーリーとチョコレート工場』などで知られるティム・バートンさんが担当し、1993年の公開以来根強い人気を誇るミュージカルアニメーション映画です。
当時の最新のデジタル映像技法と往年のストップモーション・アニメーション技法をたくみに取り入れた映像美はいつ見ても素晴らしく、本作との出会いがきっかけでクリエイターを志したという方も世界中にいるくらいに影響力のある作品です。
「ハロウィン・タウン」の住人たちのコミカルな動きはまるで本当に存在しているかのようで、実に魅力的ですよね。
ハロウィン・シーズンの基本として、押さえておくべき名作です!
ティム・バートンのコープスブライドティム・バートン

やはりホラーアニメーションといえばティムバートンでしょう!
ディズニー映画『ナイトメアビフォアクリスマス』の作者として有名な彼ですが、ナイトメア以外にも代表作があり、それがこちら『コープス・ブライド』です。
死人の花嫁と生きている人間のお話で、ティムバートンの手がけたユーモラスでかつホラーな世界観が最高におもしろい映画です。
アダムス・ファミリーバリー・ソネンフェルド

映画やオリジナルのテレビ・シリーズを見たことがないという人であっても、あまりにも有名なテーマソング『The Addams Family』は誰もが一度は耳にしたことがあるのでは?
お化け一家のアダムス・ファミリーが織り成すホラー・コメディとして、世界的な人気を誇る『アダムス・ファミリー』は、ハロウィンの定番映画としても人気のシリーズです。
その独特の雰囲気と個性的なキャラクターは、ティム・バートンさんなどのクリエイターにも大いにインスピレーションを与えました。
2020年の9月には新たなアニメーション映画として公開され、世代をこえて愛されている作品です。
今回紹介しているのは、1991年に公開された劇場版シリーズ第一弾。
小さなお子さまのいるご家族でも楽しめる、ちょっぴり怖くてユーモアたっぷり、感動もできる秀逸な1本ですよ!
悪魔のいけにえトビー・フーパー

『13日の金曜日』や『エルム街の悪夢』など、スプラッター映画の名作は数多くありますよね。
その先駆けとなった映画が、トビー・フーパー監督の『悪魔のいけにえ』です。
その内容は、若者たちがチェーンソーを持ったレザーフェイスというキャラクターに襲われるというもの。
かなりショッキングなシーンも含まれているので、苦手な方は注意してくださいね。
そして、この『悪魔のいけにえ』は1974年に公開されて以来、続編が作られ続けている人気シリーズでもあるんです。
気に入った方は、続編もチェックしてくださいね。
オオカミの家クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ

普通の映画は観飽きた、という方には『オオカミの家』がオススメです。
こちらはクリストバル・レオンさんと、ホアキン・コシーニャさんが手掛けたストップモーションアニメ。
怪しげな組織から逃げ出してきた女性が、男たちに追い詰められていく様子を描いています。
言葉では言い表せないほど不気味でおぞましい映像が見どころですね。
かなり珍しい手法の作品なので、まずは予告編を見てみてください。
約2分ですが、それだけでもかなり怖いです。
屋根裏のアーネストクリストファー・ランドン

引っ越したばかりの家で遭遇した記憶喪失の幽霊、アーネストとの交流を描いた、コメディでありつつあたたかさも感じられる作品です。
アーネストとであうまでは何かがいるかもしれないというホラーの要素が強く、遭遇してからの流れはコメディの要素が強くなっていく印象ですね。
謎につつまれたアーネストの過去を調査、その中で政府機関にも目をつけられるという激しい展開から、しっかりと物語の世界観にひきこまれます。
幽霊だからこその自由な動き、それに振り回される町の人々のリアクションも注目したいポイントです。