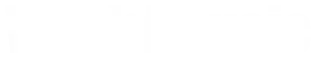現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲
現代音楽と言われても、そういった音楽ジャンルがあること自体知らない、という方が大多数なのではないかと思います。
知識として多少は知っていたとしても、敷居が高く難解なイメージを抱かれている方も多いのではないでしょうか。
クラシックのみならず、ミニマル・ミュージックからアヴァン・ポップ、フリージャズ、ノイズ・アヴァンギャルドにいたるまで、現代音楽の影響は多くの分野で根付いています。
そんな現代音楽の名曲とされる楽曲を軸として、幅広い分野における楽曲を選出してみました。
- 【定番】コンテンポラリー・ミュージックの名曲
- ミニマルミュージックの名曲|マイナーな作品も登場
- 【2026】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- Z世代に人気の高い洋楽。ヒットソング
- 洋楽のピアノの名曲。おすすめの人気曲
- 【タンゴ】タンゴの名曲。おすすめの人気曲
- 【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- K-POPの名曲&ベストヒット集【最新&定番の人気ソング+エディターセレクト】
- 誰でも知ってる洋楽。どこかで聴いたことがある名曲まとめ
- 【クラシック】ワルツの名曲。おすすめの人気曲
- 【2026】ミュージカルの名曲。最新作から往年の名作まで紹介!
現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲(1〜10)
月に憑かれたピエロArnold Schönberg

『月に憑かれたピエロ』という邦題でも知られるこちらの作品は、もともとはベルギーの詩人が発表したフランス語の詩集であり、ドイツ語訳のものを題材とした音楽作品。
複数の作曲が曲付けしている中で、最も有名な作品が、オーストリアの作曲家であるアルノルト・シェーンベルクさんが手掛けたものです。
シェーンベルクさんはいわゆる調性音楽を脱した「十二音技法」を創始したことで知られ、アメリカに移住してからは弟子にあのジョン・ケージさんを持つなど、現代音楽家に大きな影響を与えた存在です。
今回紹介している『月に憑かれたピエロ』は、十二音技法を確立する以前の作品であり、調性を放棄した無調が提示された作風で、現代音楽の傑作のみならず、20世紀の音楽史において重要な作品の1つです。
一般的な室内楽から著しく脱した不協和音の連続、歌と詩の朗読の中間のような歌曲が絡み合い、複雑で奇怪な世界を作り上げています。
美しい旋律は皆無、決して心地良いものではありませんが、他の音楽では味わえない音楽的な体験として、日本語の訳詞を片手にぜひ挑戦してみてください。
Epitaph for MoonlightRaymond Murray Schafer

いわゆる「サウンドスケープ」という概念を提唱したことで有名なカナダの作曲家、レーモンド・マリー・シェーファーさん。
日本の合唱団のために書かれた合唱曲も多く、残念ながら2021年の8月14日に亡くなられてしまったことも記憶に新しいですね。
そんなシェーファーさんが1968年に発表した『Epitaph for Moonlight』は、邦題では『月光への碑文』と呼ばれる人気の作品です。
学生合唱団のための練習曲として書かれたものだそうですが、楽曲の持つ幻想的かつ神秘的な響きは聴いているだけで厳粛な気持ちにさせられます。
メイン・フレーズの反復やきっちりとした拍分割をするタイプの楽曲ではなく、自由度の高さが特徴的で、無伴奏や金属打楽器群を用いて演奏される場合もあり、それぞれのパートが個性豊かに表現しながら、1つのアンサンブルを作り上げていく様は、まさに「音の風景」というべきものかもしれませんね。
世の終わりのための四重奏曲Olivier Messiaen

1908年生まれ、フランスはアヴィニョン出身のオリヴィエ・メシアンさんは20世紀を代表する現代音楽家というだけでなく、オルガン奏者やピアニストでもあり、音楽教育者としても業界に多大なる貢献を果たした偉大な人物です。
メシアンさんの教えを受けた学生は、ピエール・ブーレーズさんやカールハインツ・シュトックハウゼンといった著名な方々がいることだけ見ても、メシアンさんが音楽史においてどのような立ち位置にいるのかがわかるというものでしょう。
そんなメシアンさんは作曲家としても多くの作品を残しておりますが、今回は第二次世界大戦中に収容所で捕虜となっていた過酷な時期に作曲された『世の終わりのための四重奏曲』を紹介しましょう。
ヴァイオリン、クラリネット、チェロ、ピアノという異色の編成で演奏され、新約聖書「ヨハネの黙示録」から着想を得た宗教的な背景を持つ室内楽の大作です。
作品そのものの革新性や素晴らしさはもちろん、特殊な状況下で作曲された歴史的事実やどのように初演を迎えたのかなど、興味のある方はぜひご自身で調べてみてくださいね。
現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲(11〜20)
海の音調への練習曲Salvatore Sciarrino

何はともあれ、この楽曲については演奏動画をご覧いただきたいです。
カウンターテナー、フルート四重奏、サクソフォン四重奏、パーカッションという編成に加えて、なんと100本のフルートと100本のサクソフォンで表現する壮大な音響実験の如き作品なのですね。
200人以上の奏者がステージに立つ姿だけでも壮観ですが、そもそもこれをやろうという発想自体に感服してしまいます。
原題は『Studi per l´Intonazione del Mar』というこちらの楽曲を生み出したのは、イタリア出身の現代音楽作曲家、サルヴァトーレ・シャリーノさん。
基本的に独学で作曲を学ばれたそうで、常識的なクラシック音楽の理論では絶対に表現できない、シャリーノさんの独創的な作品群は高く評価されています。
こちらの楽曲も、いわゆるメロディアスで美しいフレーズなどは皆無、まさしく海そのものが生み出す音の調べであり、できればCD音源ではなく実際にホールで体験すべき音世界であると言えましょう。
fullmoon坂本龍一

「教授」こと坂本龍一さんは、今さら説明するまでもなく、日本が世界に誇る偉大な音楽家ですよね。
今回、現代音楽というテーマで坂本さんの楽曲を取り上げたのは、いわゆる基本的な音楽理論を身に付けた上で、それらのフォーマットを用いた素晴らしい名曲を多く生み出しながらも、10代で現代音楽に目覚め、既存の形式やルールにとらわれない作曲活動を続けてきたという経緯を踏まえたことが理由としてあります。
こちらの『fullmoon』は、2017年にリリースされたソロ名義としては8年ぶりとなったオリジナル・アルバム『async』の収録曲で、ヴォーカル入りの楽曲。
坂本さんが映画音楽を手掛けた小説『The Sheltering Sky』から引用された文章、というのも興味深いですね。
アルバム自体に「架空のアンドレイ・タルコフスキー監督の映画音楽」というコンセプトがあり、非常に映像的なイメージを感じさせる作品なのです。
音楽というものの先入観をできる限り取っ払って、無心で向き合ってみてください。
断ち切られた歌Luigi Nono

イタリアはヴェネツィア出身のルイジ・ノーノさんは、戦後の現代音楽~前衛音楽において中心的な役割を果たした作曲家です。
20世紀ドイツ最大の交響曲作家とも言われるカール・アマデウス・ハルトマンさんが、バイエルン放送と共同で主催した現代音楽の演奏会「ムジカ・ヴィーヴァ」でその名を知られるようになったとも言われており、いわゆるセリエル技法を習得した初期から電子音楽に興味を持ち始めた中期、新たな地平へと進んだ後期で作風が違うことでも有名な存在ですね。
エドガー・ヴァレーズさんやカールハインツ・シュトックハウゼンさんといった先鋭的な作曲家と交流しながらも後に決別している、という点もノーノさんが独自の道を歩むタイプであることを物語るエピソードと言えそうです。
共産主義者でもあり、政治的な思想を作曲へと落とし込むタイプのノーノさんが1955年から1956年にかけて作曲した『Il canto sospeso』は、彼の代表作と言える声楽作品、カンタータです。
『断ち切られた歌』という邦題のこの作品は、戦時中の抵抗運動の闘士たちによる遺書からインスパイアされ、十二音技法と独自のセリエル技法を駆使したもので、当時大ヒットを記録したそうです。
音だけでなく、その背景にあるメッセージ性はぜひ知っておくべきものと言えるでしょう。
Music for 18 MusiciansSteve Reich

現代音楽というカテゴリーの中で、ミニマル・ミュージックと呼ばれるジャンルが存在します。
クラシック音楽を源流に持ったミニマル・ミュージックは、ミニマルという言葉が持つ意味の通り、音の動きを最小限に抑制した上で、1つのパターンが反復していく手法で生み出される音楽。
後のミニマル・テクノなども、そういったミニマル・ミュージックの音楽的方法論を取り入れたジャンルの1つです。
そんなミニマル・ミュージックを代表する作曲家、スティーヴ・ライヒさんの名曲『18人の音楽家のための音楽』を紹介しましょう。
1974年の5月から1976年の3月にかけて作曲され、複数のモチーフが反復しながら少しずつ楽曲が変化していくミニマル・ミュージックの基本的な音楽構成を持ちながらも、タイトル通り演奏には大規模な編成を要求され、音楽の歴史に新たな可能性を生み出した重要な作品と言っても過言ではないでしょう。
難解のようで意外に聴きやすく、既存のメロディとは違う豊潤な響きを持ったフレーズが繰り返される中で、受け手は体験したことのない世界の扉を開く事となるでしょう。