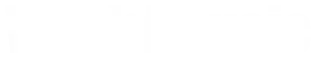現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲
現代音楽と言われても、そういった音楽ジャンルがあること自体知らない、という方が大多数なのではないかと思います。
知識として多少は知っていたとしても、敷居が高く難解なイメージを抱かれている方も多いのではないでしょうか。
クラシックのみならず、ミニマル・ミュージックからアヴァン・ポップ、フリージャズ、ノイズ・アヴァンギャルドにいたるまで、現代音楽の影響は多くの分野で根付いています。
そんな現代音楽の名曲とされる楽曲を軸として、幅広い分野における楽曲を選出してみました。
- 【定番】コンテンポラリー・ミュージックの名曲
- ミニマルミュージックの名曲|マイナーな作品も登場
- 【2026】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- Z世代に人気の高い洋楽。ヒットソング
- 洋楽のピアノの名曲。おすすめの人気曲
- 【タンゴ】タンゴの名曲。おすすめの人気曲
- 【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- K-POPの名曲&ベストヒット集【最新&定番の人気ソング+エディターセレクト】
- 誰でも知ってる洋楽。どこかで聴いたことがある名曲まとめ
- 【クラシック】ワルツの名曲。おすすめの人気曲
- 【2026】ミュージカルの名曲。最新作から往年の名作まで紹介!
現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲(11〜20)
THE HEART ASKS PLEASURE FIRSTMichael Nyman

スティーヴ・ライヒさんなどに代表されるミニマル・ミュージック界における著名な作曲家であり、映画音楽としても大成、音楽評論家の顔も持つイギリス出身のマイケル・ナイマンさん。
音楽評論の中で初めて「ミニマル」という概念を持ち込んだのもナイマンさんであり、実験音楽についての研究論文などは、後の現代音楽評論にも大きな影響を与えています。
そんなナイマンさんの名前を世界的なものとして、ミニマル・ミュージックに興味がない層へもその才能を知らしめた作品と言えば、1992年に公開された名作映画『ピアノ・レッスン』の映画音楽でしょう。
とくにピアノ・ソロ曲で『楽しみを希う心』という邦題でも知られるこちらの楽曲は際立って美しく、ヒーリング・ミュージックとしても大人気となりました。
寄せては返す波のように反復していくメロディの素晴らしさ、圧倒的なエモーションの洪水の中で味わう音楽体験は極めて特別なものと言えます。
未見の方は、ぜひ映画本編もチェックしてみてくださいね。
A Rainbow in Curved AirTerry Riley

テリー・ライリーさんは、スティーヴ・ライヒ さんやフィリップ・グラスさん、そしてラ・モンテ・ヤングさんらと並んでミニマル・ミュージックの代表的な作曲家として挙げられる存在です。
2020年の2月、新プロジェクト実施のために佐渡島へ来日していたライリーさんが、パンデミックの影響もあり、85歳という年齢でそのまま日本へ移住することを決意したことも記憶に新しいですよね。
そんなまだまだバリバリ現役なライリーさんが1969年にリリースした、2曲入りの傑作『A Rainbow in Curved Air』の表題曲を紹介します。
1つのフレーズが反復していくミニマル・ミュージックの手法を軸として、オーバーダビングを用いた電子オルガンやハープシコード、タブラッカといった楽器で生み出された18分をこえる音世界は、まさに虹色のサイケデリアのごとし。
どこか異国情緒を感じさせる、というのもポイントです。
あのザ・フーのギタリスト、ピート・タウンゼントさんがこの曲に影響を受けて名曲『Baba O’Railey』を作ったという逸話も踏まえると、この楽曲の偉大さが理解できるというものでしょう。
SinfoniaLuciano Berio

1968年から1969年にかけて作曲された『Sinfonia』は、ニューヨーク・フィルハーモニックの125周年を記念して委嘱された作品です。
作曲を担当したのは、イタリアの著名な現代音楽作曲家のルチアーノ・ベリオさん。
ピアノ~クラリネット奏者として活動するも軍隊生活の中で右手を負傷、その後はいわゆるミュージック・セリエルに興味を抱きつつ、1950年代には電子音楽へと接近。
70年代にはオペラに取り組むなど、多くの領域で活躍した多作なタイプの作曲家です。
そんなベリオさんが手掛けたこちらの『Sinfonia』は5つの楽章で構成されている、8人の混声重唱を伴う管弦楽曲で、それぞれの楽章に興味深いテーマが設けられています。
細かい説明は省きますが、社会人類学者のクロード・レヴィ=ストロースの引用から始まって、キング牧師へのオマージュと言える第二部、マーラーの交響曲第2番「復活」を始めとするさまざまなクラシック音楽や詩人の言葉などのコラージュ……と、何とも不思議な世界が繰り広げられる前衛的なオーケストラです。
元ネタを知っている方が楽しめますから、先にこの作品で引用されている曲などを調べた上で、聴いてみるのもいいかもしれません。
Jeux vénitiensWitold Lutosławski

戦後におけるポーランドの前衛的な現代音楽家として知られるヴィトルト・ルトスワフスキさんは、欧州ではいわゆる「ポーランド楽派」とも呼ばれ、その代表的な作曲家兼ピアニストとして著名な方です。
ここ日本においても高く評価されており、第9回京都賞精神科学・表現芸術部門において受賞を果たしています。
新古典主義からその作風をスタートさせるも、調性にとらわれない手法を取り入れ、たとえばジョン・ケージさんの『ピアノとオーケストラのためのコンサート』に衝撃を受けるなど、時代の流れとともに常に新しい音楽の表現方法を模索し続けた作風で、独自の個人様式を追求し続けたルトスワフスキさんの作品の中でも、今回は転換期と呼ばれる時期の1961年に作曲された『Jeux vénitiens』を紹介します。
「コントロールされた偶然性」を導入したと言われ、演奏者たちの自由な演奏に任せているようで、実は厳密にコントロールされているという作風の管弦楽曲です。
アドリブという名の偶然性を、あくまでコントロールされたルールの下で成立させることによって、カオティックな音の混乱ではない精密かつ壮絶な音世界を作り上げているのですね。
限りなく前衛的な作品ではありますが、あえてそういったことは気にせずこの音の奔流に飛び込んでみてはいかがでしょうか。
Piano ConcertoElliott Carter

1908年生まれ、2012年に103歳という生涯を終えるまで、現役で在り続けたのがアメリカ出身の現代音楽家の巨匠、エリオット・カーターさんです。
その長い作曲家人生は、一般的には新古典主義の初期、調性を離れて複雑なリズムを取り入れて、ピッチクラス・セット理論と呼ばれる概念を打ち出した中期、ヨーロッパに紹介されて世界的な名声を得た後期の3つに分けられています。
今回紹介している『Piano Concerto』は1964年に作曲された中期の楽曲であり、いわゆる通常の『ピアノ協奏曲』とは違う、非常に複雑で難解な作品となっており、現在においてもあまり演奏される機会はないそうです。
美しいメロディやフレーズ、といったようなものを求めている方にとっては「これは音楽なのか」と感じてしまうかもしれませんね。
典型的な現代音楽のスタイルとも言える作風ですから、この作品を聴いて何か感じ入るものがあれば、より深掘りしていくきっかけとなるのではないでしょうか。
Un tranquillo posto di campagna, Pt. 11Ennio Morricone

2020年7月26日、映画音楽の歴史において最も重要な作曲家の1人であるエンニオ・モリコーネさんが91歳の生涯を終えました。
1928年にイタリアはローマで生まれたこの偉大なマエストロは、1960年代初頭に映画音楽家としてデビューして以来、映画史に残る素晴らしい楽曲を生み出し続け、映画の添え物ではなく、時には主役級の輝きを放つスコアを提供し、名画の誕生に貢献したとも言えるでしょう。
そんなモリコーネさんは『荒野の用心棒』などの初期のマカロニウエスタンにおける哀愁漂う名曲、または『ニュー・シネマ・パラダイス』などのメロディアスで美しい作風以外にも、実験的な音楽家としての顔を持っています。
今回紹介している楽曲は、1969年に公開された『怪奇な恋の物語』のサウンドトラックで、モリコーネさん自身が所属していた即興演奏グループによる現代音楽ど真ん中のサウンドを聴けば、一般的なモリコーネさんのイメージはがらりと変わるはずです。
モリコーネさんによるトランペット演奏も含まれており、複雑怪奇でトライバル、原始的な音の祭典のような曲も作ってしまうマエストロの新たな一面を、ぜひこの機会に知ってください!
現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲(21〜30)
オラトリオ「日蓮聖人」黛敏郎
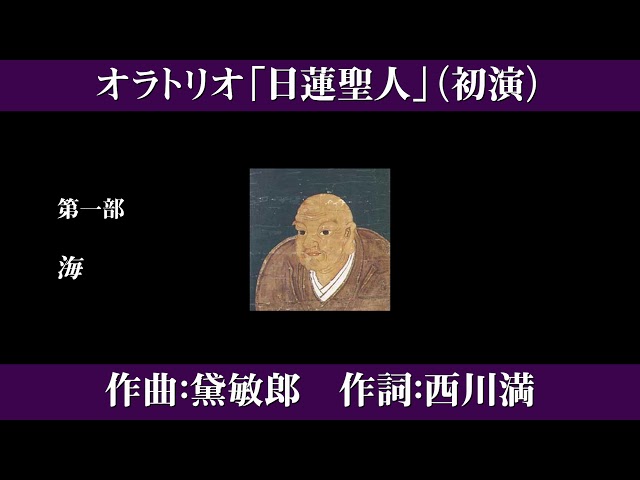
戦後の日本音楽界を代表する作曲家として知られる黛敏郎さん。
現代音楽のみならず映画音楽の分野でも活躍した音楽家です。
黛さんの作品のなかでも、仏教的世界観を西洋のオラトリオ形式で表現したこの大作は、まさに圧巻の一言に尽きます。
日蓮の生涯を「海・花・光・雪・山」の5部構成で描き、日本語の朗読と重厚な合唱、シンフォニックなオーケストラが一体となって壮大な物語を紡ぎだすのですね。
終盤、題目を反復しながら高揚していくクライマックスは、聴く者の魂を揺さぶるでしょう。
本作は、日蓮聖人第七百遠忌の記念事業として1982年4月に初演された作品です。
西洋音楽の枠組みに日本の精神性を融合させた、唯一無二の音楽体験を求める方にぜひ聴いていただきたい名曲です。