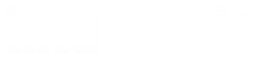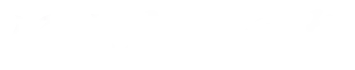民謡の人気曲ランキング
懐かしのあのメロディ、歌い継がれる、ふるさとの心、古今東西のさまざまな民謡をリサーチしました!
この記事ではこれまでに当サイトに寄せられた音楽ファンの確かな声をもとに人気の曲をピックアップ。
そのなかでもとくに評判だったものをランキング形式でご紹介いたします。
どうぞご覧ください。
童歌や子守唄などの子供向けのもの、労働歌、行事の歌などもリサーチいたしました。
近年では「民謡クルセイダーズ」や「俚謡山脈」など民謡の新しい聴き方が新たなファン層を呼んでいる。
- カラオケで歌いたい民謡。みんなで楽しめる名曲、人気曲
- 【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集
- ご高齢者向けの人気曲ランキング
- 童謡の人気曲ランキング【2026】
- 長崎の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 沖縄の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 幼児向けの人気曲ランキング
- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 川をテーマにした童謡・唱歌・わらべうた。懐かしい水辺の名曲たち
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 【空の童謡・唱歌】時代をこえて愛され続けるこどもの歌
民謡の人気曲ランキング(41〜50)
アイスクリームのうた作詞:さとうよしみ/作曲:服部公一50位

『アイスクリームのうた』は、作詞:さとうよしみさん、作曲:服部公一さんの日本の童謡です。
もともとは1960年、ラジオ番組の『ABC子供の歌』のために書き下ろされた曲で、1962年にはNHKの『みんなのうた』で放送され、有名になりました。
アイスクリームの歌だけあって、アイスクリームのコマーシャルソングとして使われたこともあります。
民謡の人気曲ランキング(51〜60)
手のひらを太陽に作詞:やなせたかし/作曲:いずみたく51位

やなせたかしさんといずみたくさんのコンビによって生まれたこの童謡は、1962年にNHK『みんなのうた』で初めて放送されました。
ミミズやアメンボといった小さな生き物も同じように生きている仲間なんだと歌う温かな歌詞が印象的です。
やなせさんが自分の手を太陽にかざして血のめぐりを感じ、そこから命の尊さを見つめ直した経験が歌詞に込められています。
1965年にはボニージャックスのシングル盤が発売され、紅白歌合戦でも歌われました。
学校行事や地域のイベントで歌うと自然とみんなの心が一つになるような温もりを感じられます。
北風小僧の寒太郎作詞:井出隆夫/作曲:福田和禾子52位

テレビドラマ『木枯し紋次郎』をヒントにして、子供向けの演歌をというコンセプトで作られたのがこちらの曲だそうです。
1974年にみんなのうたで発表された曲で、当時は堺正章さんが、1982年には北島三郎さんが歌ったリメイク版が発表されました。
ほっぺたが赤くて色白の寒太郎のかわいいアニメーションにいやされた人たちも多かったのではないでしょうか。
小学校の音楽の教科書にも何度か掲載され、幅広い世代に愛されている冬の曲といえます。
雪のこぼうず作詞:村山寿子/作曲:不詳53位

キングレコードから発売されている『ゆったり どうよう60』にも収録されている雪関連の歌。
もともとは外国の曲で、さまざまな歌詞がつけられて歌われています。
歌詞の内容は「雪のこぼうず」が空からやって来て、池に落ちて、水になって消えていったとするもの。
妖精なのかはたまた概念的な存在なのか、「雪のこぼうずって何なんだろうね?」とみんなで話をしながら歌うのも楽しそうですね。
1番、2番、3番とポーズを変えて歌えるのもオススメポイントです。
とんぼのめがね作詞:額賀誠志/作曲:平井康三郎54位

秋になるとたくさん見かけるトンボ。
そんなトンボのかわいいメガネのお話が歌われたのが、こちらの『とんぼのめがね』です。
トンボがメガネをかけているという時点で、とてもかわいらしい光景が感じられますね。
そのトンボがかけているメガネが水色や赤色だったり、光ったりしているときもあるけど、それはどうしてなのかな?という疑問から、かわいらしい想像が展開されていきます。
空を飛ぶトンボを見て、あのトンボはどんなメガネをしているんだろ、こっちのトンボは?と想像しながらこの歌を歌ってみるのもオススメですよ!
そーめんつるつる55位
夏にぴったりな手遊びといえば『そーめんつるつる』。
夏になると一度は食べるそうめんの手遊び歌です。
手をぐるぐる回したり、そうめんを食べる動きをマネしたり、とても単純な振り付けなので小さな子でも遊べますよ。
そうめんの種類も歌詞に出てきて、種類によって振り付けの動きもかわります。
そうめんを食べたことがない子も、この手遊びでそうめんを知って「食べたい!」と興味を持つのではないでしょうか?
夏の手遊びを探しているのならオススメです!
うれしいひなまつり作詞:山野三郎(サトウハチロー)/作曲:河村直則(河村光陽)56位
春先のイベントと言えばひな祭り、ということでこちらの童謡をぜひ!
詩人のサトウハチローさん、作曲家河村直則さんによる『うれしいひなまつり』は1936年に楽曲として発表され、現在にいたるまで広く親しまれています。
「ひな祭り」と聞くと真っ先にこの歌が思い浮かんじゃいますよね!
それぐらい、日本人の心に根付いた作品だと思います。
さまざまな歌手がカバーしている曲でもあるので、自分の好みのバージョンを探す楽しみ方もできるかも>