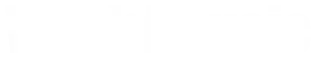華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集
歌い手の身体そのものが楽器になるのが「声楽」。
あまりちゃんと聴いたことはないという人も多いのではないでしょうか?
声楽曲にはオペラや歌曲などさまざまなものがありますが、初心者にもぜひぜひおすすめしたい有名な曲を集めました。
人の体からこんなに豊かな表現が生まれるのか!と、感動することまちがいないですよ。
メロディだけでなく歌詞やストーリーを意識しながら聴いてみるのもおすすめです。
- 【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌
- 華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集
- 【2026】ミュージカルの名曲。最新作から往年の名作まで紹介!
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- 美しい高音が心地いい!ハイトーンボイスを堪能できる洋楽の名曲。
- ミュージカル初心者におすすめの名曲
- 【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 女性が好きな洋楽の歌。世界の名曲、人気曲
- シャンソンの名曲。おすすめの人気曲
- 美しくきれいな洋楽。おすすめの名曲まとめ
- 有名なドイツ民謡|日本のアノ曲がドイツ民謡だった!?
- 【コラール】コラールの名曲。おすすめの人気曲
- 【クラシック】ワルツの名曲。おすすめの人気曲
華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集(21〜30)
歌劇「ペール・ギュント」より「ソルヴェイグの歌」Edvard Hagerup Grieg

世界最高峰の劇作家ヘンリック・イプセンが1867年に書いた名作「ペール・ギュント」に劇音楽を付けて上演するためにノルウェーの国民楽派を代表する作曲家のエドヴァルド・グリーグに依頼して1876年2月にオスロの王立劇場で初演が行われたもので、美し叙情的な「ソルヴェイグの歌」は、その劇中で歌われ有名になった曲です。
歌劇「ホフマン物語」より「森の小鳥たちは憧れを歌う」Jacques Offenbach

ルチアーナ・セッラはイタリア・ジェノヴァ生まれのコロラトゥーラ・ソプラノ歌手です。
装飾的な高音を正確に歌い上げる高い技術と華やかな美声が持ち味。
この曲では機械仕掛けの人形・オリンピアに扮してコミカルに、可憐に歌い上げます。
サムソン HWV.57 より「万軍の主よ、帰りたまえ」Georg Friedrich Händel

バロック音楽の巨匠、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによるオラトリオの名作『サムソン』。
その劇中で歌われるこの作品は、絶望の淵にいる英雄と、英雄を想う民の切実な祈りを描いています。
そんな本作の魅力は、アルト独唱による内省的な祈りが、やがて荘厳な合唱へと発展していく部分。
神への深い嘆願と、苦難のなかで希望を求める人々の想いを見事に表現した楽曲です。
1743年の初演時から高い評価を得ており、名歌手キャスリーン・フェリアーが残した1952年10月の録音は歴史的名盤として知られています。
荘厳な物語を持つクラシック音楽が好きな方はぜひ!
主をほめ讃えよWolfgang Amadeus Mozart

静寂さの中に美しいメロディーが流れ心いやされる声楽曲が「Laudate Dominum:ラウダーテ・ドミヌム」です。
モーツァルト作曲で「ヴェスペレ Vesperae solennes de confessore K.339」証聖者のための晩課の第5曲です。
約束の地~The Promised Land~植松伸夫

讃美歌を思わせる神聖なコーラスが印象的な楽曲です。
作曲を担当したのはゲーム音楽の巨匠として世界的に知られる植松伸夫さんで、荘厳なコラール風の作品に仕上げられています。
ラテン語で歌われる詞には、なぜ人は罪を背負い苦しむのか、そして命はどこへ還るのかといった根源的な問いと、避けられない運命への哀しみが込められているようです。
この楽曲は、2005年9月発売のサウンドトラック『FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN』に収録。
映像作品の挿入曲として、登場人物たちが天へと昇っていく感動的な場面で使用されました。
壮大な物語の世界に静かに浸りたい夜におすすめです。
アヴェ・マリアFranz Peter Schubert

『アヴェ・マリア』。
たくさんの作曲家の作品があります。
シューベルトの『アヴェ・マリア』、も有名な作品です。
きれいなピアノのイントロがとても美しく、そこから優しくのびやかな歌声に魅了されますね。
心がおだやかになる声楽の名曲といえるでしょう。
教会で聴きたいすばらしい作品です。
荒野の果てに

西部劇映画を彷彿とさせる、荘厳で哀愁に満ちたサウンドが魅力的なナンバーです。
歌手の山下雄三さんを広く知らしめた楽曲ですね。
1972年11月にテレビ時代劇『必殺仕掛人』の主題歌として公開された作品で、アルバム『歌、その出発』に収録されています。
作詞家が描いた荒涼とした世界で、非情な宿命を背負いながらも信念を貫く主人公の深い精神性が、山下さんの情感が豊かな歌声によって表現されていますよね。
静寂からクライマックスへと駆け上がるドラマティックな曲構成は圧巻です。
物語性の高い音楽にじっくりと浸りたい人に聴いてほしい、魂を揺さぶる一曲です。