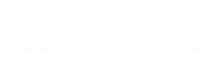小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
夏休みの自由研究の工作なら、男の子の興味をグッとつかむアイデアを選びたいですよね。
そこでこの記事では、ダンボールでガチャガチャを作ったり、本格的なリール付き釣り道具を作ったり、エアホッケーやバスケットゲームを手作りしたり…と、男の子が夢中になれる工作のアイデアをご紹介します。
どれも見た目は本格的なのに、身近な材料で作れるものばかり。
お気に入りの作品で、友達と一緒に遊ぶ楽しい夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか?
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 【男の子向け】ペットボトルキャップを使った工作アイデア
- 簡単だけどすごい工作。小学生が作りたくなる工作アイデア
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- ストローを使った楽しい工作
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 小学生の低学年にオススメ!身近な材料で作るペットボトルの工作アイデア集
- ダンボール工作で作るおもちゃ!作って遊べる本格アイデアも
- 親子で楽しめる工作。子供の暇つぶしにおすすめの工作アイデア
- 紙コップ工作で小学生が夢中になる!楽しい作品のアイデア集
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 段ボールで作れる!かっこいい刀&剣
小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア(81〜90)
遊びながら貯まる貯金箱
ダイソーの3段引き出しケースを使って、遊びながら楽しくお金が貯まる貯金箱を夏休みに作ってみましょう。
2段目と3段目のケースを逆さにして、まっすぐな面が手前にくるように組み替えます。
次に、プラダン(プラスチック段ボール)を好きな形にカットして、引き出しの外側に貼り付け、見た目にもこだわったデザインに仕上げましょう。
内部には両面テープを貼ることでコインが途中で止まり、ゆっくりと落ちていくように工夫します。
自分で作った貯金箱なら、お金を貯める習慣も楽しく身につけられます。
発想と工夫で日常を変えることができる、実用性も兼ね備えたユニークなアイデアです。
電気スタンド
@gakky_07 夏休みの自由工作にどう❓#夏休みの工作#夏休み#電気スタンド
♬ 楽しい磯野家/サザエさん[カバー] – サウンドワークス
マグネットで固定できるタイプのLEDライトを使った電気スタンド作りのアイデアです。
スタンドはすべて木製で、アームの部分は角度を調整できるように可動式になっていますね。
まずはどんな大きさにしたいのか、どんな構造にしたいのかを考え、設計図を書いてみましょう。
設計図ができたら必要な木材の長さや数を把握し、木材を調達してください。
最近では100円ショップでもちょっとした木材が売っているので、それらを使ってもいいかもしれませんね。
ニスやオイルでナチュラルな仕上げにするのか、ペンキを使って好きな色に塗るのかなど、どんな仕上げにするのか選べるのも木工の楽しさですので、ぜひいろいろなパターンを考えてみてください。
バードコール作り

自然観察が好きな子供にぴったりの工作として、バードコール作りをオススメします。
手で持てるサイズの木の枝を用意し、中心に小さな穴を開けましょう。
そこにアイナットという金属の部品をねじ込み、木と金属がこすれ合うように動かすと鳥のさえずりのような音が鳴ります。
この音に本物の鳥が反応することもあり、作った後に公園などで実際に試してみるのもポイント。
音の大きさや高さは木の種類や穴の深さによって変化するため、音の違いを記録しながら工夫を重ねることで自由研究としての完成度も高まります。
自然と触れ合いながら音のしくみにも興味を持てる、体験型のアイデアです。
世界に1つのトイクロック

時計のムーブメントと板を用意して時計を作り、そこにいろいろなおもちゃを貼り付けていくというアイデアです。
時計のムーブメントは100円ショップやハンドメイドショップで手に入り、時計の盤面となる板はホームセンターで購入しましょう。
まずは板に対角線を引いて中心点を出し、ムーブメントを取り付ける穴を空ける目印を付けます。
次に分度器を使って時計の数字を書く位置を決めましょう。
そして穴を空けたり色を塗ったりしたら、いよいよ盤面のデコレーションです。
グルーガンを使っておもちゃを好きなように貼り付けていってくださいね。
最後に時計のムーブメントを穴に固定すれば完成です。
あなたのお好きなおもちゃをセンスよく貼り付けて、ステキな時計を作ってくださいね!
割り箸コースター

木の温もりが感じられる、割り箸コースターを紹介します。
割り箸、接着剤、サンディングシーラー、ニス、ハケを準備して作っていきましょう。
土台の板の周りに割り箸を貼り合わせていきましょう。
割り箸はカッターで切り目を入れてから割るときれいにに割ることができますよ。
先端はやすりで少しやすると丸みが出ます。
外側から内側に向かって割り箸を貼り合わせていきましょう。
割り箸の大きさはちお右折しながら貼り合わせていきましょうね。
ハケでニスを塗って乾燥させたら完成です。
ぜひ作ってみてくださいね。
小物入れ

かわいくて便利な小物入れ入れを紹介します。
ウッドボックス、カッティングボード、丸い棒、グルーガン、ノコギリを準備して作っていきましょう。
グルーガンを使ってウッドボックスにカッティングボードを左右に貼り合わせていきましょう。
丸い棒を適切な長さに切ったらやすりで先端を磨いて穴に通してグルーガンで固定します。
作り方もシンプルで作りやすのでぜひ作ってみてくださいね。
上から色を塗ってオリジナル感を出したりするのもオススメです。
小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア(91〜100)
昆虫インテリア

昆虫標本をインテリア風に仕上げようというアイデアです。
標本といえば箱に入ったものをイメージすると思いますが、今回紹介するのはビンに入ったものです。
用意するのは、コルクでフタができるビンとアクリルの板と昆虫の標本です。
作り方はシンプルで、まずはアクリル板をビンの中に収まるサイズにカットしましょう。
次にコルクのフタに切り込みを入れ、そこにカットしたアクリル板を挟んで接着剤で固定します。
最後に昆虫の標本をアクリル板に接着し、フタをすれば完成です。
透明のアクリル板を使うことで昆虫がビンの中に浮いているように見え、とってもオシャレな雰囲気に仕上がりますね。