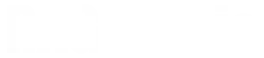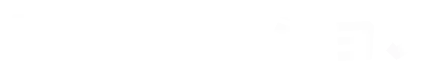【高齢者向け】夏にまつわるクイズ。レクで盛り上がる面白問題まとめ
夏の暑い日のレクリエーションに、室内で快適に過ごせるクイズはいかがでしょうか?
近年の日本は暑さが年々増していますよね。
クイズは体を動かさずに脳トレができるため、真夏の高齢者施設でのレクリエーションにオススメですよ。
夏がお題のテーマになっているので、季節を感じたり過去を思いだすきっかけになるかもしれません。
高齢者の方にとって過去を振り返り話すことは、心の安定につながり認知機能にも効果的。
また、話すことで周りの方とのコミュニケーションが生まれやすくなりますよ。
クイズで脳トレをしながら、楽しい夏のひとときを過ごしてくださいね!
- 【高齢者向け】夏祭りの雑学クイズ&豆知識問題。知識が増える楽しいクイズNEW!
- 【高齢者向け】夏に挑戦しよう!海の雑学クイズ&豆知識問題まとめNEW!
- 【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がるNEW!
- 【高齢者向け】8月の健康ネタ。暑い夏を楽しく快適に過ごすヒントNEW!
- 【高齢者向け】脳トレ!思い出しクイズ集!
- 【高齢者向け】楽しく脳トレ!都道府県クイズ
- 【高齢者向け】知識が増える!楽しい雑学クイズ
- 【高齢者向け】盛り上がる!連想ゲームのアイデア
- 【高齢者向け】言葉遊びゲームで盛り上がろう!しりとり言葉遊びのアイデアまとめ
- 【高齢者の方向け】盛り上がる!8月に雑学と豆知識クイズ
- 高齢者の方が楽しめる8月のクイズ!
- 【高齢者向け】面白くてためになる!雑学やクイズをご紹介
- 【高齢者向け】脳の活性化につながる楽しいなぞなぞ
- 【高齢者の方向け】9月のおもしい雑学と豆知識クイズで盛り上がろう!
【高齢者向け】夏にまつわるクイズ。レクで盛り上がる面白問題まとめ(41〜60)
「カブトムシ」のツノは何本以上でしょうか?
夏を象徴する昆虫といえばカブトムシ、どのようにして捕獲するのかを試行錯誤した人も多いかと思います。
特にオスのカブトムシは、強さを象徴するような立派なツノを持っていて、少年からするとテンションが上がりますよね。
メスにはツノがなく、オスはツノがあることも特徴ですが、ツノの本数について考えてみましょう。
1本の大きなツノというイメージも強いかと思いますが、ツノは「2本」あり、上下にあるものの下のツノが象徴的な大きなツノです。
2本以上のツノを持つ種類も存在しているので、そちらをあわせて知るのもおもしろそうですね。
「ラジオ体操」はどこから来た文化?
夏休みの行事といえば、朝の早起きとラジオ体操も欠かせない風物詩ではないでしょうか。
ラジオ体操は夏休みにしかしなかった人、それ以外でもおこなう機会がある人など、向き合い方もさまざまなですよね。
そんな手軽に体を動かせるラジオ体操の歴史について知れば、より前向きに体操に向き合えるのではないでしょうか。
ラジオ体操は「アメリカ」のメトロポリタン生命保険会社が、保険加入者の健康促進を目的に1925年にはじめたものとされ、そこなら日本に伝わってきました。
1927年に日本に渡った体操が、どのように進化してきたかも、あわせて知っていきましょう。
お盆に位牌やお供え物を飾る棚を「盆棚」といいます。もう一つの呼び名は何でしょうか?
ご先祖様をお迎えして供養するお盆、お供え物をはじめとしたさまざまな飾り付けも特徴ですよね。
そんなお盆に欠かせないお供え物を飾る棚は「盆棚」と呼ばれますが、そのほかにはなんと呼ばれているでしょうか?
答えは「精霊棚」、お盆にちなんだ飾り付けや行事に「精霊」とついていることからもイメージしやすいかと思います。
これらのことからご先祖様のことを「精霊」と呼んでいることも感じられ、ご先祖様が神聖なものだと強く感じられるのではないでしょうか。
別名「徹夜踊り」とも呼ばれる盆踊りの「郡上おどり」は何県で行われているでしょうか?
ご先祖様をおむかえするお盆には、お祭りが開催されることもあり、その際には盆踊りが披露される場合が多いかと思います。
そんな盆踊りの中でも特殊な、「徹夜踊り」とも呼ばれる「郡上おどり」は何県で行われているでしょうか?
答えは「岐阜県」で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている、伝統的な盆踊りです。
夜から翌朝にかけて踊るつづけるのが大きな特徴で、ご先祖様への供養と娯楽の要素をあわせもった盆踊りだと言われています。
日本で一番うちわを作っている都道府県はどこ?
暑い夏を快適に過ごすために、扇子やうちわで涼しい風を起こす様子も定番の光景ですよね。
そんな当たり前に使っているうちわについて、知識を深めていくのはいかがでしょうか。
伝統工芸品として、さまざまな地域で作られているうちわですが、特に生産量が多いのは、「香川県」の「丸亀うちわ」と言われています。
経済産業大臣指定の伝統工芸品として、全国うちわ生産量の9割を占めているそうです。
各地域のうちわの違い、歴史について調べてみるのもおもしろそうですね。