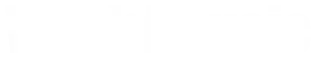【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌
世界中で愛されている賛美歌と聖歌。
キリスト教の神をたたえる歌として知られている賛美歌と聖歌ですが、日本では仏教徒が多いため知名度は決して高くありません。
優れた楽曲も多いのですが、探しづらい部分が難点ですね。
今回はそんな賛美歌と聖歌の有名な作品をピックアップしてみました。
作品が作られた経緯や、歌詞の意味なども細かく解説しているので、賛美歌と聖歌の知識がない方でも楽しめる内容です。
日々のストレスで疲弊しきった心を賛美歌と聖歌で癒やしてみてはいかがでしょうか?
それではごゆっくりとお楽しみください!
- 有名なドイツ民謡|日本のアノ曲がドイツ民謡だった!?
- 日本のゴスペル。おすすめのゴスペルライクな邦楽
- 世界のゴスペル・シンガー。ゴスペル・ミュージックの名曲、おすすめの人気曲
- 【アイルランド民謡】意外と身近な民族音楽の名曲・定番曲
- ゴスペル初心者のための練習曲
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- 華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集
- 誰でも知ってる洋楽。どこかで聴いたことがある名曲まとめ
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- 【コラール】コラールの名曲。おすすめの人気曲
- 【洋楽】ブルーグラスの名曲。おススメの人気曲・代表曲
- 洋楽の日曜日の歌。世界の名曲、人気曲
- イギリスのソプラノユニット、Liberaの人気曲ランキング
【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌(21〜30)
讃美歌第二編一番「こころを高くあげよう」ヘンリー・モンテギュー・バトラー

イギリスの学者であり聖職者であるヘンリー・モンテギュー・バトラーが1881年に作詞した作品です。
賛美歌にふさわしく神への信頼と献身を表現しており、心を高く上げて神に向かうことの大切さを歌っています。
曲は1916年にウォルター・グレートレックスが作曲した「ウッドランド」に乗せて歌われることが多いそうです。
学校の歌としても広く採用されており、若い世代にも親しまれています。
バトラーはハロー校の校長やケンブリッジ大学トリニティ・カレッジのマスターを務めた方で、教育者としての経験が歌詞にも反映されているのかもしれませんね。
心が疲れたときに聴くと、勇気をもらえそうな一曲です。
荒野の果てに

西部劇映画を彷彿とさせる、荘厳で哀愁に満ちたサウンドが魅力的なナンバーです。
歌手の山下雄三さんを広く知らしめた楽曲ですね。
1972年11月にテレビ時代劇『必殺仕掛人』の主題歌として公開された作品で、アルバム『歌、その出発』に収録されています。
作詞家が描いた荒涼とした世界で、非情な宿命を背負いながらも信念を貫く主人公の深い精神性が、山下さんの情感が豊かな歌声によって表現されていますよね。
静寂からクライマックスへと駆け上がるドラマティックな曲構成は圧巻です。
物語性の高い音楽にじっくりと浸りたい人に聴いてほしい、魂を揺さぶる一曲です。
Guide Me Oh Thou Great RedeemerCharlotte Church

12歳にして天才歌手としてデビューしたウェールズの歌姫である、シャルロット・チャーチさんの名曲『Guide Me Oh Thou Great Redeemer』。
キリスト教信者が信仰を続ける大きな理由のひとつは、神様に導いてもらえるからです。
日々生活する中で私たちは常に選択をしながら生きています。
その選択の積み重なりがその人の人生になります。
もちろん、選択する上で迷ったり、苦しんだりすることもあり、正しい道がわからなくなることもあります。
そんな時に、私たちを導いてくれる神様をたたえた1曲です。
讃美歌第312番「いつくしみ深き」Charles Crozat Converse

弁護士としても活動したチャールズ・クロザット・コンヴァースによる、世界中で親しまれている賛美歌です。
この楽曲の原詩は、婚約者を二度も失うという深い悲しみを経験した人物によって書かれたそうです。
どんな悩みも分かち合ってくれる友への祈りがあふれているかのような、温かく包み込むメロディーは心を穏やかにしてくれますね。
本作は1868年頃に作られ、作曲したコンヴァースは1895年に名誉法学博士の学位を授与されています。
静かに自分と向き合いたいときや、安らかな気持ちで眠りにつきたい夜に聴くのにオススメな一曲です。
オラトリオ《マカベウスのユダ》第3幕 『見よ、勇者は帰る』Georg Friedrich Händel

「表彰式の曲」と聴けば、多くの方がこのメロディを思い浮かべるのではないでしょうか?
運動会をはじめ、さまざまな場面で親しまれているこの有名な曲は、バロック音楽の巨匠ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによって1740年代に書かれました。
実はこの楽曲、オラトリオ『Judas Maccabaeus』の中で、戦いに勝利した英雄を民衆が歓喜とともに迎える場面で演奏されます。
表彰のシーンにぴったりな背景を持つ楽曲な上、その堂々とした風格が感じられる旋律は、ベートーヴェンも主題とした変奏曲を残すほど。
もともとは別の作品のために書かれたものを、ヘンデル自らが自信作として本作に組み込んだと伝えられています。
勝利の栄光を高らかに歌い上げる、まさに凱歌と呼ぶにふさわしい一曲ですね。
讃美歌373番「ナルドの壷」Edwin Pond Parker

イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事をしようとしていた時に、ひとりの女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてあるつぼを持ってきて壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた、という『マルコによる福音書』に記載されている一節が基となっています。
彼女は、主イエスへの感謝と愛とを表すためには、その他のどんな物よりも大切なナルド油を与えるのがふさわしいと思い、このような行動をしました。
自分にとって大切なものを人のためにささげる奉仕の業を意味しています。
わがたましいをCharles Wesley
イングランド国教会における信仰覚醒運動であるメソジスト運動の指導者であったチャールズ・ウェスリーを代表する作品です。
彼は生涯にわたって多くの讃美歌を作りましたが、この讃美歌は英国の中で最も有名な讃美歌の一つです。
チャールズ・ウェスレーの回心後まもなく作られ、1740年に「試練の時に」と題して発表されました。
メソジスト運動に対する迫害に危険の中で作られたという説があり、神に身を守ることを求める讃美歌です。