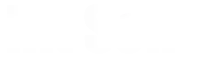1980年代の邦楽ヒット曲、今でも耳に残る懐かしの名曲集
1980年代といえば、今なお人気が衰えることがない名曲がたくさん登場した時期ですよね!
現在活躍しているミュージシャンに影響を与えたアーティストなどもたくさん活動した時代で、ミリオンセラーが爆発的に生まれる1990年代を前にしたJ-POP創世期といえるのではないでしょうか?
この記事では、そんな名曲ぞろいの80年代ヒット曲の中から、とくにオススメの曲をたっぷりと紹介していきますね!
当時の思い出がよみがえるような、懐かしいヒット曲たちをぜひお楽しみください。
- 80年代懐かしの邦楽ポップスの名曲・ヒット曲
- 80年代の歌謡曲の名曲・ヒット曲
- 【懐かしの名曲】ヒットした80年代の邦楽ラブソング
- 1980年代に活躍したバンドの名曲&ヒットソング特集
- 昭和のかっこいい曲。色気や情熱、渋さが光る昭和の名曲
- 80年代のCMソング。これまでCMで使用された80年代邦楽まとめ
- 90年代懐かしの邦楽ポップスの名曲・ヒット曲
- 80年代懐かしの邦楽アイドルの名曲・ヒット曲
- 人気の懐メロ・名曲ランキング【80年代邦楽ランキング】
- 古き良き時代を感じさせる。現代でも愛されている昭和の感動ソング
- 80年代の男性シンガーソングライター・人気曲ランキング【2026】
- 1980年代にヒットした失恋ソング。邦楽の名曲、人気曲
- 懐かしすぎて新しい?高度経済成長期の日本を彩った昭和レトロの名曲
1980年代の邦楽ヒット曲、今でも耳に残る懐かしの名曲集(71〜80)
キスしてほしいTHE BLUE HEARTS

1987年11月に発売された2ndシングル曲です。
プロ野球中日ドラゴンズ藤井淳志選手が2009年から入場曲に使用していることでも有名です。
たくさんのバンドが出てきた時代の中でもとてもすてきなバンドでした。
め組のひとRATS&STAR

日本ではじめてドゥーワップスタイルに取り組んだ音楽ユニット、シャネルズからラッツ&スターに改名して1枚目のシングル曲です。
当時は大ヒットを記録し、その斬新なヴィジュアルから今でも語り継がれる伝説的グループ。
初期はなかなか日本では受け入れられなかったというエピソードもあります。
それになぜか、顔を黒く塗る行為=差別としてメディアに差別され、批評を受けたこともありました。
しかし、初期から山下達郎さんは彼らを評価していたそうです。
ギンギラギンにさりげなく近藤真彦

1981年に発売された、80年代を象徴するポップスの名曲。
派手な演出と近藤真彦さんのカリスマ性あふれるパフォーマンスで、多くのファンを魅了しました。
ハウス食品「ククレカレー」のCMソングにも起用されて、大ヒットを記録。
当時の若者文化やファッション、恋愛観を色濃く反映した歌詞が印象的です。
さりげなく生きる青年の姿を描いた本作は、自分らしさを大切にしながらも周囲と調和したいという思いが込められています。
派手すぎず、でも確かな存在感を放ちたい。
そんな気分のときにぴったりの1曲ですね。
1980年代の邦楽ヒット曲、今でも耳に残る懐かしの名曲集(81〜90)
TRUTHT-SQUARE

『TRUTH』も多くの世代に親しまれている名曲です。
こちらはフュージョンバンド、T-SQUAREが1987年にリリースした曲で、F1レース中継のテーマソングとしても親しまれています。
また、スピード感がありつつスタイリッシュなサウンドから、さまざまな作品のBGMに使用されています。
実はリミックスバージョンやセルフカバーバージョンなど、複数のバージョンがあるんですよ。
いずれも素晴らしいので、それぞれ聴き比べてみましょう!
RASPBERRY DREAMREBECCA

この『RASPBERRY DREAM』は1986年に発売された、REBECCAの5枚目のシングルです。
REBECCAといえば今でも人気な『フレンズ』が有名ですが、その他にもいい曲が多くあります。
この『RASPBERRY DREAM』もどこか懐かしいメロディで切なくなります。
淋しい熱帯魚Wink

『淋しい熱帯魚』は1989年7月にリリースされたWinkのシングルで、松下電器産業のCMソングに使われています。
オリコンチャートでは初登場で1位にランクインし、全日本有線放送大賞と日本レコード大賞を受賞したヒット曲です。
YES-NOオフコース

フォークからロックバンドの時代。
1980年6月にリリースされた曲。
小田和正の透き通った声。
当時の音源でもそれが全面に押し出されています。
夏の海の景色が出てくるようなそんな壮大なサウンドに仕上がっています。
Charaや稲垣潤一などさまざまなアーティストにもカバーされており、今なお歌われ続けられている名曲。
カラオケで歌うと……少しキーが高い!?でも歌いたくなるすてきなメロディです。