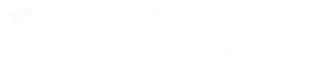【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び
子供たちが喜ぶ屋外での遊びやレクリエーションゲームを紹介します!
小さい頃は公園でブランコに乗ったりすべり台をすべっていれば満足していた子供たちも、成長するにしたがってルールがあるゲームや走ったり飛び跳ねたり、思いきり体を動かす遊びをしたがるようになりますよね!
「子供が喜ぶ外遊びってなんだろう?」そんなときはぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
お父さんやお母さんが子供だった頃に遊んだ、懐かしい遊びありますよ!
- 屋外レクの人気ランキング
- 【親子レク】親子で楽しむレクリエーション、ゲーム。運動会にも
- 道具なしで楽しく遊べるオススメの外遊び
- 小学校低学年におすすめの野外・アウトドアのゲーム・レクリエーション
- 子供におすすめの野外・アウトドアのゲーム・レクリエーション
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 大人数の外遊び。盛り上がる子どもの遊び
- 子供向けのレクリエーション人気ランキング
- アウトドアで盛り上がる楽しいレクリエーションゲーム
- 子供の頃に流行った懐かしい遊び
- 楽しい冬の遊び。子供が楽しめるレクリエーション
- 【子供とつくる】手作り外遊びのおもちゃ特集
- 【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び(1〜10)
なわとび

これもお外で遊ぶのに最適な「なわとび」。
学校の授業などでもよく取り上げられると思います。
縄の両端を持ち、それを回して飛ぶといったシンプルなものですが、体全身の筋肉を使えるかなり有効な運動です。
そして普通の跳び方に慣れてきたら「あやとび」や「二重とび」など、どんどんワザを増やしてみるといいと思います。
なわとび板を使えば普通ではできないびっくりするようなワザもできますので、上達にあわせてどんどん練習してみてください!
じゃんけん列車

お年寄りから小さな子供までみんなで遊べるレクリエーションです。
このレクリエーションをしたあとはみんな仲良くなっているので、新入生の歓迎会や社員研修のゲームとしても使えそうですね。
ルールは簡単!じゃんけんをして負けた人は勝った人の後ろに電車のようにつながります。
それを続けていくといつの間にか長い列車になっていて、最後には長い1本の電車になるんです。
人が何十人もつながった景色はとてもシュールでなぜか笑えてきますよ。
学校の文化祭・体育祭のプログラムにしてもきっと盛り上がります!
だるまさんがころんだ

きっと誰もが子供の頃にやったことがある遊び、「だるまさんがころんだ」。
鬼が木や壁につき「だるまさんがころんだ」とコールしている間に子は鬼に近づきます。
鬼が振り返った時に少しでも動いている人はアウト、鬼につかまってしまいます。
残った子は鬼に近づき、鬼と子のつないでいる手を離し、その場からダッシュで逃げます。
鬼が「ストップ!」と言ったところで止まり、鬼が決められた歩数で移動、捕まった人が次の鬼になります。
止まる時のポーズを工夫するなど、オリジナルのルールなど加えてみましょう!
【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び(11〜20)
砂遊び

公園の砂場を使う砂遊びは、古くから現在まで外遊びの定番として親しまれていますよね。
みんなで協力してお城や山を作ったり、オリジナルの泥団子を作ってお友達と勝負したりなど、子供の想像力や手の感覚を鍛えるためにも有効な遊びと言えるのではないでしょうか。
近年では砂場で遊べる道具も進化し、砂や土を方に入れてケーキなども作れるため、おままごととしても遊びを広げられますよ。
楽しみ方を幅広く選択できるため、家でゲームばかりになりがちな子供にもおすすめの外遊びです。
缶けり

昔ながらのお外遊びの定番「缶けり」。
こちらもルールさえ把握できれば楽しく誰でも遊べます。
こちらも鬼ごっこのように鬼を決めるのですが、タッチではなく目視と「〇〇さん見つけた」という掛け声によってプレイヤーを捕まえていきます。
そして何より、缶けりというだけあって、その掛け声とともに缶を踏まなければいけません。
その缶から鬼が離れているすきにプレイヤーは鬼に見つかることなく、もしくは見つかっても鬼が缶を踏む前にその缶を遠くにけりとばせば勝ちです。
鬼もプレイヤーもかなりのドキドキ感を持って遊べるので、集中力がグッと深まること間違いなしの遊びです。
かげふみ

自然を使ったお外遊び「かげふみ」。
普段あまり意識することのない「影」を使った遊びです。
夕方ならば西日が強く出る時期ですので、この遊びにちょうどいいかもしれないですね。
「かげふみ」は自分の影を踏まれないように相手から逃げ、その間に相手の影を踏んでゆきます。
影は木陰や物陰などで見えなくなるので、相手からうまく逃げるためには知恵を使って考えることが大切です。
自分の影を気にしすぎて後ろ向きで走ると危ないので、踏まれそうなときは別の影に隠れたり、前を向いて全力で逃げましょう!
けんけんぱ

コンクリートの住宅街などでもできる「けんけんぱ」。
このリズミカルな語感「けん」は片足での着地、「ぱ」は両足での着地を意味します。
砂なら木の枝などで、コンクリートならチョークで「けん」か「ぱ」の丸をかいてそれを飛んでいきます。
ただそれを飛ぶだけではなくおもしろいリズム感があり、その丸の上を飛ぶ子供たちにあわせ「けんけんぱ」と声を出します。
慣れてきたら長いコースや丸の距離感などを変えたりして遊びましょう!