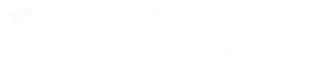【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び
子供たちが喜ぶ屋外での遊びやレクリエーションゲームを紹介します!
小さい頃は公園でブランコに乗ったりすべり台をすべっていれば満足していた子供たちも、成長するにしたがってルールがあるゲームや走ったり飛び跳ねたり、思いきり体を動かす遊びをしたがるようになりますよね!
「子供が喜ぶ外遊びってなんだろう?」そんなときはぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
お父さんやお母さんが子供だった頃に遊んだ、懐かしい遊びありますよ!
- 屋外レクの人気ランキング
- 【親子レク】親子で楽しむレクリエーション、ゲーム。運動会にも
- 道具なしで楽しく遊べるオススメの外遊び
- 小学校低学年におすすめの野外・アウトドアのゲーム・レクリエーション
- 子供におすすめの野外・アウトドアのゲーム・レクリエーション
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 大人数の外遊び。盛り上がる子どもの遊び
- 子供向けのレクリエーション人気ランキング
- アウトドアで盛り上がる楽しいレクリエーションゲーム
- 子供の頃に流行った懐かしい遊び
- 楽しい冬の遊び。子供が楽しめるレクリエーション
- 【子供とつくる】手作り外遊びのおもちゃ特集
- 【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び(11〜20)
ことろことろ

「ことろことろ」は、子供たちが楽しめる屋外レクリエーションゲームの1つです。
4人一組で手を肩に置き、一直線に並んで遊びます。
鬼役の子が最後尾にタッチしないよう、みんなで協力するのがポイント。
手が離れないように気をつけながら、制限時間内に一列を保つことができれば勝利です。
屋内外問わず楽しめるので、場所を選びませんね。
鬼役を交代しながら全員で活動できるのも魅力的。
保護者の方や先生が昔懐かしい遊びを、お子さんと一緒におこなう絶好の機会にもなりますよ。
ドリブルリレー

ボールを使ったスポーツの入門編としても楽しめるドリブルリレー。
チームごとに分かれて、ボールを地面にバウンドさせながら次の人へ渡していく競技です。
息を合わせながらボールを受け渡すので、お子さんの協調性も育ちますよ。
オフェンスとディフェンスに分かれると、フィールド上の動きも戦略的になり、新しいスキルを身に付けるチャンスにもなります。
お子さまの動きを尊重しながら、保護者の方も一緒に楽しむ姿勢で挑戦すれば、運動能力とコミュニケーション能力を同時に伸ばせる遊びになりますよ。
ぜひ家族や友達と一緒に遊んでみてくださいね。
ベーゴマ

ベーゴマで遊んでみませんか?
集中力や指先の器用さを育む楽しい遊びです。
お子さんと一緒に戦略を練ったり、順番を待つ忍耐力も身につきますよ。
先生や保護者の方も、お子さんとのコミュニケーションを深める良い機会になりそうです。
世代を超えた交流の時間として、みんなで楽しめるのがベーゴマの魅力。
公園や広場で、風を感じながらベーゴマを回してみましょう。
きっと新しい発見があるはずです。
お子さんの成長を見守りながら、一緒に楽しい思い出を作ってくださいね。
いろおに

鬼ごっこというのは本当にたくさんの楽しいルールがあり、これらを考えた人はすごいなぁと思います。
今回はその中でも人気の「いろおに」の紹介です。
基本的は普通の鬼ごっこなのですが、いろおにの場合は「指定された色を触っていればバリアができる」というところがポイントです。
はじめに鬼が色を指定し、そこから一斉にばらけてその色を探しに行きます。
想像もつかなかったところにお目当の色があったり、どこにもなかったり、広い視野と観察力を持って遊べる鬼ごっこです。
「透明!」と言われて空気を触ったことを思い出します。
水切り

河原や湖など、石ころが転がっている水辺で遊べるのがこちらの「水きり」。
アウトドア遊びの定番ですが、やはりなんどやっても楽しいですね。
石をできるだけ水面と平行にして投げることにより、石が水の上を跳ねるという現象が起きます。
うまくやれば何回も何十回も跳ねるので、この連鎖を競ったりして楽しみましょう。
投げる姿勢や石選びなど、コツをつかめばどんどんうまくなってゆく感覚が気持ちいいすね。
たくさん跳ねさせてみんなの歓声をあびるにも最高です!
色水遊び

色水遊びは、子供たちの感性を刺激する素敵な遊びです。
透明な水に色を付けて、水の感触や色の変化を楽しみましょう。
まずは、水性マーカーでコピー用紙に色を塗ります。
次に、水の入ったコップにコップ用紙をつけると、少しずつ色が広がっていきます。
子供たちの驚く顔が見られるかもしれませんね。
いくつかの色水ができたら、それぞれを混ぜて新しい色を作ってみるのもおすすめです。
集中力や観察力を育む色水遊びを、ぜひ実践してみてくださいね。
【子供向け】屋外レクリエーション・ゲーム。たのしい外遊び(21〜30)
雪合戦

雪が降る地方では定番の冬の遊び、雪合戦。
雪が少ない地域でも雪が降るとみんな喜んで外に出かけて雪だるまを作ったり友達が集まると雪合戦をして遊びますよね。
最近では雪合戦はスポーツとして、細かなルールもあってひそかに注目の遊び、スポーツになっています。
隠れる場所を作ったり、お互いの陣地にぬいぐるみなどを置いてそれを取られたら負けなど、いろいろと工夫をして遊んでみましょう。
人数が少なくても大人数でも遊べますよ。