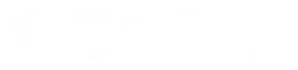カラオケで人気の演歌ランキング【2026】
人気の演歌曲を歌うと、たとえ演歌がそれほど好きではない人でも盛り上がりますよね。
でも、カラオケっていざ曲を選ぼうとすると、迷ってしまいがちです。
カラオケで人気の演歌をランキングにまとめてみましたのでご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気の演歌。最新ランキング【2026】
- カラオケで人気の演歌歌手ランキング【2026】
- カラオケで歌いたい演歌の名曲、おすすめの人気曲
- 五木ひろしの人気曲ランキング【2026】
- 【60代】カラオケで盛り上がる曲ランキング【2026】
- 人気の演歌歌手ランキング【2026】
- 【女性】カラオケで歌いやすい曲ランキング【2026】
- 【2026】演歌の最近のヒット曲。要注目の歌謡人気曲
- 【男性】カラオケで盛り上がる曲ランキング【2026】
- 【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~女性歌手編
- 吉幾三のカラオケ人気曲ランキング【2026】
- 日本の心・演歌のかっこいい名曲
- 【2026】演歌の代表的な有名曲。定番の人気曲まとめ【初心者向け】
カラオケで人気の演歌ランキング【2026】(21〜30)
おんな港町八代亜紀22位

『おんな港町』は1977年にリリースされた八代亜紀さんのシングル曲で、実は1973年に発表された南有二とフルセイルズによる『おんなみなと町』が原曲のカバー曲です。
第28回NHK紅白歌合戦でも歌唱され、第10回全日本有線放送大賞の特別賞を受賞した名曲ですね。
歌謡曲テイストが濃厚な音作りで、直球の演歌にまだ慣れていないという方や、昭和歌謡がお好きな方であればカラオケで歌うという意味でもうってつけの曲と言えそうです。
日本語をしっかりと発音して軽いアクセントをつけたリズミカルなAメロ、Bメロやサビに登場する特徴的なビブラートの部分などは音程を外しやすいですから重点的に練習してみてください。
舟唄八代亜紀23位

唯一無二のハスキーボイスで演歌界に多大な影響をもたらした女性演歌歌手、八代亜紀さん。
死してなお愛されており、今でも多くのカラオケ喫茶で彼女の楽曲が歌われていますね。
そんな八代亜紀さんの楽曲のなかでも、特にオススメしたいのが、こちらの『舟唄』。
やや音域の広い楽曲ですが、音程の上下自体はそこまで激しくはありません。
ただ、楽曲のアイコンにもなっている間奏部分で歌われるパートが少し厄介です。
このパートは息が続きづらいので、最初からビブラートをかけるのではなく、歌い終わりでビブラートをかけるようにしましょう。
そうすれば息が続きます。
雨の慕情八代亜紀24位

八代亜紀さんの名曲『雨の慕情』。
独特のハスキーボイスを活かしたメロディーが印象的な作品で、全体を通してボーカルラインが控えめに仕上がっています。
声を張り上げるようなパートはなく、枯れた雰囲気をしみじみと歌い上げるタイプの楽曲なので、声量やシャウトなどの力強いボーカルを必要としません。
彼女の楽曲としては、こぶしの登場回数も少ないので、歌いやすい楽曲と言えるでしょう。
ぜひレパートリーに加えてみてください。
わが町は緑なりき千昌夫25位

おだやかなメロディーが印象的な千昌夫さんの名曲『わが町は緑なりき』。
一応、ジャンルとしては演歌にあたる作品なのですが、ボーカルラインに関しては昭和歌謡のエッセンスが強く、演歌の特徴であるこぶしはほとんど登場しません。
少なからず登場するこぶしはほとんどが1音階の上下にとどまっているので、演歌の歌い回しが得意ではない方でも問題なく歌いこなせるでしょう。
昔ながらのムードのある楽曲が好きな方は、ぜひレパートリーに加えてみてください。
俺ら東京さ行ぐだ吉幾三26位

コミックソングから女歌、泣き歌まで幅広い音楽性で知られる演歌歌手、吉幾三さん。
演歌歌手としては珍しく、シンガーソングライターとしての一面も持っており、自身で作詞作曲した独創性にあふれる楽曲は、時代を超えて常に愛され続けています。
そんな吉幾三さんの名曲といえば、やはりこちらの『俺ら東京さ行ぐだ』ではないでしょうか?
演歌らしい要素を持ちながらも、語り口調のパートが多いため、全体の難易度は低めです。
コミックソングということもあって、盛り上がりはバツグンなので、ぜひレパートリーに加えてみてください。
さざんかの宿大川栄策27位

熱のこもった歌声が聴く人の心を震わせる大川栄策さんの代表曲。
不倫をテーマにした切ない恋の物語を描いた歌詞と、情感たっぷりのメロディが見事に調和しています。
1982年8月にリリースされ、累計180万枚の大ヒットを記録。
1983年の日本レコード大賞ではロングセラー賞を受賞し、同年のNHK紅白歌合戦初出場も果たしました。
演歌初心者の方にもお馴染みの曲だと思いますが、歌唱にはある程度の技術が必要ですね。
まずは大川さんの歌い方をよく聴き、息継ぎのタイミングなどを研究してみるのがおすすめです。
珍島物語天童よしみ28位

愛する人との再会を願う切ない思いが胸を打つ名曲です。
韓国・珍島の「海割れ現象」をモチーフに、離れ離れになった人々の強い思いを描いた歌詞が多くの共感を呼び、1996年2月にリリースされると瞬く間に大ヒットを記録しましたね。
天童よしみさんの力強い歌声が楽曲の魅力をさらに引き立てています。
歌詞には「海の神様、カムサハムニダ」といった韓国語がちりばめられているのですが、難しい発音は少なく、メロディーラインも覚えやすいため、カラオケで気軽に歌える一曲と言えるでしょう。
演歌が好きな方はもちろん、普段あまり演歌を歌わない方にもおすすめの楽曲です。