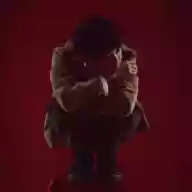背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
「怖い曲で恐怖を感じたい!」または「怖い曲の歌詞を眺めたい!」そんな好奇心旺盛の方に必見の不気味な名曲、怖い人気曲をリサーチしました。
音楽ファンの間で人気のものから、当サイトの音楽を専門としたライターが選んだ曲を織り交ぜながら幅広く紹介します!
邦楽や洋楽、新旧問わず厳選いたしました。
聴いただけで分からないけど、歌詞の解釈次第では恐怖を感じる楽曲もあります。
夏の名物の怪談などで紹介した曲の内容を話してみるのも面白いと思います!
怖い歌を聴いて背筋を「ゾクゾクっ!」と凍らせてみませんか!
背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲(41〜50)
夜叉ヶ池人間椅子

人間椅子と言えば、イカすバンド天国という番組で、ネズミ男のコスプレをしていた男がいたバンドと言えば、世代の人ならわかると思います。
この曲の怖い所は、いきなり自殺しているのです。
童謡の通りゃんせとか、これもまた怖い歌なのです。
リンチcali≠gari

カルト的な曲調が特徴で1993年に結成されたバンドcali≠gariの『リンチ』は、曲の出だしから強烈な歌詞が耳に飛び込んでくる青春、ブラック、恐怖が詰め込まれた恐怖ソングの代表のようなアングラ曲です。
テンポのいいリズムなのに明るさを感じさせない曲です。
餓鬼犬神サアカス團

食事中の方は、この曲『餓鬼』を聴くのは食後にしてください。
聴きながらだと気持ち悪くなって箸を置いてしまいます。
詩が恐ろしくて、グロテスクさが日本一と言える曲です。
演奏しているロックバンド犬神サーカス団(現:犬神サアカス團)は、1994年の当時高校生だったボーカルの凶子さんがマンガ雑誌の文通コーナーにて活動メンバーを募り結成したバンドで、現在も活躍中です。
恐怖が伝わってくる曲の創作を得意としているグループです。
まちぶせ石川ひとみ

ちょっぴり切ない片思いソング……ではありますが、見方によってはストーカーではないかと思ってしまう曲です。
1970年代に活躍したアイドルで、歌手、女優としても高い評価を得ている石川ひとみが歌っています。
もともとは三木聖子の曲として1979年にリリース。
その後1981年に石川ひとみバージョンが発売されました。
怖い歌というくくりに入れてはいますが、名ラブソングとして長年、世代を超えて愛されています。
幽楽町線八十八ヶ所巡礼

踏切音が鳴り響くイントロをバンドで表現しているところから、まず、不気味。
八十八ケ所巡礼、通称『八八(はちはち)』は、2006年に結成された日本で活動するスリーピースインディーズバンドです。
エキセントリックな歌詞やメロディは中毒性があり、気がつけば何度も聴いてしまう狂信者多数……。
独特の世界観は、ぜひ彼らのライブで現実に味わってみると、開けてはならないパンドラの箱が開くかも。
メトロポリタン美術館大貫妙子

この時、子供だった皆様にはトラウマソングなのです。
この歌はNHKのみんなのうたでかけていました。
二番歌詞でファラオは眠ると歌っていて、細微に目覚まし時計掛けておくから、ファラオは起こさない様にしてください。
だからメトロポリタン美術館に閉じ込められるのです。
死にぞこないの唄友川カズキ

この歌は、死んだりする怖い曲ではなくて、自殺志願の男が何をやっても死なない、死ねない歌です。
何を訴えたのか、死にきれないなら生きろです。
生きぞこないより死にぞこないの方がむマシだろうの事です。
で、この歌の怖い所は、淡々と自殺場面を歌っている所です。