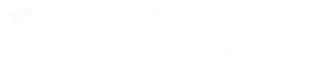中学生におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
中学生にオススメの室内遊びを紹介します!
最近では、中学生でもスマホをお持ちの方が多いと思います。
コミュニケーションアプリで話したり遊んだりする事もあると思いますが、まだまだ実際に顔を合わせて楽しむ事も多いですよね。
そこでこの記事では、クラスメイトや部活のメンバーなど、みんなで一緒に楽しめる室内レクリエーションを紹介していきたいと思います。
学校の休み時間や放課後、仲良しメンバーと集まった時などに遊べるので、ぜひみんなで楽しんでくださいね!
- 中学生向けの楽しい遊び。レクリエーションゲーム
- 中学生向けのレクリエーション人気ランキング
- 中学生向けの盛り上がる学年レクリエーションまとめ
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 【盛り上がる!】学校の教室で遊べる簡単ゲーム。クラスで楽しむレクリエーション
- 室内レクの人気ランキング
- 【中学生向け】暇なときのオススメの過ごし方
- 【小学校】中学年におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 室内で楽しめる簡単なレクリエーション・ゲームまとめ
- 【第2弾】12月におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 雨でも安心!体育館でできる楽しいレクリエーション
- 高校生が本気で盛り上がるレクリエーション!楽しいアイデア集
- 暇つぶしにぴったり!3人で楽しめるゲームまとめ
中学生におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム(11〜20)
並び替えゲーム
@ick_inc 並び替えゲーム! 見事成功できるか?! #ick株式会社#バズりたい会社#ゲームチャレンジ#チャレンジ #チャレンジ動画
♬ オリジナル楽曲 – ICK株式会社 – ICK株式会社
ヒントをもとに答えを導き出そう!
並び替えゲームのアイデアをご紹介します。
休み時間や自由時間にオススメしたいレクリエーションのアイデアですよ!
ペットボトルなどの飲み物を2本ずつ5種類用意したら準備完了!
飲み物を並び替えて、正解の並べ方を当てるシンプルなゲームですよ。
1人につき1つ並べ替えて、正解を導き出すのがポイントです。
指示役は現段階で正解している飲み物の数を伝えられると良いでしょう。
簡単そうに見えて頭を使うゲームです!
飲み物以外に文房具などでも応用できそうですね!
フラフープダウン

新年度から送別会まで、どのタイミングで遊んでも楽しい!
フラフープダウンのアイデアをご紹介します。
フラフープダウンの遊び方は、参加者が輪になりフラフープを人差し指の上に乗せて、指が離れないように地面までおろすというシンプルなルールです。
一見、簡単そうに見えるゲームですが、なぜかバランスが崩れたりフラフープが指から離れたりと、予想外のハプニングに盛り上がるでしょう。
仲の良い友達と挑戦するのもおもしろいですが、あまり話したことのない関係性でも、心をひとつにする良い機会となりそうです。
ポーズ合わせゲーム

人数が多ければ多いほど盛り上がるかも?
ポーズ合わせゲームを紹介します。
その名の通り、お題に合わせてそれぞれが「せーの!」でポーズをとり、ポーズが全員一致すれば成功という遊びです。
お題は動物やキャラクター、さまざまな職業の人や身近な人など、みんなが知っているものならなんでもOKです。
人数が多いときはチーム戦にして、先に全員一致したチームが勝ちというルールにしてもおもしろそうですね。
チームワークが試されるユニークなゲーム、ぜひ遊んでみてくださいね。
わたしはだれ?クイズ

出題者と回答者みんなで盛り上がる私はだれでしょうクイズ。
出題者はお題を決めたらお題のヒントや特徴を回答者へ伝えます。
回答者は、お題が何かを考えて答えていきましょう。
考える力、想像する力を育て、刺激できる楽しいゲームになっています。
慣れてきたら、制限時間を設けたり問題の難易度を高めたりしながら進めていきましょう。
また、実在する人物や歴史上の人物をお題にするのもオススメです。
ぜひ楽しんで挑戦してみてくださいね。
ジェスチャー伝言ゲーム

言葉を使わずに身ぶり手ぶりだけで伝えるジェスチャー伝言ゲームを楽しんでいきましょう。
1チーム5、6人位でチームを作り一列に並んだら最初の人がお題を確認します。
お題を次の人へ言葉はなしで身ぶり手ぶりを大きくしながら伝えていきましょう。
最後の人はお題の正解を答えます。
ジェスチャーを大きくしたり、顔の表情も加えることで伝わりやすくなるかもしれませんね。
もし伝わらなかった場合どう工夫すれば伝わるのか考えるのもこのゲームの楽しいポイントかもしれませんよ。
紙コップジェンガ

ドキドキしながら楽しもう!
紙コップジェンガのアイデアをご紹介します。
ジェンガは、積み木を使ったパーティーゲームで、参加者が積み上げた塔を崩さずにブロックを取り出していくシンプルなゲームです。
子供から大人まで楽しめるジェンガを、今回は紙コップとコピー用紙でアレンジしてみましょう。
準備や片付けが簡単にできるのも魅力的ですよね。
休み時間やすきま時間にもオススメなゲームなので、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。
中学生におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム(21〜30)
反応ゲーム
https://www.tiktok.com/@otnasobi_ehime/video/7129096193015123202指示をよく聞いて、素早く動くのがポイント!
反応ゲームのアイデアをご紹介します。
室内でも体を動かして遊びたいという時にオススメしたいレクリエーションのアイデアです。
準備するものはカラーマーカーなどのアイテムのみ。
2人1組で向かい合わせに立ったら準備完了です!
ゲームが始まったら足踏みをして、指示された自身の体の部位に触れましょう。
指示役が「ひじ」といったらカラーマーカーを取るというシンプルなゲームです。
ぜひ、取り入れてみてくださいね。