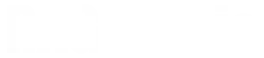【洋楽】カッコいいスリーピースバンド。おすすめのトリオまとめ【2025】
スリーピースのバンドって、ステージに立った見た目がすでにカッコいいですよね。
基本的なギター、ベース、ドラムという編成であれば、真ん中のドラマーがはっきり見えるというのもポイントが高いです。
パンキッシュでストレートなサウンドを鳴らすバンドもいれば、高い演奏技術でトリオとは思えない分厚く複雑なアンサンブルで魅せるバンドもいますし、人気のスリーピース・バンドほど、それぞれのミュージシャンとしての才能や個性を生かした形でトリオ編成の魅力を引き出しているものです。
そこで今回の記事では、洋楽史に残るカッコいいスリーピースのロック・バンドをご紹介。
伝説的なバンドから近年の若手まで、幅広いラインアップでお届けします!
【洋楽】カッコいいスリーピースバンド。おすすめのトリオまとめ【2025】(61〜80)
We Better Get ReadyPack

ドイツの最初期パンクバンドにして最高峰。
ミュンヘン出身で、デビュー時はメンバー全員30歳を超えていたとか。
石炭倉庫で録音されたということですが、初期衝動もろだしのアグレッシヴな演奏はパンクとしてのパワーも申し分ありません。
LolaThe Raincoats

79年デビューした、いわゆるポストパンク世代の中では実力・人気でトップを走ったガールズトリオ。
音楽性の高さはジョン・ライドンやカート・コバーンも絶賛したほど。
84年解散、94年再結成し、10年にはなんと奇跡の初来日も果たしました
Fight The Good FightTriumph

カナダのハードロック界を代表するトライアンフは、1975年に結成された3人組バンドです。
ラッシュと並んでカナダのロックシーンを牽引し、ハードロックやヘヴィメタルのジャンルで活躍しました。
1979年にリリースされたアルバム『Just a Game』からの楽曲がアメリカでヒットし、ビルボードチャートにも登場。
1981年の『Allied Forces』は100万枚以上の大ヒットを記録しています。
彼らのライブパフォーマンスは高い評価を受け、1978年にはカナダジャムフェスティバルで約11万人の観客を前にヘッドラインを務めました。
2008年にはその功績が認められ、ジュノー賞の殿堂入りを果たしています。
ハードロックの魂と卓越した演奏技術を求める方におすすめのバンドです。
Freak SceneDinosaur Jr.

2022年の3月に日本でも公開されたドキュメンタリー映画『フリークシーン』で若い音楽ファンの間でも注目を集めている、USオルタナティブロックの生き字引であるダイナソーJr.。
変わった性格とやるせない歌声で「無気力大魔王」とも言われたJ・マスシスさんを中心として、後にセバドーやといったプロジェクトで人気を集めるベーシストのルー・バーロウさん、そしてドラマーのマーフさんがオリジナル・メンバーとして知られている彼らは1980年代のハードコア・シーンから登場し、インディーズ・シーンのカリスマ的存在のソニック・ユースに認められて名門SSTレコード名門と契約を果たして『You’re Living All Over Me』と『Bug』という2枚の名盤をリリースします。
その後ルーさんが脱退、その後はメジャー・デビューを果たして商業的な成功を収めるも、マーフさんも脱退して以降はマスシスさんの実質的なソロ・プロジェクトとして活動、1997年には解散してしまいます。
数年後に2005年にはオリジナル・メンバーが集結して再結成、マイペースながら現代もバリバリの現役として活動中です。
そんな彼らのトレードマークともいえる、マスシスさんの耳をつんざく轟音ギターの中に漂う切ないメロディは本当に唯一無二の魅力を放ち、90年代オルタナティブロックの形成において重要な役割を果たしていることも見逃せません。
そんな彼らのポップな魅力を味わいたいのであれば1991年の『Green Mind』辺りを、オリジナル・メンバー3人による強力なバンド・アンサンブルの魅力も味わいたい方は前述したインディーズ時代の2枚をオススメします!
TomorrowSilverchair

オーストラリアが誇るロックトリオ、シルヴァーチェアは、グランジからアートロックまで幅広い音楽性で世界を魅了してきました。
1995年、わずか15歳でデビューアルバム『Frogstomp』をリリースし、一躍スターダムに躍り出ました。
1997年の『Freak Show』では全米トップ20入りを果たし、国際的な評価を確立。
2002年の『Diorama』はARIAアワードで7部門を受賞し、音楽性の進化を示しました。
ダニエル・ジョンズさんの個人的な闘いを反映した深い歌詞と、3人の卓越した演奏力が融合した彼らの音楽は、ロックファンの心を掴んで離しません。
パワフルかつ繊細な音楽を求める方におすすめです。