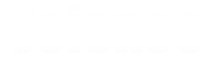先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア
理科の自主学習は、子供たちにとって楽しい冒険にもなります!
こちらでは6年生にオススメの、先生に褒められそうな自学理科のテーマを紹介します。
自由に調べてみると、学ぶことがもっと楽しくなりますよ。
身近な自然を観察したり、簡単な実験をしてみたりして、いろいろなことを発見する喜びを味わってください。
自然や科学に対する興味が育って、自分が学んだことを友達や家族に話せることも楽しいですよ。
ぜひ、こちらを参考にして、一緒に楽しい理科の世界に飛び込んでみてくださいね!
- 小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 先生に褒められる自主学習!5年生にオススメの自学理科のアイデア
- 先生に褒められる自主学習!3年生にオススメの自学理科のアイデア
- 【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集
- 先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア
- 小学生にオススメ!6年生向けの作って楽しい工作アイデア集
- 小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学3年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア
- 小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集
先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア(71〜80)
手ごねせっけん作り

手ごねせっけん作りを知っていますか?
まずせっけん素地を温めて粘土状にし、そこに色素を加えて色を付けます。
すると限りなく粘土に近い状態に仕上がります。
あとは粘土遊びをする時のように、好きな形にこねてみてください。
形を整えたら乾燥させて完成です。
動物や星形など、アイデア次第でどんな石鹸も作れてしまいますよ。
何か夏らしいものをモチーフにしてみるのも、自由研究らしくていいですね。
ちなみに匂いを付けたい場合は、精油を使うのがオススメです。
手作りクレーンゲーム

お菓子やぬいぐるみ、フィギュアなどを取るクレーンゲームは子供たちから人気を集めていますね。
「この景品はこのアームの動きで取れるかな……」というドキドキが家でも楽しめる装置を自作してみましょう。
段ボールや空き箱を使って本体を作ります。
次に、ストローや割り箸でクレーンアームを作り、糸でつなげて動かせるように工夫しましょう。
景品は、小さなオモチャやお菓子など、好きなものを用意しましょう。
クレーンゲームの仕組みを調べながら作ることで、工作の楽しさに気づくきっかけにもなります。
製作過程だけでなく、完成したゲームで遊んで楽しめる自由研究のアイデアです。
手作り望遠鏡で天体観測

望遠鏡で天体観測をしてそれを自由研究にしてみるのはどうでしょうか?
ちょっとおもしろみに欠ける……と思うかもしれませんがなんと、望遠鏡も自分で手作りしてしまおう!というアイデアなんです。
望遠鏡の材料はお菓子などの筒状の空き箱、黒い画用紙、老眼鏡、虫眼鏡、黒いビニールテープなどで廃材と100円ショップの材料で作れるのが驚きです。
オリジナルの望遠鏡を使って、月や星など観察してみましょう。
夏休みの間に月食や流星群などの天体ショーが重なるといいですね!
先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア(81〜90)
手作り花火

夏といえば花火は欠かせないイベントですよね。
市販されているものを購入するイメージが強いそんな花火を自作してみるのはいかがでしょうか。
作っていくのは線香花火で、火薬の素である酸化剤や燃焼剤、閃光剤を混ぜ合わせて、紙に巻いていくという内容ですね。
パチパチとはじけるように燃えるので、安全面には注意しつつ、より長持ちする量や巻き方などを試していきましょう。
火薬の乗せ方によっては燃え方にもムラが出るので、集中して作業に挑むことも重要なポイントですよ。
比重の実験「レインボージュース」

ひとつのグラスの中に美しい色の層がある、虹のような不思議な見た目のジュースです。
重要なのはそれぞれの色に加える砂糖の量で、液体の比重を利用して層を作っていきます。
作る色は赤と黄色と青の3色で、砂糖の量を変えて作り、重いものから順番にグラスへと注いでいきます。
色が混ざった層も作りつつ、完全に混ざらないように、スプーンを伝うようにしてゆっくりと注ぐのが重要ですね。
これだけだとただの砂糖水なので、味も楽しめるように香料などを利用するのもオススメですよ。
水の浮力の実験

浮力と聞いて思い出す人物は?
そうアルキメデスですよね。
「アルキメデスの原理」を読み解く!!とまではいきませんがそんな浮力をさまざまな角度からアプローチしてみましょう。
数種類の液体にたくさんの物体を浮かせてその浮かび具合を考察します。
まずは浮く野菜と沈む野菜の考察なんかはどうですか?
同じトマトでも浮くトマトと沈むトマトがあるんですが、糖度が違うの??それとも新鮮さが違うの?……と実験をはじめ前からなんだかワクワクしますよね。
あとは液体を変えて油や食塩水にモノを浮かべてみる。
浮力測定器があれば浮力が数値化できてより科学的な考察に!
あなたも第2のアルキメデスを目指してみましょう!
流れる水のはたらきの実験

5年生では浸食作用、運搬作用、堆積作用など、流れる水の働きについても授業で習うと思います。
それらの働きを実験を通して実際に観察してみましょう。
実験方法は、土を集めて作った斜面に水の通路を作りそこに水を流します。
浸食作用、運搬作用、堆積作用が実際にどのように現れるのか、流す水の量でその働きは変わるのか、水の通路が真っすぐの場合とカーブの場合でそれぞれの作用の現れ方が異なるのかなど、さまざまな条件で試してみてその結果をレポートにまとめてみましょう。