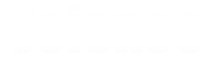先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア
理科の自主学習は、子供たちにとって楽しい冒険にもなります!
こちらでは6年生にオススメの、先生に褒められそうな自学理科のテーマを紹介します。
自由に調べてみると、学ぶことがもっと楽しくなりますよ。
身近な自然を観察したり、簡単な実験をしてみたりして、いろいろなことを発見する喜びを味わってください。
自然や科学に対する興味が育って、自分が学んだことを友達や家族に話せることも楽しいですよ。
ぜひ、こちらを参考にして、一緒に楽しい理科の世界に飛び込んでみてくださいね!
- 小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 先生に褒められる自主学習!5年生にオススメの自学理科のアイデア
- 先生に褒められる自主学習!3年生にオススメの自学理科のアイデア
- 【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集
- 先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア
- 小学生にオススメ!6年生向けの作って楽しい工作アイデア集
- 小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学3年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア
- 小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集
先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア(21〜30)
レインボーポンチの作り方

色と状態変化を学べる自由研究にぴったりなレインボーポンチ。
かき氷シロップをいくつかのカップに分けて使い、好きな色をそれぞれ混ぜます。
ゼラチンをお湯に溶かして各色のシロップと混ぜ合わせたら、冷蔵庫で冷やしてゼリーに固めましょう。
できあがったカラフルなゼリーをグラスに入れ、最後に炭酸水を注ぐとしゅわしゅわとした泡と共に虹色のドリンクが完成。
ゼラチンが液体から固体に変わる様子や炭酸水との相性を観察することで、色彩や温度状態変化に関する理解が深まります。
見た目にも楽しめて科学的な要素も盛り込める、観察と実験の両方を味わえるアイデアです。
一瞬で固まるゼリーの作り方

キラキラと光るカラフルな粒が美しいゼリーの作り方を紹介します。
ゼリーの素をアルギン酸ナトリウムで作り、かき氷シロップや食紅で色をつけた液体を乳酸カルシウムを溶かした水の中にそっと流し込むと、不思議なことに一瞬でぷるんとしたゼリーが固まります。
この現象は、アルギン酸とカルシウムが化学反応を起こしてゼリー状の膜を作るからです。
ライトで光らせると、さらに幻想的な仕上がりに。
色の組み合わせや形を工夫すれば、子供たちが見た目にも楽しい作品になるでしょう。
科学と工作が融合した、不思議がいっぱいの自由研究にぴったりなアイデアです。
持ち運べる水の実験

夏休みの宿題の自由研究に、頭を悩ませている子供もいるのではないでしょうか?
実験の要素もある、持ち運べる水を作ってみましょう。
「持ち運べる水?」と思う方もいますよね。
確かに水を手のひらにのせると、こぼれ落ちてしまいます。
ですが、あるものを水に入れるとゼリー状に。
このあるものとは、食用乳酸カルシウムと食用アルギン酸を使いますよ。
アルギン酸はカルシウムイオンと結合しやすいことから、水がゼリー状に固まるそうです。
水がプルプルとしたゼリー状になる面白い実験もできるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
空気砲

作り方は簡単!ダンボール箱に穴を開けて、隙間から空気が出ていかないよう四つ角をガムテープでしっかり止めます。
あとは側面を叩けば穴から空気が発射されます。
的を置いて当ててみたり、煙を中にためてから発射すると空気の動きが分かりやすくなりますよ。
ホバークラフトで摩擦についての考察

工作の自由研究にオススメなのが手作りホバークラフトです。
ホバークラフトは空気の力で浮く水陸両用の船なのですが、それをペットボトルと風船で再現しようというのがこの自由研究。
このまま机の上や水の上に浮かぶのでとてもおもしろいですよ。
不思議な見た目なのでそのまま作品として提出するのもいいですし、摩擦などの原理を考察して文章にまとめるのもオススメです。
バターを作る実験

パンに塗ったり、じゃがバターにしたり、さまざまな食材をおいしくしてくれるバター。
実はとてもシンプルな手順で作れるのをご存じでしたか?
主な工程としては、滅菌した容器に冷やした生クリームを入れ、強く15分振り続けるだけ。
液体が固形に変わり、その固形の部分が無塩バターです。
塩を混ぜるとバターのできあがり!
15分振り続けるのは意外に大変なので、テレビなどを見ながらすると良いかもしれませんね。
どうしてバターができるのかもまとめてみましょう。
地震計の作り方

身近な材料で作れる、地震計を作ってみませんか?
地震計と聞くと難しく感じますが、実は簡単に作れてしまうんですよ。
地震計の主な装置は、不動点となる振り子と記録機構の2つです。
振り子はコップに粘土を詰め軸となる竹串を指し、割りばしで作った支柱にフックと糸を使ってつるします。
記録構造部分は、ボルトを通したトイレットペーパーの芯とボールペンで作りますよ。
装置の土台は何でもOKですので、装置が入る木箱を探してみてくださいね。