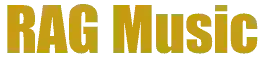懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ
演歌の名曲というと、現在の若い世代の間でも知られている名曲がたくさんあるほどで、まさに時代を越えて愛されている音楽ですよね。
とはいえ、演歌の最盛期といえば昭和時代だったのかもしれません。
数多くの演歌歌手がたくさんの楽曲を世に送り出し、多くのリスナーが演歌に心をつかまれていた時代ですよね。
そこでこの記事では、昭和の時代を彩った懐かしの演歌の名曲を一挙に紹介していきます。
時代を越えて愛される名曲はもちろん、知る人ぞ知る隠れた名曲まで選びました。
ぜひこの機会にあらためて一時代を築いた名曲たちをお聴きください。
- 【昭和】演歌のヒット曲まとめ。時代を越えて愛される名曲集
- 70年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の男性演歌歌手まとめ。演歌界を支える名歌手たち
- 80年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の女性演歌歌手まとめ。懐かしさを感じさせる歌声
- 【昭和時代の歌】カラオケで歌いやすい名曲を紹介します。
- カラオケで歌いたい演歌の名曲、おすすめの人気曲
- 【2026】演歌・ムード歌謡の名曲まとめ
- 【演歌】60代の男性歌手特集。渋さが光る演歌歌手
- 昭和を代表する女性演歌歌手まとめ
- 【2026】演歌の代表的な有名曲。定番の人気曲まとめ【初心者向け】
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~男性歌手編
- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(71〜80)
流恋草香西かおり

1988年にデビューして以来、演歌界の第一線で活躍し続ける香西かおりさん。
その豊かな表現力と情感あふれる歌声で多くのファンを魅了してきました。
1991年3月25日にリリースされたシングル『流恋草』は、彼女のキャリアにおいてとくに重要な作品の一つです。
この曲は、オリコンチャートで最高14位にランクインし、売上は80万枚を超える大ヒットを記録。
第24回日本有線大賞や第33回日本レコード大賞のゴールド・ディスク賞を受賞するなど、その実力は高く評価されています。
『流恋草』は、切ない恋心を繊細に描いた楽曲で、香西さんの歌声がリスナーの心に深く響きます。
とくに孤独と寂しさを感じる夜に、この曲を聴くことで、共感や癒やしを見つけられるかもしれませんね。
香西かおりさんのファンはもちろん、演歌をあまり聴かない方にもオススメしたい1曲です。
好きだった鶴田浩二

昭和の名優として知られる鶴田浩二さんが歌う、切ない恋愛バラードが今回紹介する作品です。
別れた恋人への後悔と未練を綴った歌詞は、男性の不器用な愛情表現を見事に描き出しています。
1956年にリリースされたこの楽曲は、鶴田さんの甘い歌声と哀愁漂うメロディが特徴的。
シングルのB面には『街のサンドイッチマン』が収録されており、カラオケバージョンも含めた全4曲が楽しめます。
1993年に再リリースされた本作は、昭和の歌謡曲に興味がある若い音楽ファンにもおすすめ。
恋に悩む人や、大切な人との思い出を振り返りたい気分の時にぴったりの一曲です。
昭和枯れすすきさくらと一郎

なんともいえない、せつない歌なんですが、決して平成生まれの方には理解できないのでは?
昭和生まれでもここまでは・・と思うのですが、1974年の人気テレビドラマ「時間ですよ昭和元年」の挿入歌として、居酒屋場面で流れる曲でイメージも生まれやすく、ヒットにつながりました。
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(81〜90)
夜明けのブルース五木ひろし

テレビの話なのですが、視聴者のチャンネル選択肢が地上波だけでおさまらなくなった今、演歌番組もどんどんとその数を増やしています。
日本の高齢化も関係しているのかな?
『夜明けのブルース』はどちらかと言うとムード歌謡寄りの演歌。
三味線・尺八とは違ったラインのノリのいいメロディーは若い人が聴いても違和感なしの1曲です。
夜の街を舞台に繰り広げられる男と女の駆け引き、その色恋をつづった歌詞はまさに大人の花舞台。
五木ひろしさんの力を抜いた歌唱がとても軽やかです。
なみだ恋八代亜紀

この時代の新宿って本当に演歌としての題材になりましたね。
1973年発売の「なみだ恋」は120万枚セールスの大ヒットしましたが、現在では歌手としても、画家としても活躍されている八代さんですが、15歳でバスガイトとなりましたが、歌手になりたくて上京したものの、苦労の連続で、お金がなくてご飯も満足に食べられない時代もあったと語られていました。
浮世絵の街内田あかり

1973年8月の「浮世絵の街」はアイドルが次から次へとデビューし、フォークソングもまだまだ盛んだった時代に異色のタイトルと衣装で歌っていたのが大きな話題になりました。
この時代はアイドルは世のおじさん、おばさんから「ジャリタレ」と呼ばれており、夜の世界を独特の歌い方でムードを出している内田あかりさんの曲が聴ける大人の曲となったようです。
女のみち宮史郎とぴんからトリオ

累計で300万枚以上を売り上げる大ヒット曲となったこの歌は、ワイルドなしゃがれ声のようで繊細な声帯コントロールと言葉の詰め方による絶妙のうまさが隠れていますが、そんな評論家めいた事はどうでも良いので、ただ聴きほれましょう。