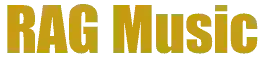懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ
演歌の名曲というと、現在の若い世代の間でも知られている名曲がたくさんあるほどで、まさに時代を越えて愛されている音楽ですよね。
とはいえ、演歌の最盛期といえば昭和時代だったのかもしれません。
数多くの演歌歌手がたくさんの楽曲を世に送り出し、多くのリスナーが演歌に心をつかまれていた時代ですよね。
そこでこの記事では、昭和の時代を彩った懐かしの演歌の名曲を一挙に紹介していきます。
時代を越えて愛される名曲はもちろん、知る人ぞ知る隠れた名曲まで選びました。
ぜひこの機会にあらためて一時代を築いた名曲たちをお聴きください。
- 【昭和】演歌のヒット曲まとめ。時代を越えて愛される名曲集
- 70年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の男性演歌歌手まとめ。演歌界を支える名歌手たち
- 80年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の女性演歌歌手まとめ。懐かしさを感じさせる歌声
- 【昭和時代の歌】カラオケで歌いやすい名曲を紹介します。
- カラオケで歌いたい演歌の名曲、おすすめの人気曲
- 【2026】演歌・ムード歌謡の名曲まとめ
- 【演歌】60代の男性歌手特集。渋さが光る演歌歌手
- 昭和を代表する女性演歌歌手まとめ
- 【2026】演歌の代表的な有名曲。定番の人気曲まとめ【初心者向け】
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~男性歌手編
- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(1〜10)
影法師堀内孝雄
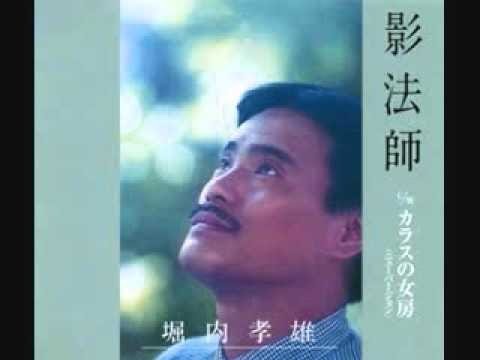
堀内孝雄が1995年に発売したシングルで、松平健が1980年にリリースした「夜明けまで」が原曲になっている曲です。
1993年の第24 回「日本歌謡大賞」で大賞を受賞し、この曲のヒットにより、第44回NHK紅白歌合戦に6年連続出場を果たしました。
テレビ朝日の「はぐれ刑事純情派」の主題歌としても起用されました。
波止場しぐれ石川さゆり

演歌に付きものといえば曲紹介の口上。
流れるような五七調で曲を紹介し、歌唱が始まる寸前でピタリとその役目を終える、まさに職人芸ですよね。
徳光和夫さんや綾小路きみまろさんの口上、ついつい聞き入ってしまいますよね。
「酒のさかなに霧笛を聞いて……」そんな口上がピッタリな曲がこの『波止場しぐれ』。
瀬戸内の港々を転々とする薄幸の女性をつづる風の歌詞も、演歌のど真ん中を突き進むもの。
ここまで五七調の調べに心が落ち着くのって、もはや日本人のDNAに五七調が組み込まれている??んですかね。
石川さゆりさんの色香も絶品の1曲です!
別れの一本杉春日八郎

故郷を離れる人の切ない思いを歌った、昭和を代表する名曲です。
春日八郎さんの澄んだ美声が心に染みわたります。
1955年12月に発売され、50万枚の大ヒットを記録。
翌年には同名の映画が制作されるなど、社会現象にもなりました。
ビゼーの歌劇『カルメン』をヒントに作られたメロディは、耳に残りやすく歌いやすいのが特徴。
ふるさとを思い出しながら口ずさんでみてはいかがでしょうか。
ゆったりとしたテンポで歌いやすいと思います。
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(11〜20)
中の島ブルース秋庭豊 & アローナイツ

メジャー盤は昭和50年発売。
どちらかというとクールファイブの歌としての方が有名ですが、こちらが本家本元です。
北海道の歌志内炭鉱でアマチュアバンドとして活躍が認められ、この曲を自主制作し、有線などでじわじわと売れ始めました。
名の通り舞台は北海道札幌の中の島でご当地ソングでもあります。
昔の名前で出ています小林旭

小林旭による伸びやかな歌唱で歌われたこの歌は、夜の街から夜の街へ、過去を捨てて生きるのがセオリーである水商売の女性が、恋心をしのぶ男性がいつ来ても良いようにと昔の源氏名を使い、店で待ち続けるという、女性のいじらしさが描かされています。
海雪ジェロ

「演歌界の黒船」ことジェロのデビュー曲。
MVに変な演歌テイストを取り入れず、ヒップホップ調なのが特にいいと思います。
宇崎竜童が「ジェロは歌える人だから」と難しいメロディを作ってしまい、彼自身は歌えないそうです(笑)。
戻り川伍代夏子

伍代夏子さんが1987年にこの名義で再デビューを果たした際のデビュー曲『戻り川』。
地道なキャンペーン活動をおこない、曲は大ヒットを記録しました。
危険な恋に走る二人に訪れた別れのとき、もうどう頑張っても一緒に生きていくことは難しいのだという切ない現実を描いています。
情感たっぷりの伍代さんの歌声が、歌詞で描かれる切なさ、残る未練を一層引き立てていますね。
一緒にいたい、でもいられない、そんな演歌の真骨頂ともいえる悲恋の物語をぜひ聴いてみてくださいね。