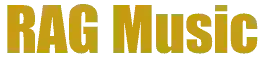懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ
演歌の名曲というと、現在の若い世代の間でも知られている名曲がたくさんあるほどで、まさに時代を越えて愛されている音楽ですよね。
とはいえ、演歌の最盛期といえば昭和時代だったのかもしれません。
数多くの演歌歌手がたくさんの楽曲を世に送り出し、多くのリスナーが演歌に心をつかまれていた時代ですよね。
そこでこの記事では、昭和の時代を彩った懐かしの演歌の名曲を一挙に紹介していきます。
時代を越えて愛される名曲はもちろん、知る人ぞ知る隠れた名曲まで選びました。
ぜひこの機会にあらためて一時代を築いた名曲たちをお聴きください。
- 【昭和】演歌のヒット曲まとめ。時代を越えて愛される名曲集
- 70年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の男性演歌歌手まとめ。演歌界を支える名歌手たち
- 80年代の偉大な演歌の名曲・ヒット曲
- 70代の女性演歌歌手まとめ。懐かしさを感じさせる歌声
- 【昭和時代の歌】カラオケで歌いやすい名曲を紹介します。
- カラオケで歌いたい演歌の名曲、おすすめの人気曲
- 【2026】演歌・ムード歌謡の名曲まとめ
- 【演歌】60代の男性歌手特集。渋さが光る演歌歌手
- 昭和を代表する女性演歌歌手まとめ
- 【2026】演歌の代表的な有名曲。定番の人気曲まとめ【初心者向け】
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~男性歌手編
- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(11〜20)
雨の慕情八代亜紀

1980年に発売されたこの曲は、阿久悠によって作詞され、その前年に発売された「舟唄」とともに八代の代表曲となりました。
サビのところからリズムが入る際の、手のひらを天に向ける振り付けが印象的ですが、他の彼女の歌の場合と同様、自然に出てきたものだそうです。
恋人を失った女心を切々と歌い上げています。
そして、神戸前川清

「そして、神戸」は1972年11月に、内山田洋とクール・ファイブの14枚目のシングルとしてリリースされました。
翌73年の第15回日本レコード大賞で作曲賞を授けられ、神戸のご当地ソングとして以上に演歌の名曲として歌い継がれています。
クール・ファイブでメインボーカルをつとめた前川清さんの代表曲でもあり、1995年の「阪神・淡路大震災」では多くの被災者を励ましました。
同年の第46回「NHK紅白歌合戦」で前川さんが歌い日本中から喝采を浴びました。
与作北島三郎

北島三郎さんのシングルで、1978年3月リリース。
これはもう当時をリアルタイムで過ごした方なら誰もがお耳にされたことのある昭和の名曲でしょう!
民謡に近いようなシンプルなメロディと歌詞の中に出てくる、とてもインパクトのある擬音等の数々、そして北島さんの卓越した歌唱力によって、聴く人の年代を超えた支持を得てロングセラーの大ヒット曲になりました。
北島さんの他にも何人もアーティストにカバーされたり、この曲のヒットにインスパイアされたと思われるゲームなども発売され、そんなことからもこの曲の影響力を強く感じさせてくれます。
擬音の部分だけを一緒に歌ってみるのも楽しい昭和の名曲です!
函館の女北島三郎

北島三郎13枚目のシングルとして1965年に発売されました。
永谷園から発売されているお茶づけ海苔シリーズの「さけ茶づけ」のCMでこの曲の替え歌が使用されたことをきっかけに大ヒットを果たし、ミリオンラーを記録しました。
1988年の青函連絡船最終運航の際、この曲の大合唱となりました。
北国の春千昌夫

千昌夫が1977年に発売した曲で、オリコンシングルチャートでは、100位以内初登場から通算92週目でミリオンセラー達成した曲です。
都会で暮らす男性が実家から届いた小包を受け取り、春間近の故郷や家族、かつての恋心などを思う内容の歌詞となっており、古帽子、丸縁眼鏡に使い込んだカバンという姿で歌う姿がとても印象的でした。
珍島物語天童よしみ

「珍島物語」は、天童よしみが、1996年に発売した楽曲で、32枚目のシングルにあたります。
彼女の代表作のひとつであり、ロングヒットで130万枚をこえる売上を記録、自身初のミリオンセラーとなりました。
韓国・珍島の海割れをモチーフに、遠く離れた相手への思いが歌詞に込められています。
懐かしの演歌。昭和の演歌の名曲まとめ(21〜30)
熱き心に小林旭

かつてコーヒーのCMに使われていました。
もっと知られていてもいい名曲。
タイトルは「熱き」とありますが、どちらかと言えば雄大さを感じさせる曲です。
メロディは大瀧詠一の書きおろし。
本当にいい曲なのでもっと全世代的に有名になってほしいです。