【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
初級からは脱出したけれど、上級レベルの曲にチャレンジするにはもう少し経験が必要……今回は、このような中級レベルのピアノ曲をお探しの方にピッタリのかっこいい作品を集めました。
繊細な響きや力強い響き、叙情的な雰囲気や快活な雰囲気、ピアノの音色が表現できる範囲は無限大!
そんなピアノの魅力を思う存分味わえるすてきな作品をご紹介していきます。
定番のクラシック曲はもちろん、映画音楽やポップな楽曲など、幅広く選曲しています。
発表会にもオススメな曲ばかりですので、これから取り組む曲にお悩み中の方は、ぜひチェックしてみてください!
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級者】オススメのピアノ連弾曲|かっこいい&華やかな作品を厳選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】(71〜80)
ソナチネ M.40 第1楽章Maurice Ravel

モーリス・ラヴェルの作品の中には、バロックや古典派作品への傾倒が垣間見えるものが多々あり、この『ソナチネ』も古典様式へのこだわりを感じられる作品の1つです。
第1楽章は、ソナチネ形式を守りつつラヴェルらしい絵画的で美しいメロディが際立つ楽曲です。
ソナチネアルバムの収録曲を練習したことのある方なら「この響きは古典作品には絶対に出てこない」というポイントを感じ取れるはず!
繊細なタッチでの演奏は容易ではありませんが、時代による違いなども感じながら演奏すると、ラヴェルの作品への興味が一層湧いてくるでしょう。
亡き王女のためのパヴァーヌMaurice Ravel

テレビCMや映画の挿入歌として使用されており、モーリス・ラヴェルのピアノ作品の中で最も多く耳にする機会があるであろう『亡き王女のためのパヴァーヌ』。
パヴァーヌとは、16世紀から17世紀にかけて宮廷に普及していた舞踏の一種です。
初めて聴く人でも心地よく世界観に浸れ、印象派の美しさを感じられるこの作品は発表会曲としても人気で、それほど高難度ではありません。
しかし、優美さと繊細さを表現するためには、丁寧な練習が必要!
上品な雰囲気を出せるよう、角のないやわらかい音で演奏しましょう。
ピアノソナタk.545 ハ長調Wolfgang Amadeus Mozart

穏やかで優美な旋律と、軽快なリズムが調和した作品です。
3楽章で構成された本作は、まるでひとつの物語を聴いているかのような魅力に溢れています。
第1楽章は明るく爽やかな旋律が印象的で、第2楽章では柔らかい表情を見せながら、優雅な雰囲気を醸し出します。
第3楽章では遊び心のある明るい旋律が心を弾ませてくれます。
1788年6月に書かれた本作は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの繊細な技巧と豊かな表現力が存分に活かされており、華やかで洗練された響きを楽しめます。
心温まる旋律とピアノならではの魅力が詰まった本作は、気分転換や癒しの時間を求める方におすすめの1曲です。
【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】(81〜90)
風の即興曲中田喜直

アルバム『こどものゆめ』に収録された一曲は、まるで風が吹き抜けていくような爽やかな旋律が印象的です。
軽やかで流れるような自由なメロディが心地よく、グリッサンドの技法を取り入れた仕上がりは発表会でも魅力的な要素となっています。
本作は、流麗なフレーズと繊細なタッチが溶け合い、ピアノならではの表現力を存分に引き出した1分20秒の小品。
2011年のピティナ・ピアノコンペティションでC級の課題曲に選ばれた本作は、音楽の楽しさを感じながら技術を磨きたい方におすすめの一曲です。
手の大きさを考慮した自然な運指で、誰もが楽しく演奏できる工夫が施されています。
子供の領分 第5曲「小さな羊飼い」Claude Debussy

クロード・ドビュッシーが愛娘エマのために作曲した、ピアノのための組曲『子供の領分』の第5曲目。
付点リズムの静かなメロディが印象的な楽曲です。
この曲のポイントは、絶妙な間合い。
楽譜に書かれたリズムをそのまま再現するというよりは、音のない瞬間を大切にしながら弾いていくことが大切です。
とはいっても、ドビュッシーの作品にまだあまり触れていない方にとっては、感覚をつかむのが難しいはず。
有名ピアニストの名演などを参考に、間合いを研究してみると、ドビュッシーらしさをより早く習得できるかもしれませんよ。
アメイジング・グレイス作曲者不明

心に染み入る美しいメロディーが印象的な『アメイジング・グレイス』。
本田美奈子.さんの透明感あふれる歌声が、記憶に深く残っているという方も多いのではないでしょうか。
「素晴らしき神の恵み」を意味するタイトルが付けられたこの曲は、もとはイギリスの牧師ジョン・ニュートンの作詞による賛美歌。
アメリカでは「第二の国歌」として親しまれており、日本でも映画やドラマなどで広く使用されています。
16小節間のシンプルなメロディーの繰り返しで構成されているため、強弱や表現、アレンジに変化を加えながら、表情豊かに演奏しましょう!
渚のアデリーヌRichard Clayderman
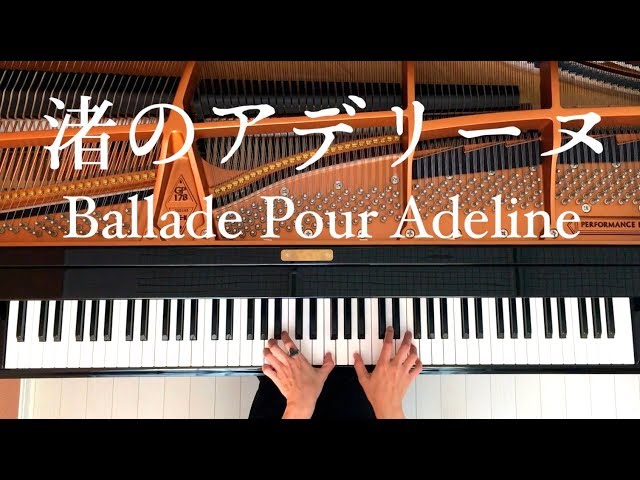
フランスのピアニスト、リチャード・クレイダーマンさんのデビュー曲である『渚のアデリーヌ』。
38カ国で発売されたレコードが、2,200万枚の大ヒットを記録した有名ピアノ作品です。
テレビやCMのBGMとして、あるいは電子ピアノに内蔵されている自動演奏の楽曲として、耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか?
期待感が膨らむ軽やかな前奏や、爽やかなメロディーに癒やされながら、力を抜いて演奏してみてくださいね!



