秋におすすめのクラシックの名曲
秋をイメージさせる、オススメのクラシックの名曲を紹介!
クラシックのなかには四季をテーマにした作品が多く存在します。
今回は直接「秋」をテーマにしたものから、秋っぽさをイメージさせる曲までをピックアップしてみました!
暗い曲調のものから明るい曲調のものまで、さまざまな曲調からチョイスしているので、お気に入りの雰囲気の曲が見つかると思いますよ!
エピソードやちょっとした豆知識も紹介しているので、クラシックが好きな方は、ぜひ最後までご覧ください!
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【秋ソング】秋の歌。秋に聴きたい名曲、おすすめの人気曲
- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選
- 【芸術の秋】珠玉のピアノ曲とともに|聴いて&弾いて楽しむクラシック
- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 人気のクラシックピアノ曲。日本人ピアニストの名演集
- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介
- チェロの名曲|奥深い音色を味わえる珠玉のクラシック作品を一挙紹介
- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽
- クラシックアレンジで聴くディズニーの名曲。おすすめの人気曲
- 【本日のクラシック】今日聴きたいオススメのクラシック音楽と名演集
秋におすすめのクラシックの名曲(51〜60)
バレエ「火の鳥」組曲Igor Stravinsky

もともとは法律家を目指していたという異色の経歴を持つロシアの作曲家、イーゴリ・ストラヴィンスキーさんは「カメレオン作曲家」と称される異才です。
有名なバレエ3部作を作曲しただけでなく、新古典主義を掲げた作風へと変化し、晩年は古典的な宗教音楽を作曲し続けた、という型にはまらない多彩な作曲家として、20世紀の音楽史に多大なる影響を及ぼしています。
そんなストラヴィンスキーさんによる『火の鳥』は、先述したようにバレエ3部作の一角を占める重要な楽曲。
実は手塚治虫さんの有名な作品『火の鳥』は、このバレエ曲『火の鳥』を手塚さんが実際に見て、作品の着想を得たというエピソードがあるのです。
そんな逸話に思いを寄せながら過ごす芸術の秋……なんともぜいたくな時間ですよね。
青く美しきドナウJohann Strauss II

ヨハン・シュトラウス2世が1867年に作曲したウィンナ・ワルツがこちらです。
ウィンナ・ワルツとは19世紀のウィーンで流行したワルツで、3拍の長さが均等ではなく、2拍目をやや早めに演奏されました。
『ウィーンの森の物語』と『皇帝円舞曲』とともにヨハン・シュトラウス2世が作った3大ワルツの一つと称され、オーストリアでは第二の国歌として親しまれています。
もともとは合唱曲としてつくられましたが、歌詞は時代に合わせて新しいバージョンに何度かかきかえられています。
「四季」-12の性格的描写 Op.37bis 10月「秋の歌」Pyotr Tchaikovsky

現代のアーティストにも大きな影響を与えた偉大な作曲家、ピョートル・チャイコフスキー。
多くの名作を作り出してきたチャイコフスキーですが、その中でも特にオススメしたいのがこちらの『「四季」-12の性格的描写 Op.37bis 10月「秋の歌」』。
四季にまつわる民衆の生活や、四季そのものを描いた作品なのですが、本作は秋が訪れ木の葉が落ちていくような、切なさを感じさせる暗い旋律が魅力です。
ぜひチェックしてみてください。
四季 作品67より「秋」Alexander Glazunov

19世紀の中盤辺りから20世紀の前半にかけて活躍した作曲家にして、教育者としての顔も持つロシア出身のアレクサンドル・グラズノフ。
幼少期から神童と呼ばれるほどの才能を発揮し、作曲者としてさまざまな作品を残したことはもちろん音楽院長として後進の育成という点においても多くの功績を残したグラズノフですが、こちらの『四季』はロシアの雄大な景色が目に浮かぶようなロマンチックなバレエ音楽で、彼の作品の中でも人気の高い作品です。
吹奏楽としてアレンジされ、好んで演奏されていることでも知られていますね。
そんな『四季』から今回の記事のテーマにふさわしい『秋』を紹介しましょう。
収穫祭をテーマとしているとのことで、繊細な響きを持ち合わせながらも全体的にダイナミックな演奏が楽しめますよ。
物悲しく寂しげな秋といったイメージとはまた違う、ロシアならではの秋の景色を思い浮かべながら聴いてみてくださいね!
秋におすすめのクラシックの名曲(61〜70)
交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」Anton Bruckner

副題の『ロマンティック』というタイトルでも知られる、オーストリアの作曲家にしてオルガン奏者のアントン・ブルックナーによって書かれた作品です。
ブルックナーといえば、難解かつ長い演奏時間の作品が多く、クラシック愛好者の中でも玄人好みの作曲家というイメージを持たれていますよね。
そんなブルックナーの作品の中では、この『交響曲第4番変ホ長調』は比較的短い演奏時間で親しみやすい旋律があり、ブルックナー初心者にもオススメできる作品です。
また、本人の名声を確立するきっかけとなった作品でもあります。
もちろん短い、といっても1時間弱の演奏時間はありますから、秋の夜長に腰を据えてじっくりと耳を傾けてみてくださいね。
ブルタバ(モルダヴ)Bedrich Smetana

民族独立運動にも参加していたチェコを代表する作曲家であるベドルジフ・スメタナが、1874年から1879年にかけて制作した連作交響詩です。
その『わが祖国』の中でもとくに有名な『ブルタバ(モルダウ)』。
曲を詳しく知っていなくてもタイトルは耳にしたという人もいらっしゃるかもしれませんね。
穏やかで軽快にも感じられる短調の始まり、しばらくたつと弦楽器が多重的に折り重なり、厳かかつ緑の風景や川の流れが浮かんでくる音像です。
実際にヴルタヴァ川の流れを描写しているようで、どこか牧歌的なノスタルジックさが感じられるのではないでしょうか。
華やかな後半の長調とそれぞれの色を持つこの曲は、スメタナのチェコへの愛国心がこめられているチェコの第二の国歌ともいえる作品。
秋の美しい風景を思わせるようでじっくりと聴いていたい名曲です。
組曲「動物の謝肉祭」Camille Saint-Saëns
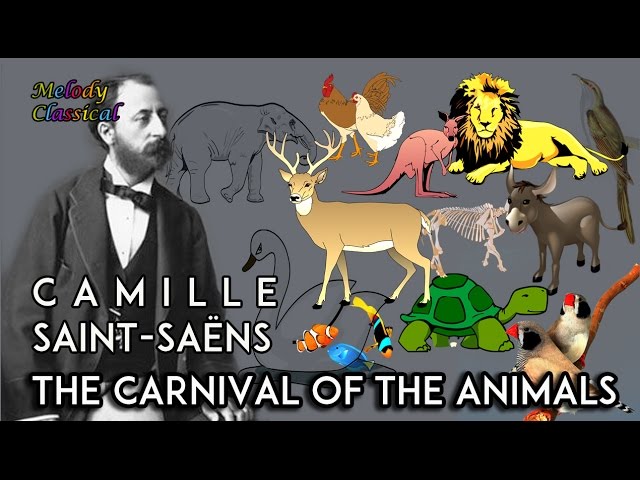
謝肉祭、いわゆるカーニバルとは四旬節の前に行われる、宗教的な意味合いを持つ行事ですが、現代においてはそういったこととは関係のない祝祭や年中行事全般を指して使われていますよね。
毎年8月の最終土曜日に浅草にて行われる「浅草サンバカーニバル」に参加して、夏の終わりと秋の始まりを感じるという方々も多いのでは?
そんな時に聴きたいクラシック曲が、この『動物の謝肉祭』です。
フランスの作曲家、カミーユ・サン=サーンスによって作曲された全14曲からなる組曲で、もともとは室内楽として作曲されたそうですよ。
既存のクラシック曲のパロディも含まれていて楽しいですよね。
個人的には『のだめカンタービレ』にてインパクトのあるシーンで使われていた、第7曲『水族館』を思い出します。



