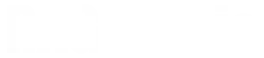クラシックピアノの名曲。一度は聴いてみたい世界の名演
誰もが一度は耳にしたことがある、心を癒すクラシックピアノの名曲たち。
ショパンの幻想的な調べ、リストの情熱的な旋律、ベートーベンの静謐な月光など、それぞれの作曲家が織りなす音の世界は、時代を超えて私たちの心に深く響きます。
技巧の粋を尽くした華麗な演奏から、静かに心に染み入る優美な曲まで、ピアノという楽器が奏でる至高の音楽をご紹介します。
クラシックピアノの名曲。一度は聴いてみたい世界の名演(61〜80)
マズルカ 第5番 作品7の1Frederic Chopin

ショパンの故郷でもあるポーランドの国民舞踏の一種で、弾むような軽快な3拍子のリズムが何とも心地よい楽曲である。
聴いているだけでつい踊りだしたくなるようなそんなショパンの隠れた名曲であるこの曲は、さほど技術的に演奏は難しくなさそうであるが、この特徴的なリズムやアクセントにより日本人がそれらしく演奏するにはなかなかの表現力が求められる。
ワルツ作品34の1「華麗なる円舞曲」Frederic Chopin

『ワルツ作品34の1 「華麗なる円舞曲」』。
ショパンの作品です。
ショパンの作品には「華麗なる大円舞曲」というものもあり、間違いやすいので要注意です。
「華麗な円舞曲」はとても華やかで、スピード感あふれる曲です。
同じメロディーが何度か転調されます。
それがとても華々しく、聴く人を虜にします。
「華麗なる第円舞曲」に比べると、少しマイナーかもしれませんが華やかさでは引けを取りません。
ぜひ聴いて下さいね。
調子の良い鍛冶屋Georg Friedrich Händel

バロック音楽というと、現在では圧倒的に大バッハが有名ですが、当時華やかな名声に包まれていたのはヘンデルでした。
彼の鍵盤曲の中では有名な「調子のよい鍛冶屋」は、ハープシコード組曲第5番ホ長調の終曲に付けられた通称です。
ペトルーシュカからの3楽章Igor Stravinsky

原始主義、新古典、12音列技法と、時代によってさまざまな作曲技法を用いたストラヴィンスキーです。
現在、彼の音楽は「火の鳥」「春の祭典」などのバレエ音楽に人気が集中していますが、「ペトルーシュカ」もそのひとつで、これはそのピアノ編曲版です。
カプリッチョ作品76の1Johannes Brahms

ドイツ3Bの一人であるブラームスの奇想曲第2番です。
イーヴォ・ポゴレリチは、旧ユーゴスラビアのベオグラード出身のピアニストです。
「異端」として知られ、さまざまなエピソードがあるが、演奏にもその異端さが型破りな演奏として出ており、曲の新しい側面を生み出す奏者でもあります。