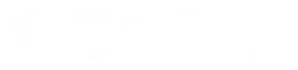カラオケで難しい曲に挑戦!歌いこなせたら称賛される楽曲
カラオケで「この曲歌ってみたい!」と思っても、いざ挑戦すると音域が広すぎたり、リズムが複雑だったり、思わぬ難関にぶつかることってありますよね。
歌うのが難しい曲は、技術的にどんな要素が壁になっているのでしょうか。
今回の記事では、カラオケで挑戦しがいのある高難度の楽曲を特集します。
どの部分が難しいのか、どんな歌い方が求められるのか、そういった視点にも触れていますので、歌の表現力を広げたい方はぜひチェックしてみてください!
カラオケで難しい曲に挑戦!歌いこなせたら称賛される楽曲(41〜50)
VanillaGACKT

GACKTさん2枚目のシングルで、代表曲の一つですね。
セクシャルで挑発的な歌詞と、スカのリズムを取り入れた独特のサウンドが特徴で、オリコン週間4位を記録し約25万枚を売り上げたそうです!
令和の曲をメインで知る方たちからは想像できないと思いますが、GACKTさんはかなり広い音域の持ち主で歌唱力も抜群です。
『Vanilla』は、B2~C5の音域のとおり、曲を実際に歌ってみると「低いし高い!」と思う方が多いはず。
また、テンポも速くラスサビでは転調し音がさらに上がっているため、初見で歌いこなすには大変かもしれませんね。
力強く歌えるように胸をしっかり響かせましょう!
カラオケで難しい曲に挑戦!歌いこなせたら称賛される楽曲(51〜60)
Tasty Beating SoundDa‑iCE
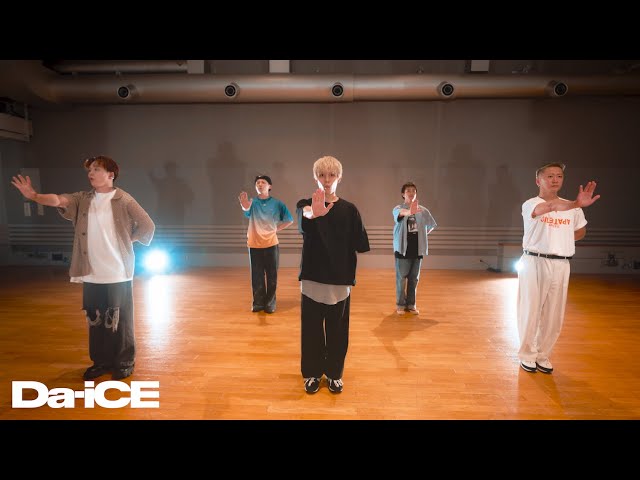
難曲が多いことで知られるダンスアンドボーカルグループ、Da-iCE。
こちらの『Tasty Beating Sound』は2025年9月にリリースされた楽曲で、直近のDa-iCEの楽曲ではかなりの難易度をほこります。
そんな本作の音域は、mid1D~hiC。
ただ高いだけではなく、下もそれなりに低いので、キーの調整が難しく、それに加えて音程の上下も激しく構成されています。
コミカルな曲調ということもあって、ロングトーンが少なめに仕上がっているのが、唯一の救いと言えるでしょう。
雰囲気とは裏腹に非常に難易度の高い楽曲なので、ぜひ挑戦してみてください。
ひゅるりらぱっぱtuki.

今、最も勢いに乗っている女性シンガーソングライター、tuki.さん。
『晩餐歌』で全国的な人気を集め、その後もヒットソングを連発していますよね。
そんな彼女の楽曲のなかでも、特に難しい楽曲が、こちらの『モエチャッカファイア』。
和風テイストのメロディが印象的な本作は、音程の上下が非常に激しい作品です。
ただでさえピッチを合わせるのが難しいのですが、加えてファルセットも連発するため、相当な難易度をほこります。
INAZMANOMELON NOLEMON

ツミキさんが作詞作曲を手がけ、みきまりあさんが歌うユニットの代表的な楽曲で、2021年8月13日にリリースされたシングルです。
エッジの効いたロックサウンドと稲妻のような衝撃をテーマにした歌詞が特徴で、ライブでも人気の高いナンバーです。
私も『INAZMA』のロック感や歌詞が好きでカラオケでよく歌います!
テンポが速いため、曲に慣れていないとブレスタイミングが取れずテンポに置いていかれそうになったり、擬音が多い歌詞のため、口が回らなくなったりするかもしれません……。
とにかくテンポに慣れてからカラオケで歌う方がいいですよ!
また、かなりの高音なのでテンション上げ気味で歌うと、声もよく出てオススメです!
アイドルYOASOBI

YOASOBIの通算19作目の配信シングルで2023年4月リリース。
テレビアニメ『【推しの子】』のオープニングテーマとなっています。
YOASOBIのコンポーザーであるAyaseさんは、ボーカロイドプロデューサーとしてもご活躍の方ですが、その、いわゆる「ボカロ曲」的なメロディ展開やボーカル処理は、このYOASOBIの楽曲でも最大限に発揮されていて、これを人間が歌って音源をそのまま再現するのは、なかなか難易度が高い…というか、ほぼ不可能じゃないかなと思います。
これをカラオケで歌うときは、まずはその複雑怪奇なメロディをしっかりと覚えた上で、あとはモノマネ的に楽しんじゃいましょう!
BOW AND ARROW米津玄師

羽生結弦さんが出演したMVも大いに話題を呼んだ、米津玄師さんによる楽曲『BOW AND ARROW』。
TVアニメ『メダリスト』の主題歌でもあり、フィギュアスケートのように流麗な疾走感を生み出すドラムンベース風のトラックは非常に現代的ですし、米津さんの見事なソングライティングセンスが際立つ楽曲となっていますね。
米津さんの高音ボーカルを生かしたメロディラインは音域の幅も広く、音程の上下の落差も激しいため難易度は高めですが、それに加えて特にこういったトラックを聴き慣れていない方であればリズム取りも難しく感じられるでしょう。
まずは楽曲を何度も聴いて、リズムとメロディ、そして歌詞がどのような形で構成されているのかを把握した上で練習してみましょう。
Naked Eyes (feat. Kohjiya)Bonbero

日本で間違いなく5本の指には入る非常にハイレベルなスキルを持っていることで知られるラッパー、Bonberoさん。
そんな彼の新曲がこちらの『Naked Eyes (feat. Kohjiya)』。
完全なラップの楽曲なので、「ラップなら歌えそう」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
とんでもなく難しいフロウがバースのいたるところでさく裂しているので、歌いこなすには相当なリズム感が求められます。
ラップに自信のある方は、ぜひ挑戦してみてください。