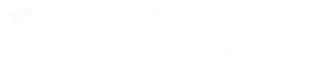中学生向けのレクリエーション人気ランキング
中学生向けの人気のレクリエーションを、ランキング形式で紹介します!
みなさんは「中学生が喜ぶレクリエーションは?」と言われたら、すぐに何か思い浮かびますか?
多くの人が「何だろう……」と悩んでしまうのではないでしょうか。
実際に中学生でも、大人数が集まるとなったときは、何のレクリエーションを選んだらいいのかわからないですよね。
そんなときは、ぜひこの記事をチェックして参考にしてみてください。
中学生向けのイベントでレクリエーションを考えているのなら、きっと役に立つと思います!
- 中学生向けの楽しい遊び。レクリエーションゲーム
- 中学生におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 中学生向けの盛り上がる学年レクリエーションまとめ
- 室内レクの人気ランキング
- 雨でも安心!体育館でできる楽しいレクリエーション
- 中学生にオススメの野外レクリエーション。楽しい外遊びまとめ
- 高校生が本気で盛り上がるレクリエーション!楽しいアイデア集
- 【盛り上がる!】学校の教室で遊べる簡単ゲーム。クラスで楽しむレクリエーション
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 【中学生向け】お別れ会を盛り上げるレクリエーションのアイデアまとめ
- 【子供向け】本日のおすすめレクリエーションアイデア集
- 高校生向けのレクリエーション人気ランキング
- 【子供向け】盛り上がるクラス対抗ゲーム。チーム対抗レクリエーション
中学生向けのレクリエーション人気ランキング(41〜50)
背中伝言ゲーム50位

背中に神経を集中させてゲームに挑戦!
背中伝言ゲームのアイデアをご紹介します。
伝言ゲームとは、お題を決めたら1番の人から順番に口頭や手ぶりなどでお題を次の人に伝えていき、最後の人にお題を正しく伝えるゲームですよね。
今回は口頭や手ぶりを使わずに、背中に書いて伝えてみましょう。
テーマは動物やキャラクターがオススメですよ!
慣れてきたら文章やロゴなど、難易度を上げて楽しむのもおもしろそうですね!
中学生向けのレクリエーション人気ランキング(51〜60)
キックベース51位

クラスメイトとチームで協力して戦いましょう!
キックベースのアイデアをご紹介します。
キックベースは、大人数だからこそ楽しめる遊びですよね。
チームに分かれて戦うことで、チームワークや協力の大切さを改めて感じながら、みんなで一緒に楽しめるでしょう。
また、思い出のあるグラウンドや体育館などの広いスペースを活用できるので、走ったり、ボールをけったりするアクションがダイナミックになり、心も体もリフレッシュできそうですね。
ゲームを通じてクラスメイトとの絆も深まり、思い出に残る楽しい時間を過ごしてくださいね。
ドッジボール52位

クラスメイトや部活のメンバーと盛り上がるゲームをお探しの方には、ドッジボールがオススメです。
単純なルールで誰でも楽しめるのに、チームワークや戦略が試されるので、参加者同士の絆を深められます。
激しい動きで運動能力が向上するだけでなく、瞬時の判断力や相手の動きを予測する力も養えるのがポイント。
生徒対教員での対抗戦などアレンジを加えても楽しめますし、普段はおとなしい人が意外な活躍を見せる瞬間もあるかもしれません。
室内から室外までさまざまな場所でトライできるので、ぜひ仲間と一緒に盛り上がってみてくださいね。
フルーツバスケット53位

英語にアレンジ!
フルーツバスケットのアイデアをご紹介しますね。
準備するものは遊びに参加する人数より1つ少ない数のイスです。
ルールはフルーツバスケットの遊びと同じですよ!
4つの季節ごとにチーム分けをしましょう。
「When is the season?」という掛け声でゲームがはじまり、真ん中に立っている人は特定の季節名を答えましょう。
呼ばれた季節名のチームは立ち上がり、座っているイスとは異なるイスに移動します。
「All seasons!」と言われた場合は、全員で立ち上がって座っているイスを交換してくださいね。
外国なぞなぞ大会54位

クイズは、レクリエーションの定番ですよね。
しかし「どんな問題を用意したらいいのかな」と悩みがち……。
そこで提案したいのが、世界のなぞなぞ大会です。
こちらは、世界各国で親しまれているなぞなぞに挑戦するという内容。
ただおもしろいだけでなく、その国ならではの価値観や文化を知れるのも魅力です。
中には英語を知っていないとわからない、難易度が高いものもあるので、答えが出ないようならヒントを出して楽しみましょう。
後出しジャンケン55位

気軽に楽しめる、道具もいらないレクリエーションをということであれば、後出しジャンケンはいかがでしょうか?
簡単すぎる、と思ってしまいそうですが、これが意外にあなどれないおもしろさがあるんです!
ジャンケンってどうしても勝ちたいと思ってしまいますよね。
普段はそうして勝つことを考えてやっているので、後出しで「負ける」ことを条件にされてしまうとグッと難しくなるんです。
もちろん「勝つ」ことを条件にしてもOK!
テンポよく、勝ち続ける、負け続けるというこのゲームは、トーナメント戦にして楽しむと大人数でも盛り上がれますよ!
並び替えゲーム56位
@ick_inc 並び替えゲーム! 見事成功できるか?! #ick株式会社#バズりたい会社#ゲームチャレンジ#チャレンジ #チャレンジ動画
♬ オリジナル楽曲 – ICK株式会社 – ICK株式会社
ヒントをもとに答えを導き出そう!
並び替えゲームのアイデアをご紹介します。
休み時間や自由時間にオススメしたいレクリエーションのアイデアですよ!
ペットボトルなどの飲み物を2本ずつ5種類用意したら準備完了!
飲み物を並び替えて、正解の並べ方を当てるシンプルなゲームですよ。
1人につき1つ並べ替えて、正解を導き出すのがポイントです。
指示役は現段階で正解している飲み物の数を伝えられると良いでしょう。
簡単そうに見えて頭を使うゲームです!
飲み物以外に文房具などでも応用できそうですね!