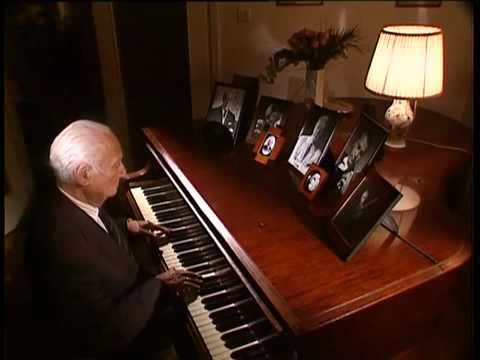美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
ピアノは、弾き手や表現方法によってさまざまな表情に変化する魅力的な楽器です。
繊細でいてダイナミックな優美さや、言葉には表せないような深みなど、その多彩な音色と豊かな響きは、ピアノ1台でオーケストラに匹敵するほどと言われています。
今回は、そんなピアノの音色を十分に堪能できる作品の中から、「美しさ」にフォーカスした曲を選びました。
ピアノを演奏するのがお好きな方も、鑑賞するのがお好きな方も、繊細な音のひと粒ひと粒を味わいながら、ピアノの魅力に浸っていただけたら幸いです。
- 切なく美しい!おすすめのピアノ曲まとめ
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【クラシックピアノ名曲】涙なしでは聴けない感動する曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【落ち着くクラシック】ピアノの旋律が心に染みる癒やしの名曲たち
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い(1〜10)
ピアノソナタ 第3番 第3楽章Alexander Scriabin

ロシアの作曲家アレクサンドル・スクリャービンが手掛けた、美しく繊細な作品。
1897年から1898年にかけて書かれた『ピアノソナタ第3番』の第3楽章は、静かで穏やかな音楽が特徴です。
「エタ・ダム(魂の状態)」という副題がつけられた本作は、スクリャービン自身の内面を反映しており、魂が悲しみやメランコリー、そして漠然とした愛や欲望の感情に包まれて浮遊しているようなイメージが描かれています。
さらに、彼自身がこの曲を演奏したとき「ここで星たちが歌う!」と叫んだことから、「星が歌う」という名でも知られています。
穏やかな海に浮かぶような繊細な感情表現は、聴く人の心を静かに洗い流してくれることでしょう。
静かな夜に、ぜひ星を眺めながら聴いてほしい作品です。
映像第1集 第1番「水に映る影」Claude Debussy

印象派音楽の先駆者として知られるクロード・ドビュッシー。
彼が1905年に作曲した本作は、全4集ある『映像』のうちの第1集のなかの1曲目『水に映る影』です。
水面に映る光や影の揺らぎを繊細な音色で描写しており、複雑な和音進行と流動的な旋律が特徴的。
それはまるで、水の動きを目で見ているかのような感覚に包まれます。
ドビュッシーは伝統的な音楽形式にとらわれず、非線形的な音楽の流れを重視しました。
本作は、ピアノの新しい音色を探求する試みでもあったのです。
水をテーマにした作品を好む方や、繊細な音の表現に興味がある方にオススメですよ。
子供の情景 Op.15 第7曲「トロイメライ」Robert Schumann

夢見心地な美しい旋律に思わずうっとりしてしまう、ロベルト・シューマンの『トロイメライ』。
子供心を描いた大人のためのピアノ作品として作曲された曲集『子供の情景 Op.15』の第7曲目に収録されている楽曲です。
曲集のなかでも特に有名なこの曲は、ピアノだけでなく、バイオリンやチェロ、フルートなど、さまざまな楽器で演奏されており、クラシックファンのみならず、多くの人の心をとらえています。
じっくり聴いて味わうもよし、ピアノで演奏としてその旋律と和声の美しさにひたるもよし!
静かな秋の夜長に、ゆったりとお楽しみください。
美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い(11〜20)
ノクターン 第20番 嬰ハ短調「遺作」Frederic Chopin
フレデリック・ショパンが1830年に作曲したノクターン。
全21曲からなるうちの、第20番は、姉のルドヴィカへの献呈とともに、『ピアノ協奏曲第2番』の練習用として書かれました。
ショパンの死後21年たった1875年に出版されたため、『遺作』と名付けられています。
レント・コン・グラン・エスプレッシオーネの穏やかなテンポで、左手の分散和音に対して右手が情感豊かな旋律を奏でる構成。
序奏部、中間部、再現部の三部構成で、美しい旋律と華やかな装飾音がメランコリックな雰囲気を引き立てています。
ショパンの内面的な感情や思索が反映された本作は、繊細な音色を味わいたい方にオススメです。
ピアノソナタ 第8番「悲愴」第2楽章Ludwig van Beethoven

ベートーヴェンの初期のピアノ作品を代表する『ピアノソナタ 第8番 悲愴』。
なかでも第2楽章は、ベートーヴェンが書いたメロディーのうちでもっとも美しいといわれ、多くの映画やドラマの挿入曲として使用されています。
シンプルなメロディーで音域もそれほど広くありませんが、それ以外のパートの音に厚みがあるため、バランスを注意深く聴きながら演奏しないとメロディーが埋もれてしまいがち。
聴く者の心を温かく包み込んでくれるゆったりと流れる優雅なメロディーと、それを支える重厚な和音を意識しながら、穏やかに演奏してみましょう。
ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2Frederic Chopin

美しい旋律に心洗われるフレデリック・ショパンの名曲。
彼が20歳の頃に作曲した本作は、現在でもさまざまな場面で使用されており、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
優雅なワルツのリズムと繊細な装飾音が魅力的で、静かでありながらも深い感動を与えてくれます。
メロディや表情の変化を際立たせるには、左手の伴奏を穏やかに演奏することが大切。
左右のバランスに気を配りながらも、機械的な音楽にならないよう、やわらかく温かい雰囲気の演奏に仕上げましょう。
カンタータ「主よ、人の望みの喜びよ」 BWV147J.S.Bach=Hess

ヨハン・ゼバスティアン・バッハが1723年に作曲したカンタータの一部として知られる本作。
イギリスのピアニスト、マイラ・ヘスによる1926年のピアノアレンジが特に有名です。
華麗な三連符のアルペジオに乗せて、美しい旋律が緩やかに流れていきます。
まるで清らかな小川のせせらぎのよう。
イエス・キリストへの信仰と喜びを歌った詩をもとにした本作は、クリスマスやイースターなどの祝祭でもよく演奏されます。
心洗われるような優しい音色に包まれながら、静かな祈りのひとときを過ごしたい方にオススメの1曲です。