【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
クラシック音楽の名曲は、テレビや映画、ショッピングモールなどで流れており、日常生活のBGMとして私たちの生活に浸透しています。
「この曲を聴くとなぜか涙が……」と感じていた楽曲が、実はクラシック音楽だったということも多くあります。
今回は、そんなクラシック作品のなかから、「泣けるほど切なく美しい」をテーマに、クラシック史に残る名曲を厳選!
繊細さと大胆さをあわせ持つクラシックならではの奥深い響きを、心ゆくまでお楽しみください。
- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介
- 人気のクラシックピアノ曲。日本人ピアニストの名演集
- チェロの名曲|奥深い音色を味わえる珠玉のクラシック作品を一挙紹介
- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち
- 【超上級】上級者でも難しい!難易度の高いピアノ曲を厳選
- ガブリエル・フォーレ|名曲、代表曲をご紹介
- 【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選
- 【本日のクラシック】今日聴きたいオススメのクラシック音楽と名演集
【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介(21〜30)
ラ・カンパネラFranz Liszt

イタリアのバイオリニスト、ニコロ・パガニーニの『バイオリン協奏曲第2番第3楽章』のロンド「ラ・カンパネラ」の主題を編曲して書かれたピアノ作品です。
パガニーニは超絶技巧でとくに有名であり、その演奏技術は「悪魔に魂を売り渡した代償として手に入れたものだ」と言われるほどでした。
彼の高度な技法がこの曲にもよく表れています。
ラ・カンパネラはイタリア語で鐘という意味をあらわし、冒頭の旋律から鐘の音が鳴り響いている様子が想起できますよね。
天使のセレナーデGaetano Braga

ガエターノ・ブラーガは19世紀に活躍したイタリアのチェリスト、作曲家です。
ピアノと弦楽器で演奏されることが多いですが、もともとは歌曲であり、これらの楽器の上にさらに歌の旋律が加わります。
死の床にある子どもが聞いた不思議な天使の歌声をめぐり、母親と子どもの対話の形式で物語が進んでいきます。
「ワラキアの伝説」よりという副題がついていますが、ワラキアとはルーマニア南部の地方名であり、そこに伝わる伝説を基に作曲されました。
【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介(31〜40)
星の夜Claude Debussy

フランス印象派を代表する作曲家クロード・ドビュッシーの若き日の習作です。
18歳頃に作曲された本作は、後の印象主義音楽への道を開いた重要な作品として評価されています。
星空の下で夢見る様子を描いた詩に、柔らかな和音が寄り添い、穏やかで幻想的な世界を作り出しています。
ピアノパートの複合和音や、減7和音を用いた優しいニュアンスが特徴的で、ドビュッシーらしい繊細な音色が魅力を思う存分堪能できる1曲です。
星空を眺めながら、ゆったりと聴いてみてはいかがでしょうか?
弦楽とオルガンのためのアダージョト短調Remo Giazotto
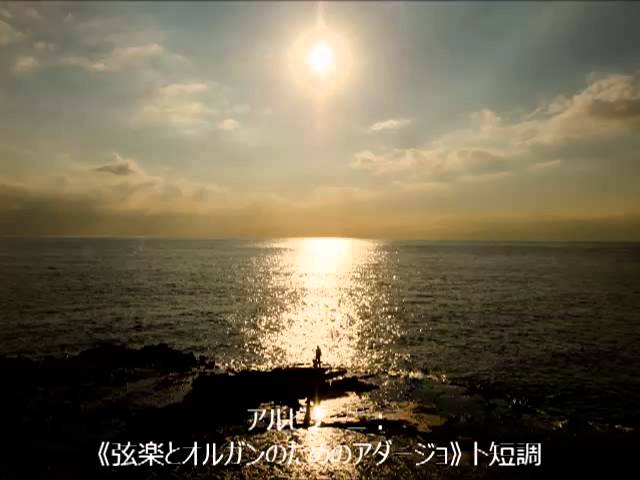
1958年に出版されたイタリアのレモ・ジャゾットさんが作曲した弦楽合奏とオルガンのための曲です。
こちらの曲は『アルビノーニのアダージョ』とも呼ばれ、1671年にイタリアで生まれたバロック音楽の作曲家トマゾ・アルビノーニが作った曲にレモ・ジャゾットさんが手を加えたものといわれていましたが、現在では実際はすべてジャゾットさんが作ったものとわかっています。
オルガンの楽曲というとバロック音楽をイメージしますが、こういった新しめの楽曲もすてきですね。
ため息Edward Elgar

バイオリンの美しい調べが心を打つ『愛の挨拶』で知られる、イギリスの作曲家エドワード・エルガーの楽曲。
1914年、第一次世界大戦の開戦直前に、弦楽合奏とハープ、オルガンのための作品として作曲されました。
幾重にも重なる重厚な弦楽器の音の後ろで、さりげなく奏でられるハープの音色が切なさを感じさせる、心に深くしみいる1曲です。
ハープのパートはピアノでも演奏されます。
さまざまな楽団の演奏で、楽器編成による音色の違いを楽しむのもおすすめですよ。
アヴェ・マリアGiulio Caccini

終始、厳かで切ない雰囲気を持った作品。
歌詞も旋律も単純ではありますが、単純だからこそ直接心に響く力を持った作品です。
この曲は「カッチーニのアヴェマリア」として、シューベルトのアヴェマリア、グノーのアヴェマリアとともに「3大アヴェマリア」と言われていましたが、実は旧ソ連のヴァヴィロフによる作品ではないかと推測されています。
彼は20世紀のギタリスト・リュート奏者であり、正式な作曲の教育を受けておらず自分の名前で作品を発表するのをためらったために、カッチーニの名前を出して作品を発表したのではないかと言われています。
愛の夢 第3番Franz Liszt

リストのピアノ曲集『愛の夢』の第3番はとても有名で、結婚式などでも耳にすることの多いロマンチックで美しいメインのフレーズが印象深い作品です。
実はこの『愛の夢』は全3曲で構成された作品であるというだけではなく、もともとは歌曲として作曲されたものであったということはご存じでしょうか?
女性が歌うソプラノ独唱の歌曲として1845年ごろに作曲され、作品には『おお、愛せるだけ愛してください』というタイトルも付いているのですよ。
数年後の1850年にリスト本人がピアノ独奏曲として編曲、現在多く耳にする『愛の夢』が生まれたという経緯があるのです。
ドイツの詩人、フェルディナント・フライリヒラートの詩がついた歌曲『おお、愛せるだけ愛してください』も、歌入りならではの美しさを味わえますから、合わせて聴いてみることをオススメします!



