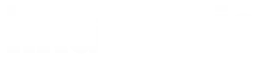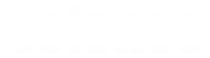中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
中学生の自由研究で「面白い!」と先生や友達を驚かせたい中学生のみなさんへ!
理科の実験や工作の中には、シンプルな材料でも意外な発見がある実験がいっぱいあるんです。
銅線と乾電池で電車を走らせたり、オレンジの皮で風船を割ったり…。
普段の生活では気づかない不思議な現象を、自分の目で確かめられるのが魅力です。
こりらでは、自由研究のヒントになる面白い実験や工作を紹介します。
理科が好きな人も、そうでない人も、きっと「なるほど!」と納得する発見があるはずですよ。
- 中学生向にオススメ!短時間でできる自由研究のアイデア集
- 【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア
- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
- 大人が夢中になる!トイレットペーパーの芯の工作アイデア集
- 【小学生向け】理科にまつわるゲーム・クイズまとめ
- 身近な材料で驚きの発見!面白い夏休み自由研究のアイデア
- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集
中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集(141〜150)
ワクチンについて調べる
ワクチンは英語でvaccineと表記します。
日本人にはちょっと覚えにくいつづりですね。
万能に思われるいわゆる「抗生物質」がうまく対処できないウィルス性の感染症のためにワクチンはさまざまな進化をとげてきました。
自由研究にはその歴史や功労者、国別で特徴あるワクチンへの取り組みなどをリサーチするのがいいと思います。
また開発が続く新型コロナウィルスワクチンの進ちょく状況などを製薬会社のホームページなども参考にして考察するのも。
今の時代にリアルに響く自由研究になるかも!
動画を作ってみる

動画制作を自由研究にしてみるのはいかがでしょうか?
動画制作には頭を使います。
このカットは何秒間見せるのがいいか、この字幕の表示秒数はこれでいいか、どういう構成にすれば視聴者の目を引けるのか、など……。
こういった、消費者の目を意識したものづくりという経験は非常に貴重で、ほかのことにもいかせるはずです。
最近は、スマホさえあれば簡単に動画制作ができるので取り組みやすい題材かもしれませんね。
手作りロボット

アイデア次第でオリジナリティを出せる手作りロボットも定番のアイデアです。
一口にロボットといっても、テーマによって出来上がる作品は大きく異なります。
たとえばですがラジコンのように走らせられるロボットを作ってもいいですし、掃除をしてくれる実用的なロボットを作るのもありです。
また掃除ロボットにしても、掃除機を搭載したものや、ブラシが駆動するものなどさまざまなパターンが考えられます。
ぜひ自分だけのロボットを考えてみてくださいね。
中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集(151〜160)
昔の教科書を調べよう

普段の授業に使っている教科書ですが、何度も改訂が加えられて現在の内容となっています。
そこで、改定前の教科書、もしくはもっと昔の教科書について調べて、違いを探ってみましょう。
図書館や歴史資料館などに昔の教科書が置いていないかを調べることからスタートするとスムーズですよ。
備長炭電池

備長炭を電池に変えて、電気が発生していることを確かめる実験です。
備長炭にティッシュペーパーを巻き、そこに食塩水をかけて、その上から備長炭を少しだけ出した状態でアルミホイルを巻けば電池が完成します。
電池が完成したら豆電球や音の出る機会をつないで、電気が発生しているかをチェックしてみましょう。
この作業によって備長炭がどうして電池に変わるのかを疑問に感じる人も多いかと思うので、理由もあわせて勉強すれば、科学の知識が深まりますね。
他の電池に変えられるものや、電気をとおす物質について知っていくのもおもしろそうですね。
和製英語

「コンセント」や「ワンピース」「カンニング」といった、日本で独自に使われている英語のような言葉を和製英語と呼びますが、いまや、カタカナ語は和製英語だらけです。
普段何気なく使っているカタカナ語が実は和製英語だった……そんなことがよくあります。
これらを集めまとめあげるだけでも、非常に実用的な研究といえるのではないでしょうか。
もう一歩踏みこんで、その言葉の由来まで調べられれば、さらに研究らしくなります。
縄文土器づくり

古代の人類の生活を支えた縄文土器、歴史の授業でしか目にする機会がないかもしれませんね。
そんな縄文土器がどのように作られていたのかを、自分の手で確かめてみるのはいかがでしょうか。
粘土をこねて土器の形に成形し、乾燥させるだけのシンプルな工程なので、気軽に楽しめることもポイントです。
教科書などの資料を参考にして再現する方向でもいいですし、オリジナルのデザインを考えてみるのも楽しいいかもしれませんよ。
実際に使えるくらい丈夫なものが完成すれば、楽しさがより強調されますよ。