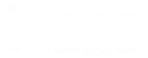【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
ピアノ発表会で演奏する楽曲は、誰しも悩んでしまうもの。
特に、曲の好みなどがはっきりしてくる小学生くらいのお子さんの発表会曲となると、どんな曲を選べば発表会映えするのか、考えてしまいますよね。
そこで今回は、小学生のお子さんが発表会の舞台で演奏するのにピッタリのピアノ曲をピックアップしてみました。
どれも比較的難易度が低く、演奏しやすいものばかりです。
楽曲の構成や演奏のコツにも触れているので、ぜひこれから迎える発表会の選曲の参考にしてみてください!
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】小学生・高学年にオススメのクラシック曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【ピアノ発表会】小学生・中学年におすすめのクラシックの曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【ピアノでディズニーの名曲を】発表会にもおすすめの簡単な楽曲を厳選
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
- 【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介
- 【ポピュラーピアノ】観客の視線集中!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめポップス曲
【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち(91〜100)
シンフォニア No.1ハ長調J.S.Bach

明るく快活な三声のピアノ旋律が美しい小品で、1720年に息子の教育のために書かれた作品です。
冒頭から流れるように展開される主題は、上声部から中声部、下声部へと優雅に受け継がれ、バロック音楽ならではの緻密な対位法が光ります。
本作は、途切れることのない旋律線と心地よい和声進行により、聴き手を魅了する魅力に満ちています。
パッセージがはっきりと聞こえ、フレーズのつながりも自然で、小学校高学年の子供たちにぴったりの演奏曲です。
きらびやかな音の重なりと豊かな表現力で、発表会の舞台を華やかに彩れることでしょう。
お菓子の世界 第14曲 「鬼あられ」湯山昭

きらきらと硬質なピアノの響きが印象的なアルバム『お菓子の世界』に収録された小品です。
1973年に制作されたこの楽曲は、1分25秒という短い時間の中に、和と洋の要素を見事に融合させた独創的な世界を描き出しています。
イ短調の4分の4拍子で始まり、不協和音とスタッカートを巧みに操ることで、硬くて跳ねるような音の表現を実現。
3声のパートや複雑なリズム、テーマの変奏など、演奏の難しさと魅力を兼ね備えています。
発表会やコンクールで演奏されることも多く、表現力を試される作品として愛されています。
プログラムの締めくくりに効果的な一曲として、クラシック音楽の新しい魅力を求める方におすすめです。
【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち(101〜110)
ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1「子犬のワルツ」Frederic Chopin

躍動感がありつつどこか懐かしさを感じさせる曲調が魅力的な、フレデリック・ショパンの『ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1』。
『子犬のワルツ』としておなじみのこの曲で繰り返し登場する明るく愛らしい旋律は、子犬が自分の尻尾を追いかけてクルクル回る様子を表しているとされています。
この曲を弾く際には、軽やかな右手の旋律と左手の分散和音のバランスを取りながら、曲が持つ天真らんまんなイメージを大切にしつつ、クリアな音色で表現するのがポイントです。
練習を重ね、細かいパッセージを丁寧に弾けば、きらびやかな舞台にふさわしいパフォーマンスができますよ!
こどものための連弾曲集「エチュード・アレグロ」中田喜直

ハ長調で書かれた連弾曲は、明るく勢いのある雰囲気で、子どもの豊かな音楽性を育める作品です。
右手の16分音符のパッセージでは音の粒を揃えて弾くテクニック、左手では表現を豊かに旋律を歌わせていきます。
中間部では変イ長調への転調があり、ペダルを使いながらレガートな演奏が要求されます。
最後には華やかなグリッサンドが登場し、本作は1956年に発表会などで人気の高い曲となりました。
発表会やコンクールでレパートリーとして用意される方にもおすすめです。
また、技術的な向上と音楽的な表現力を高めたい方にも最適な作品となっています。
野ばらに寄せてEdward MacDowell

アメリカの作曲家エドワード・マクダウェルが1896年に作曲した『森のスケッチ Op.51』の中の1曲。
穏やかで心洗われるような美しいメロディが印象的な作品です。
音数はそれほど多くありませんが、メロディラインが左右にちりばめられているため、常にメロディがどこにあるのか意識しつつ、伴奏と音量のバランスをとりながら弾いていくことが大切です。
楽譜のメロディ部分に色を付けて、視覚でも区別できるようにしておくと、より意識しやすくなりますよ!
ガボットFrançois-Josehp Gossec

タイトルを知らなかったとしても、メロディを耳にすれば「あの曲か」と思い当たるはず!
テレビ番組やCMのBGMなどでもおなじみの『ガボット』は、もともとはフランスの作曲家フランソワ=ジョセフ・ゴセックによるオペラ作品の中で使われた楽曲で、本来はバイオリンとオーケストラによって演奏される作品です。
この楽曲の上品な軽やかさの秘密は何といってもスタッカートの多さで、下から上へと動く左手の伴奏は慣れないとミスタッチが多くなってしまうかもしれません。
中間部からスラーなどを使った繊細で優美な展開へと変わるところにも注意しつつ、メリハリをつけた演奏を心がけましょう。
ウクライナ民謡による7つの陽気な変奏曲Dmitri Kabalevsky

多彩な子供向けのピアノ曲で知られるドミトリー・カバレフスキーさんが手がけた『ウクライナ民謡による7つの陽気な変奏曲』は、ウクライナ民謡の魅力あふれる1曲。
各変奏はそれぞれ異なる雰囲気を持っており、演奏技術の向上はもちろん、表現力の幅も広げてくれます。
特に軽快な第6変奏や、情熱的なコーダは演奏効果も抜群!
カバレフスキー作品のなかでも、発表会で取り上げられる機会が少なめの作品なので、定番曲ではなく誰とも被らなさそうなインパクトのある曲を演奏したいお子さんにオススメです!