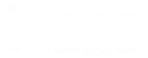【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
ピアノ発表会で演奏する楽曲は、誰しも悩んでしまうもの。
特に、曲の好みなどがはっきりしてくる小学生くらいのお子さんの発表会曲となると、どんな曲を選べば発表会映えするのか、考えてしまいますよね。
そこで今回は、小学生のお子さんが発表会の舞台で演奏するのにピッタリのピアノ曲をピックアップしてみました。
どれも比較的難易度が低く、演奏しやすいものばかりです。
楽曲の構成や演奏のコツにも触れているので、ぜひこれから迎える発表会の選曲の参考にしてみてください!
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】小学生・高学年にオススメのクラシック曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【ピアノ発表会】小学生・中学年におすすめのクラシックの曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【ピアノでディズニーの名曲を】発表会にもおすすめの簡単な楽曲を厳選
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
- 【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介
- 【ポピュラーピアノ】観客の視線集中!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめポップス曲
【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち(111〜120)
ソナチネ 第8番 第1楽章Muzio Clementi

豊かな響きと軽やかな旋律が印象的なピアノ曲を求めているなら、こちらの作品をおすすめしたいと思います。
ト長調の明るい調性で綴られた本作は、華やかで躍動感のあるメロディと、それを支える力強い伴奏が見事に調和しています。
1797年に出版された教育的作品でありながら、コンサートピースとしても十分に通用する芸術性を備えています。
順次進行を多用した優美な第1主題と、忙しなく動き回る第2主題という対照的な旋律の掛け合いも聴きどころです。
技巧的な面白さと音楽的な魅力を兼ね備えた本作は、ピアノの表現力を存分に引き出したい方や、華やかで力強い曲調を好む方にぴったりの1曲となっています。
春Samuel Maykapar

発表会曲やコンクールの課題曲として取り上げられることの多い、ウクライナ出身の作曲家兼ピアニスト、サムイル・マイカパルの『春』。
穏やかな春の訪れを感じさせる、ゆったりとした曲調の作品です。
中間部は少し活発な印象になるため、短い中でも変化をつけやすい作品といえるでしょう。
宮廷音楽のような上品さを損なわないようなめらかにレガートで演奏し、伴奏の音量を極力抑えながら、やさしい音色で演奏できるといいですね。
アレグレットAnton Diabelli

こちらの『アレグレット』はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンに師事していたというオーストラリア出身の作曲家、アントン・ディアベリによるピアノ曲です。
クラシックに詳しい方であれば、ベートーヴェンの『ディアベリ変奏曲』などが発表された経緯のなかでアントン・ディアベリの存在があったことをよくご存じでしょう。
そんなディアベリによる『アレグレット』は古典派らしい作風をしっかり味わえるため、古典派の世界に触れてみたい方にピッタリ。
スタッカートは歯切れよく音の強弱をしっかり意識し、オーケストラを再現するような迫力のある演奏で、ぜひ発表会の主役をものにしてください!
おどりとうたと中田喜直

「踊り」と「歌」の2つの要素が織り込まれた、魅力的なピアノ独奏曲です。
リズミカルな和風の旋律と、柔らかな歌心が見事に調和しており、夏の夜の情景が目に浮かぶような印象的な一曲となっています。
「5/8拍子」による変拍子やシンコペーションを取り入れた躍動感があふれる「踊り」のパートと、優美な和音の上で奏でられる「歌」のパートが交互に現れ、聴く人の心を惹きつけます。
ご家族で楽しめる発表会向けの曲を探している方や、和の雰囲気を大切にしながらリズム学習を深めたい方におすすめです。
スタッカートやペダリングの工夫で、さらに表現の幅を広げることが可能な学びがいのある作品といえるでしょう。
魔法の木William Gillock

20世紀に活躍したウィリアム・ギロックは、ピアノ教師であり音楽教育の分野において多くの作品を残した作曲家です。
「音楽教育界のシューベルト」と称されるほどのメロディの美しさを持ち合わせながら、それほど高度な技術を必要としない彼のピアノ曲は、初級から中級向けのピアニストたちにも好んで演奏されているのですね。
今回紹介している『魔法の木』はいわゆるアウフタクト、最初の小節線の前に現れるフレーズが特徴的で前半は左手が旋律を奏でることもあって、左手の良い練習となるでしょう。
中間部で旋律を弾くのが右手へと切り替わるなど、ある程度ピアノに慣れた方でないと難しく感じる場面も多々ありますが、この楽曲を弾きこなせれば中級者への道が開かれるかもしれません!
ピアノソナタ 第11番 K.331 第3楽章「トルコ行進曲」Wolfgang Amadeus Mozart

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトのピアノ作品の中でも特に有名な『トルコ行進曲』。
実は『ピアノソナタ 第11番 K.331』の第3楽章であり、もとは独立した作品ではありませんが、現在では単独で演奏される機会も多く、発表会の定番曲としても人気の1曲となっています。
聴きなじみのある覚えやすいメロディですが、曲全体のレベルとしては決して易しくありません。
モーツァルトらしい、緻密に計算され並べられた音たちを正確に弾きこなすのは至難の業。
しかし、弾けたときの達成感は格別です!
アヴェ・マリアFranz Schubert

フランツ・シューベルトの名曲『アヴェ・マリア』。
シューベルトの最晩年の作品として知られている楽曲で、オペラでも積極的に歌われています。
そんな『アヴェ・マリア』は、非常に魅力的な音楽ですが、シンプルなメロディーと和声進行で構成されているため、とっても弾きやすいんです!
ゆったりとしたテンポをキープしながら優雅なイメージで演奏しつつ、単調にならないようしっかり旋律を歌いながら、丁寧で美しい演奏に仕上げられるとよいですね。