【おすすめ】交響曲&宗教曲の大家・ブルックナーの名曲を厳選
交響曲と宗教音楽の大家と知られた、オーストラリアの作曲家兼オルガニスト、アントン・ブルックナー。
本記事では、重厚感のある曲調や、敬けんなカトリック教徒であったことがうかがえる宗教色の強い作風で知られる彼の作品の中でも、名曲として幅広く知られている作品をご紹介します。
オーストリアの豊かな自然と荘厳なバロック建築の教会を思わせる優雅で壮大な風景が見え隠れする、ブルックナーらしい深みのある作品の数々を、動画と解説あわせてお楽しみください。
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【ロマン派の名曲】魂を揺さぶる珠玉の有名作品を一挙紹介!
- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介
- 【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選
- グスタフ・マーラーの名曲。人気のクラシック音楽
- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽
- ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽
- 【ハイドン】名曲、代表曲をピックアップ!
- 【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽
- 【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!
- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介
- ドヴォルザークの名曲。人気のクラシック音楽
【おすすめ】交響曲&宗教曲の大家・ブルックナーの名曲を厳選(21〜30)
ピアノ小品 変ホ長調 WAB.119Anton Bruckner

『ピアノ小品 変ホ長調 WAB.119』は、オーストリアの偉大な作曲家のアントン・ブルックナーが1856年に作曲した作品で、演奏時間が約1分30秒と非常に短くブルックナーの他の大作とは一線を画す作品です。
この小品からは、彼の内面的な感受性や繊細さが感じ取れるでしょう。
パブリックドメインに属するこの曲は、ブルックナーのピアノ作品の中でも親しみやすく、彼のピアノ曲を弾いてみたいという方にも適した作品と言えそうですね。
交響曲第7番第2楽章Anton Bruckner

交響曲第7番はブルックナーの交響曲の中で、初めて初演が成功した曲とされ、第4番と並んで人気が高い曲の1つです。
第2楽章の作曲中に敬愛するワーグナーが危篤となり、ブルックナーは彼の死を予感しながら書き進め、ワーグナーが死去すると、ワーグナーのために「葬送音楽」とするコーダを付け加えました。
【おすすめ】交響曲&宗教曲の大家・ブルックナーの名曲を厳選(31〜40)
交響曲第9番Anton Bruckner

ブルックナーが取り組んだ最後の交響曲であり、作曲者が他界したときに未完の状態で残されました。
現在でも第四楽章の補筆完成の試みが続けられています。
全体として、明色系の豊かな音色にあふれ、序盤は若干早めのテンポで進み、中盤からは舞曲のような流れていくような美しい情景です。
終盤は夢を見るような静かな心地よさを感じ、終わりはあっさりとした感じで終わります。
無用な加減速がないので好感がもてます。
交響曲第9番 第3楽章Anton Bruckner

交響曲第8番完成後、1987年8月に作曲を開始しましたが、以前の作品の改訂で中断され、1891年にようやく集中できるようになりました。
たび重なる病気を押して、死の直前まで完成させようと力を尽くしましたが、第4楽章を欠いた三楽章までの交響曲となりました。
槍騎兵のカドリーユ WAB.120 第1番Anton Bruckner

1850年頃に作曲された『槍騎兵のカドリーユ WAB.120』は、6つのセクションからなる四手連弾のための作品で、19世紀の社交ダンス「カドリーユ」に基づいた軽快な舞曲の要素が含まれています。
交響曲の重厚な印象とは異なる、よりカジュアルで親しみやすいブルックナーの一面が垣間見える貴重な作品といえるでしょう。
クラシック初心者の方にもおすすめできる、ブルックナーの多様な才能を感じられる1曲です。
交響曲第7番Anton Bruckner

ブルックナーの交響曲というと、「壮大なスケール」「壮大な終結部」というイメージが根付いている。
この曲も例外ならず、全四楽章全てを演奏すると演奏時間は1時間を超える。
この曲の特徴はワーグナーチューバが用いられていることで、第二楽章と第四楽章では、その独特なハーモニーに包まれる。
ミサ曲 第1番 ニ短調Anton Bruckner
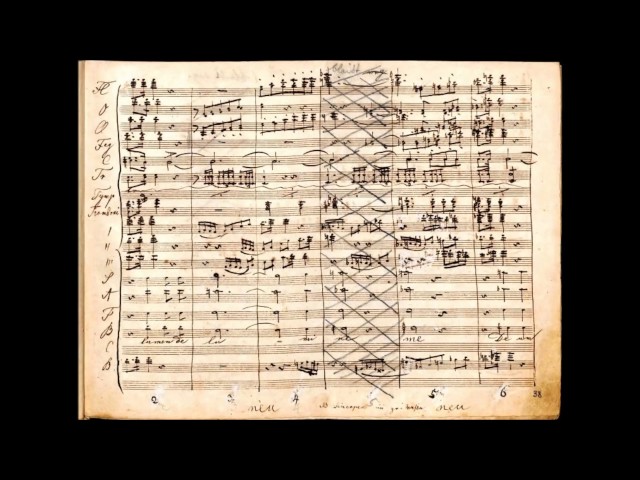
アントン・ブルックナーは敬虔なカトリック教徒であり、多くの宗教音楽を書き残しています。
この『ミサ曲 第1番』もその一つで、男女混声4部合唱とオーケストラで構成されています。
重厚かつ温かみのある曲調から、石造りの教会と荘厳なミサが目に浮かぶような1曲です。


